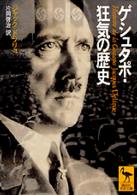内容説明
崩壊する日本社会への提言。『戦後史』の著者が、ついに戦後60年を語る。
目次
第1章 経済が社会を破壊している(日本の社会は人間の再生産に失敗しつつある;何が「子どもの危機」を深刻化させているのか ほか)
第2章 長期不況のほんとうの原因は何であったのか(中成長時代の経済運営の失敗;経済政策をめぐる議論の混乱 ほか)
第3章 日本型システムのどこに問題があったのか(不均衡はどのようにして拡大したのか;日本型システムの理解と評価 ほか)
第4章 民主制を機能させて有効な政府をつくる(民主制を機能させる条件;プログラム型政治の可能性を求めて ほか)
第5章 人間が育つ社会をつくる(新しい文明をつくる;学校教育のあり方を考える ほか)
著者等紹介
正村公宏[マサムラキミヒロ]
1931年東京生まれ。東京大学経済学部卒業。1974年以後、専修大学経済学部教授。2002年に定年退職し、現在は同大学名誉教授。『知識産業論』(中央経済社、1972年)で専修大学より経済学博士号
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
8
著者は繰り返し、「認識のリアリズムが実践のリアリズムの基礎である」と主張し、現実社会の分析と方向性でリアリストであることを強調します。同時に、イデオロギーであることに対しては強い拒否反応を示しています。社会のあり方として、社会民主主義を思考しているのだと思いますが、同時に個々の問題では不可知論に陥っている著者の迷走ぶりもありました。客観的であろうとするために、実践的ではない気がして、著者の問題意識が伝わりにくいのではと思いました。2014/06/07
takao
1
ふむ2023/11/14
れむ
0
タイトルで読むのを決めた。これは是非学生でも社会人でも関係なくいろんな人に読んで欲しい。日本は高度経済成長期で十分にフローを増やす事はできたのだからストックを増やすべき。しかし、当の時代の人は目先の通貨危機に目を奪われてまたフローを増やす努力に傾いてしまった。それが今の不況や社会問題の原因になっている。本当に今政治がすることは経済成長なのか?2013/08/14