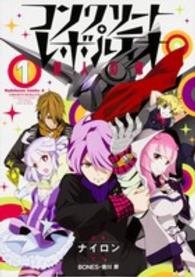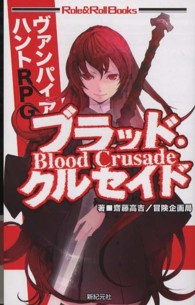内容説明
戦後、コンピュータが世界中で作られた。日本だけが生き残った。若きエンジニアたちの呼吸も伝わる未公開写真多数。
目次
第1章 計算機とエレクトロニクスはまだ出会っていなかった(リレーの時代;世界的にも珍しい非同期方式計算機―ETL Mark 1/2 ほか)
第2章 ラジオにも、鉄腕アトムにさえも「真空管」が使われていた(真空管の時代;国産初のコンピュータはたった1人の手で作られた―FUJIC ほか)
第3章 日本生まれの「パラメトロン」でコンピュータが作られた(パラメトロンの時代;最初のパラメトロン式コンピュータ―MUSASINO‐1 ほか)
第4章 「トランジスタ」が日本の高度成長のバネになった(トランジスタの時代;エレクトロニクスの応用例として取り組まれた ほか)
第5章 計算機からコンピュータへ(コンピュータ産業の成立までの道のり;もう1つのコンピュータ産業への道のり ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
YO)))
11
本邦コンピュータ産業の前史となる国産電子計算機の開発を豊富な写真と共に概観する。 論理素子(0|1のビット情報を保持するためのパーツ)の実装が真空管→トランジスタと移り変わる過渡期において、コイルとコンデンサを用いた「パラメトロン」と呼ばれる日本独自の技術が発達した。2024/08/31
工作魂
1
日本におけるコンピューター創世記を、現存しない計算機の貴重なものも含め豊富な写真と共に、さまざまな視点からバランス良く、かつ簡潔にまとめられて非常に優れた本。2023/06/17
roughfractus02
1
1958年安部公房が見学したのはパラメトロン型電子計算機だったという。彼はこの機械を単なる計算機と捉えず「予言機械」と名付けて『第四間氷期』を書いた。本書はリレー、真空管、パラメトロン、トランジスタと急激に開発の加速する50~60年代に巨大計算機と呼ばれた機械の歴史を同時代SFアニメのエピソード等も織り交ぜつつ辿る。70年以後IBMに挑む「モスキート」(日本のコンピュータ産業の綽名)が試行錯誤しつつ非同期型やパラメトロン等独自の技術開発した時代を、本書の豊富な図版は未知へ躍動する力として伝えるかのようだ。2017/04/24
noritsugu
0
国産機の歴史。ある意味楽しそうだなあ。2006/02/11
yos
0
1950年代から1960年頃にかけてのコンピュータが紹介されている。写真が多く、日本のコンピュータ業界の黎明を支えた数々の名機をビジュアルで見ることができた。各コンピュータについて、その成り立ちや開発陣のエピソードなどが、ちょっとした読み物風に、簡潔に記されている。国産初のコンピュータは、岡崎文次というたった一人の男が作った手作りのコンピュータであった話など、何度読んでもゾクゾクするいい話だ。2006/05/05