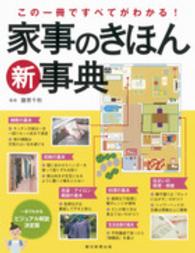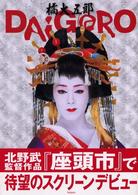内容説明
ゲーミングシミュレーションの論理と技法、倫理の問題まで、詳細に解説。
目次
1章 問題の所在
2章 人のコミュニケーション方式
3章 人のコミュニケーションモデル
4章 未来を語る言語としてのゲーミング
5章 ゲームデザインのプロセス
6章 ゲームの構成要素
7章 ゲーム技法の総覧
8章 ゲームの評価基準項目
9章 ゲーミングの可能性
10章 ゲーミングのデザインと評価
著者等紹介
デューク,リチャード・D.[デューク,リチャードD.][Duke,Richard D.]
現在、ミシガン大学名誉教授。1964年、ミシガン大学より博士号を取得する。1998年、定年退職するまで、40年余ミシガン大学建築・都市計画学部教授を務める。その間、同大学環境シミュレーション研究所長などを歴任する。約40年間にわたり、ポリシーゲーミングの領域において,先駆的かつ指導的立場で、研究開発に従事する。フルブライト委員会よりドイツに派遣されるなど、約40か国にておもにポリシーゲームの研究活動を指導、政府機関等、民間企業等向けに100以上のゲームを研究開発している。国際シミュレーション&ゲーミング学会の創立者(1968年)となり会長(1994年~1995年)を務める。さらに北米シミュレーション&ゲーミング学会の発起人(1969年)となる。また、ゲーミングシミュレーションに関する6冊の専門書を著作し、現在、集大成となるゲーミング専門書を執筆中である。これら、ゲーミングシミュレーションに関する業績により学術団体および専門家団体から各種の賞を受賞している。1994年、国際シミュレーション&ゲーミング学会賞を受賞する。1998年、日本シミュレーション&ゲーミング学会賞を受賞する
中村美枝子[ナカムラミエコ]
1988年、筑波大学大学院社会工学研究科博士課程単位取得退学。現在、流通経済大学経済学部教授。2001年ミシガン大学建築・都市計画学部客員研究員。1991年、国際シミュレーション&ゲーミング学会京都会議(ISAGA1991)にて参加型知的ゲームに遭遇以来、1994年に米国・ミシガン、1995年にスペイン・バレンシア、1996年にラトビア・リガ、1997年にオランダ・ティルブルグ、1998年に米国・ハワイ等、ISAGA、SAGSET、ABSELなどの関連国際学会に参加発表しながら、新しいゲームを求めている。この間、日本シミュレーション&ゲーミング学会理事、企画委員長、「Simulation&Gaming」誌日本セクションエディターなどを務めている。現在、集団意思決定、統計学へのゲーミングシミュレーション応用の研究を進めている
市川新[イチカワアラタ]
1971年、工学院大学工学部工学専攻科修了。工学院大学工学部助手、ハワイ州・日米経営科学研究所研修生などを経て、現在流通経済大学経済学部教授。1973年、ハワイ大学東西センターで日米外交政策研究ゲームに遭遇以来、企業経営ゲーム、都市経営ゲーム、社会システムシミュレーションの研究開発を行っている。1983年、フルブライト委員会により南カリフォルニア大学安全システム管理大学院に留学中、都市環境ゲームを学ぶ。1992年、オレゴン州・ポートランド州立大学都市研究センターに客員教授滞在中、協調ゲームを学ぶ。この間、日本シミュレーション&ゲーミング学会発起人、理事、事務局長、会誌「シミュレーション&ゲーミング」編集長、副会長などを務めている。また社団法人コンピュータエンターテインメントソフトウェア協会理事などを務めている
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
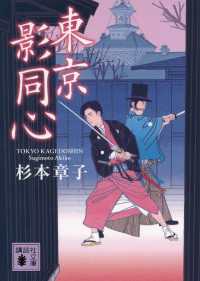
- 電子書籍
- 東京影同心 講談社文庫