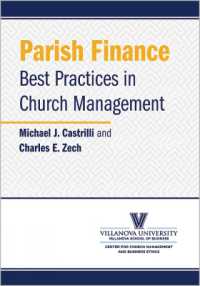内容説明
本書は臨床との戦いのなかで得た知識とその肉付けがあるだけに、臨床的身近さを感じさせる。クライン学派の理論と実践を学ぶには、フロイトはいうに及ばず、自我心理学、さらには自己心理学とは臨床素材の考え方にも扱い方にも異質なものがあるだけに、一度は古い着物を脱ぎ去って、装いを新たにしないとクライン理論を本当に理解することは難しいということも教えてくれる。
目次
第1部 心の中の世界と対象(意識と無意識;心の中の世界;心の中の世界の誕生;内的世界の発展 ほか)
第2部 対象と愛そして憎しみ(感情と思考と対象;対象と感情―その発達;自己愛;エディプス・コンプレックスとエディプス状況;終章:コンテイナー/コンテインドモデルの利用)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ステビア
14
わかりやすい。基本的には臨床に役立てるため読むことを想定されているようだ。2016/09/25
anchic
4
対象関係論について、わかりやすいが本当にざっくりとしか書かれていない本です。専門書並の値段でこの内容なので、正直微妙です。2011/09/19
huchang
3
私は分析が嫌いだ。それを強化したのは、分析を主戦場にしている知り合いで友達付き合いをしたいのが誰一人としていないというド主観だ。悪口ならいくらでも言えるが話題が逸れるから省略。それにも関わらず、臨床では少しは使わざるを得ない。だって便利だもん。だから一応定期的に関連書を読む。古典的分析には付き合いきれんがその礎の上に付き合える分析があるのね、でも私はやっぱクラインはノーサンキューだと再確認できた。完全に好き嫌いでしかないが。臨床で食っていこうという人以外は読む必要ないかな。分かりやすかったけど。2022/10/21
Jas
2
まだ「なんとなく」わかる段階。勉強が必要。2023/09/19
の箱
2
乳児が感じてるであろう快不快のプロセスを、授乳や排便という現実の現象を素材に解釈し構築することで、大人でも快不快をちゃんと受け取ることのできる状態になるための言語コードを作り上げたてことなんだろう。そのコードでは食欲や性や愛情や支配などの話を患者の抱える現実問題と織り合わせて語れるので、患者が無意識や己の過去と向き合って生きるためのツールとなる。ただ文字通り考えたら母乳以外や父子家庭とかどうなるのか?まさか悪だと主張するんだろうか。そういう注意書きもなくって。おっぱいや糞尿て隠喩でなく本気なんだろうか2018/09/15


![ハチャトゥリャン/《仮面舞踏会》よりワルツ[4手連弾] zen-on piano library](../images/goods/ar2/web/imgdata2/41116/4111609317.jpg)