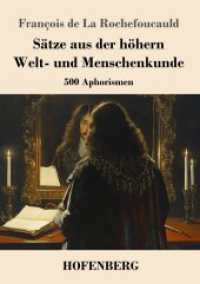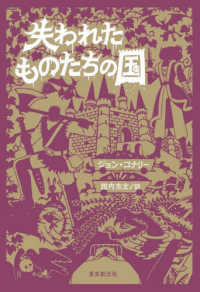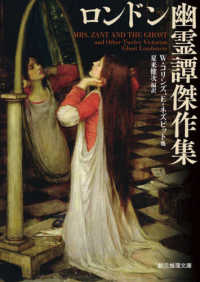出版社内容情報
プラトン、アリストテレス以来の西洋文明の伝統では、触覚はしばしば「最も下等な」感覚と捉えられ、知的なものや詩的なものと結び付いた「高貴な」感覚である視覚と対置されてきた。本書は、モダニズムの時代の芸術、文学、哲学の検討を通じ、20世紀前半における触覚の言説やイメージがこのような感覚の伝統的な階層区分に対して転覆的機能を持っていることを示す。そしてそのような転覆は、動物と人間、原始的なものと文明的なものなどの区分の揺らぎとも関わり、この時代の西洋的な価値体系の地殻変動にも連なっている。
序論 触覚とモダニズム
第一章 後期D・H・ロレンスにおける触覚の意義
一 接触=触覚と身体の真実
二 古代エトルリア文明と触覚的感性
三 「ローマ式敬礼」と触覚の政治
四 セザンヌの古代性、あるいは「りんごのリンゴ性」
第二章 スティーグリッツ・サークルにおける機械、接触、生命
一 スティーグリッツ・サークルの芸術家たちとD・H・ロレンス
二 マックス・ウェーバーと「触覚的親密さ」
三 写真の「機械性」と手という芸術の領域
四 アメリカ、機械、写真
五 スティーグリッツの写真における「女性的なもの」と「原始的なもの」
第三章 ヴァルター・ベンヤミンにおける触覚の批評的射程
一 ベンヤミンにおける二つの触覚
二 「近さの魔法」とエロス
三 触覚的なものと〈原史〉
四 模倣と「手」というトポス
五 翻訳の触覚
第四章 触覚的な時間と空間―モーリス・メルロ=ポンティのキアスム
一 接触、可逆性、否定性
二 奥行、垂直性、原初性―セザンヌと接触
三 時間、記憶、忘却の触覚性
結論
あとがき
注
索引
高村 峰生[タカムラ ミネオ]
1978年東京生まれ。東京大学文学部英文学科卒業。同、人文社会系研究科修士課程を修了。イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校で博士号を取得。
(Ph.D in Comparative Literature,2011年)。現在は神戸女学院大学文学部英文学科准教授。専門は20世紀の英米文学・文化、および比較文学/表象文化論。
共著に『文学理論をひらく』(木谷厳編・北樹出版、2014年)。『英文学研究』、『表象』、『ユリイカ』などに論文やエッセイを発表している。
内容説明
モダニズムにおける触覚表象を技術と身体の歴史的な境界面、つまり、われわれの環境認識を考察する。直接性の経験。
目次
触覚とモダニズム
第1章 後期D.H.ロレンスにおける触覚の意義(接触=触覚と身体の真実;古代エトルリア文明と触覚的感性;「ローマ式敬礼」と触覚の政治;セザンヌの古代性、あるいは「りんごのリンゴ性」)
第2章 スティーグリッツ・サークルにおける機械、接触、生命(スティーグリッツ・サークルの芸術家たちとD・H・ロレンス;マックス・ウェーバーと「触覚的親密さ」;写真の「機械性」と手という芸術の領域;アメリカ、機械、写真;スティーグリッツの写真における「女性的なもの」と「原始的なもの」)
第3章 ヴァルター・ベンヤミンにおける触覚の批評的射程(ベンヤミンにおける二つの触覚;「近さの魔法」とエロス;触覚的なものと“原史”;模倣と「手」というトポス;翻訳の触覚)
第4章 触覚的な時間と空間―モーリス・メルロ=ポンティのキアスム(接触、可逆性、否定性;奥行、垂直性、原初性―セザンヌと接触;時間・記憶・忘却の触覚性)
結論
著者等紹介
高村峰生[タカムラミネオ]
1978年東京生まれ。東京大学文学部英文学科卒業。同、人文社会系研究科修士課程を修了。イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校で博士号を取得(Ph.D in Comparative Literature、2011年)。現在は、神戸女学院大学文学部英文学科准教授。専門は20世紀の英米文学・文化、および比較文学/表象文化論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
moi
Mealla0v0