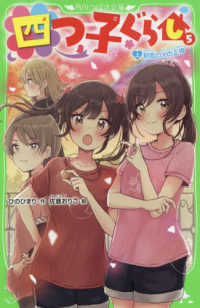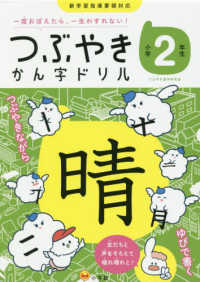内容説明
本気で短歌を学ぶ人へ、上達の秘訣大公開。骨太の入門。永久座右版。旅の歌の詠み方・佐藤佐太郎の歌会指導実録も収載。
目次
1 作歌入門のポイント(短歌を作りやすくする一〇のポイント;旅の歌を作りやすくする七つのポイント;吟行のポイント―積極的に新しい素材に立ち向かう)
2 作歌上達のポイント―作歌者への助言(私の作歌心得;作歌者への助言;結社と歌論)
3 推敲のポイントと添削例(推敲のポイント―よくある失敗;添削例―みずから「悟り得る」添削のポイント)
4 天の声抄―佐藤佐太郎の歌会指導(よい歌の条件;改善のポイント)
著者等紹介
秋葉四郎[アキバシロウ]
昭和12年(1937年)、千葉県生まれ。歌人・文学博士。昭和42年「歩道」入会、佐藤佐太郎に師事。現在「歩道」編集人(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
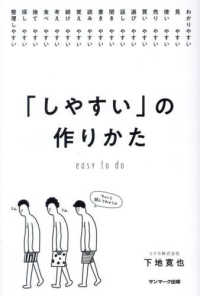
- 和書
- 「しやすい」の作りかた
-

- 和書
- 反逆の星 ハヤカワ文庫