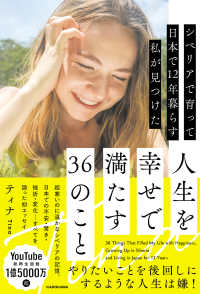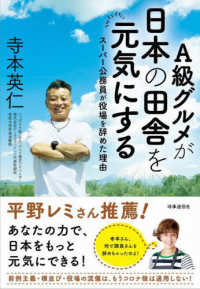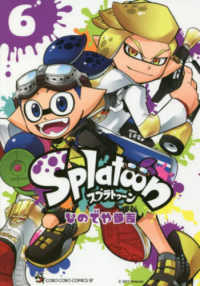内容説明
モノと仕事がつながり、めぐっていく。
著者等紹介
大西暢夫[オオニシノブオ]
1968年生まれ。写真家・映画監督の本橋成一氏に師事。1998年からフリーカメラマンとなる。25年間の東京での暮らしから、現在は生まれ育った岐阜県揖斐郡池田町に拠点を移す。ドキュメンタリー映画『水になった村』(2007年)で第16回EARTHVISION地球環境映像祭最優秀賞を受賞。写真絵本『おばあちゃんは木になった』(ポプラ社)で第8回日本絵本賞、『ぶたにく』(幻冬舎)で第58回産経児童出版文化賞大賞、第59回小学館児童出版文化賞を受賞。『ホハレ峠』(彩流社)で第36回農業ジャーナリスト賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
pino
105
フリーカメラマンの大西さんの「写真絵本」。子供はもちろん大人にとっても興味深い、ものの循環の話。最初に著者は和ろうそく職人の工房を訪ねる。丹念な作業を経て完成する和ろうそくの美しいこと!だけどここで感動するのはまだ早かった。工程に使われる蝋や和紙や副産物の行方を追うと藍染、焼物の窯元、墨作りの老舗などに繋がり、取材は日本各地に及んている。仕事はめぐり、捨てるものがない!なんて素晴らしいのだろう。最初と最後のページの和ろうそくの美しく揺らぐ炎のように伝統工芸が守られいつまでも続きますよう願わずにいられない。2022/04/02
☆よいこ
92
写真絵本。知識の本。音読18分▽愛知県岡崎市、和ろうそく職人⇒長崎県島原市、蝋の原料になるハゼの実の収穫をする。蝋職人が蒸して圧搾→福岡県広川町、しぼりかすは藍染め職人のもとで藍発酵につかう。藍建てにつかった残りの灰→大分県日田市の小鹿田焼のうわぐすりに。藍染めに使う蒅(すくも)は徳島県上板町で作られる。発酵に使うむしろは佐賀県東与賀町で作られる。和ろうそくの芯に使われる和紙は岡山県美作市のミツマタを使う。岡山県津山市の和紙職人がミツマタの皮から和紙をすく。燈心は奈良県安堵町の燈心草。真綿は滋賀県米原市▽2022/08/25
けんとまん1007
77
想像を超えた広がりと深さのある1冊。和ろうそくの独特の炎とゆらぎ。そこに至る、そこから広がる世界。原材料、加工に必要な素材、そこで出たもの・残ったもののつながりが、あまりにも広くて驚く。世の中に溢れる、半ばファッション化した言葉や情報・取組らしきもの(3R、SDGsなどに関する)は、この1冊の世界には、到底、太刀打ちできない。まさに、人は自然の一部でり、ものは、元の形に戻るものということを痛感する。2024/05/10
とよぽん
63
これまでに読んだ大西暢夫さんのどの著作からも「人間は自然の一部なのだ」ということが伝わってくる。和ろうそくの炎の魅力から始まって、和ろうそくをつくる工程をたどる。職人さんの仕事場に出かけて話を聞く。原材料は自然の木や植物、土であること。ろう、和紙、藍、むしろ、灯芯、墨、真綿、ものづくりは次々とつながって、捨てるところがなく自然の恵みを使い切る。見事だ。和ろうそく、すばらしい。2022/05/05
モリー
62
日々、様々な製品が生み出される。そして、小売店にはそれらが商品としてずらりと並ぶ。しかし、その商品の製造過程においては、不用とされ廃棄されるゴミが大量に発生する。人手不足に加えて円安の昨今、これらのゴミの処分費用を抑える事が企業にとっは生き残りをかけた重大事になっているのではなかろうか。製造過程で生じる産業廃棄物は、その場においてはただの厄介者かもしれないが、それを必要とする場所さえ見つかれば、立派な資源なのだ。和ろうそくの製造工程にゴミは生じない。全くもって驚きだ。この知恵を製造業界全体で共有すべきだ。2023/07/09