内容説明
野原が、村へ村は、街へ。うつりゆく時代の中で1本の木が見たものとは?日本の歩みをたどる風景絵本。
目次
50年後―明治時代のはじめ
75年後―明治時代の中ごろ
95年後―大正時代のはじめ
105年後―大正時代のおわり
110年後―昭和時代のはじめ
115年後―昭和10年
125年後―昭和20年
135年後―昭和30年
145年後―昭和40年
165年後―昭和60年
173年後―平成5年
平成20年の予想図
著者等紹介
島田アツヒト[シマダアツヒト]
昭和7年3月大阪市に生まれる。戦後まもない頃、「内外タイムス」に漫画を投稿、利根義雄氏の「漫画報」同人となる。その後、民家の漫画家、広瀬安美氏と知り合い親交をふかめる。日本の各地に残るカヤ葺き民家を訪ねて、ペン画で旅行誌に連載。絵本に民家や伝統産業をテーマとしたものが多い
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やすらぎ
190
ある一点から見つめたニッポンの風景絵本。大阪にある住吉大社の巨木は今も守られている。穏やかな一日が静かに過ぎていく。遥か昔の若木が大きく梢を広げている。遠く山嶺から流れ出る恵み、丘から吹きおろす風にゆられて湿原は多くの生命を育む。やがて村が生まれた。稲穂が垂れ収穫を祝う。どんどから高く舞う煙に平穏を願う。電気が引かれ姿を変えていく。鉄道を囲むように建物が立ち並ぶ。樹齢千年のくすの木は今も私たちを見つめている。「ちいさいおうち」のような絵本。過ぎ去りし時、失われた風景に切なさ漂う。その気持ちを大切にしたい。2022/11/19
ヒラP@ehon.gohon
19
一本のクスノキは、町の変化をじっと見つめてきたのですね。都市化されて街になった場所も、昔は素朴な田園風景だったことを実感しました。 明治中頃に丘陵に建てられた社が印象的です。高い建物に視界を遮られてしまいましたが、今も残っているのでしょうか。2019/12/27
絵本専門士 おはなし会 芽ぶっく
14
同じ場所に視点をい据えて、江戸時代から平成20年までを13枚の絵で描いている。目印は真ん中に立つ1本の木。一時太い綱をつけられ神木のように扱われているが、ラストは小さく描かれている。切り倒されなかったようですが…。2020/02/07
のん@絵本童話専門
4
図書館内で読んだ本なので簡単な感想ですが…初見で手に取った絵本ですが、緻密に細い線で描かれたモノクロの風景にとても惹かれました♪一本の大きな木を中心に、大正時代から現在まで、少しずつ野原が村になり、町になり…時代と共に変遷していく様子を描いています。大阪の住吉を描いたのだそう。2022/02/11
sarigreen
3
図書館で流し読み(見?)。1本の木を中心とした,江戸から平成までの移り変わる風景や人々の様子を,繊細なタッチで描いている。細かく描かれているので,隅々まで興味を持って眺めたくなる。なかなかの良本。2014/12/01
-

- 電子書籍
- マイナス感情を稼いで無限ガチャ【タテヨ…
-
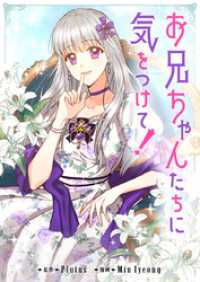
- 電子書籍
- お兄ちゃんたちに気をつけて!【タテヨミ…
-
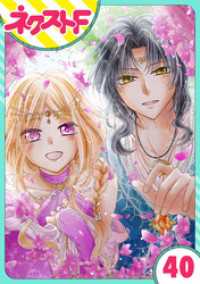
- 電子書籍
- 【単話売】蛇神さまと贄の花姫 40話 …
-

- 電子書籍
- ルポ 大阪の教育改革とは何だったのか …
-
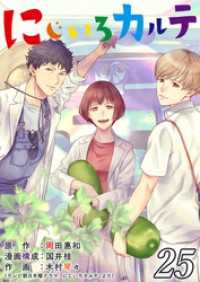
- 電子書籍
- にじいろカルテ【単話】 25 Rent…




