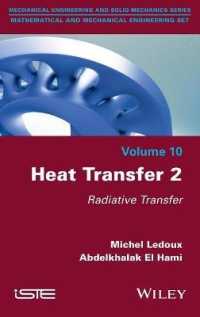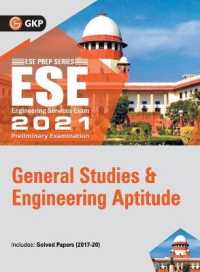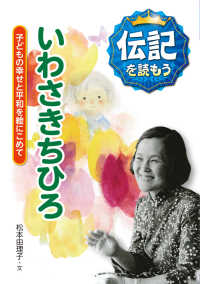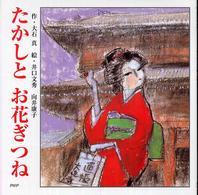出版社内容情報
〈デモでたたかう若者は何を守りたかったのか〉
絶望的な状況にあっても人々は、文学を読み、音楽を聴き、未来を思い描く。
迷いや葛藤を抱えて生きる人々、そして失われゆく都市の姿を内側から綴ったノンフィクション。
---------
都市から自由が消えていく様に ともに迷い、引き裂かれつつも、 そこで生きようとする人々の姿に迫っていく。
ミレニアル世代の著者が記録する 激動の一九九七年から二〇二〇年。
---------
それでも香港はそこに生きる人が愛さずにはいられない文化が息づく街である。
本土に?まれていく旧植民地の矛盾や葛藤、そして魅力を柔らかく繊細な感性で描く。
内容説明
家族との対立、高い家賃と狭い部屋、市民間の格差や分断…香港で生きることに苦悩する著者はやがてその街の文化の中に居場所を見出すが―都市から自由が消えていく様にともに迷い、引き裂かれつつも、そこで生きようとする人々の姿に迫っていく。ミレニアル世代の著者が記録する激動の一九九七年から二〇二〇年。
目次
二〇二一年、香港の地図
第1部(一九九七年;祭りとしきたり;パラレル・ワールド)
第2部(二〇〇三年;二十二人のルームメート;二〇一四年;五里霧中)
第3部(インターナショナル・スクール出身者;言語を裏切る者;工場へようこそ;煉獄の都市)
著者等紹介
カレン・チャン[カレンチャン]
1993年中国深〓に生まれ、香港で育つ。香港大学で法学とジャーナリズムを専攻。卒業後は、編集者・ジャーナリストとして活動する。香港のデモやカルチャーシーンを取材し、国内外に向けて執筆。「ニューヨーク・タイムズ」、「フォーリン・ポリシー」などに寄稿している。「ワシントン・ポスト」、「エコノミスト」で年間ベストブック(2022年)に選出されるなど、反響を呼んだ本書が、デビュー作となる
古屋美登里[フルヤミドリ]
翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まーくん
踊る猫
踊る猫
踊る猫
星落秋風五丈原