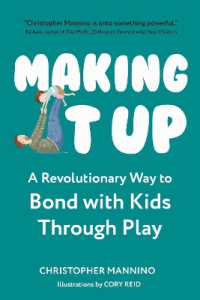出版社内容情報
《コミュニケーションで悩む人たちへ》
コミュニケーションや感情表現が上手できないと悩んだ著者はやがて、当たり障りなく人とやり取りする技術を身につけていく。
だが、難なく意思疎通ができることは、本当に良いこと、正しいことなのか。
なめらかにしゃべれてしまうことの方が、奇妙なのではないか。
「言語とは何なのか」「自分を言葉で表現するとは、どういうことなのか」の深層に迫る、自身の体験を踏まえた「当事者研究」。
--------------------------------------
自分だけのものであるはずの感情を、多くの人に共通する「言葉で表す」ことなど、どうしてできるのだろうか。
そして、人に「伝える」とはどういうことなのか――。
言葉、存在、コミュニケーションをめぐる思考の旅が始まる。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
101
「モヤモヤの正体」に次いで著者の作品は2冊目。非定型の発達者から見える日本社会のありように身をもって体験してきたからこそ現在がある。定型発達した「普通」の人たちの社会において「わかる」と「できる」は重視されている。それは人というのは統合されているはずだという人間観を持つ人の価値観だ。「うまくできない」非定型の発達をしてきた人にとり、「能力の欠如」ではなく、サナギ状態の生きながら死ぬ「胚胎期間」なのだ。この国で感じるのは絶え間なく「普通」についての教育を受け続けていること。その結果もたらされるのは同化だ。2022/08/13
*
33
読みながら「こんなに深く思考できる人がいるなんて絶望しかないわ」と思ったら〈絶望は内語の誤訳かもしれない〉と言われ、最近、自分が何者か問われるなと思っていたら〈「自分は何者か」という問いに潜む陰影に気づく〉が目に飛び込んだ。あぁ、全部バレてるんだ▼特定の障害ではなく、"非定型発達"と副題にあるのは救いだと思った。診断名がなくても、コミュニケーションに苦しんでいる人はいるはずだから。2022/06/21
水色系
21
「自身の生き難さを生きることが他の人にはできない。それが自分への尊重につながるのではないかと思っている。」(P214)これいいな。「まだら模様をちゃんとまだらに捉える」(P41)のあたりも。人には人それぞれのタイムラインがありそのなかで生きていてそれはあたりまえのことだ。人と比べたり安易な共感を得て安心したりしなくていいのだということ。2022/07/18
ぽんてゃ
11
僕はなにがわからないのかわからない時代を長く過ごした。僕はしゃべることはできなかったけれど、内面に関する言葉を諦めることはなく、そういう意味では言語に関して開かれていた 所々自分が感じていたような感覚があったと思う。鏡像の話の所で知的障害者が鏡を全然見ないらしいとの事で自分的に繋がったのですがニートひきこもりになった私も全く鏡を見なくなりました。家族と家は社会と程遠い。家では人間やれてるのに社会が絡むと無力とか微力になる。でも何者かを目指さないで自分のまま出来ることをやってこうって思えた。それしかない2022/09/06
umico
8
読書の日記に尹さんが出てきたので。読みながら、あまりに細かく分析されている自己と言語と他者について…開かれる思いもありつつ、しんどくなってしまった。普段あまりにもそこに無意識に生きているからか…使っていない筋肉を急に使うと疲れるような感じ。普段いかに自分が他者についても自己についても無自覚に生きているのかを知る。馴染むことを是として文章を読むのは豊かではない…と思いつつ、疲れるものはどうしようもなかった。「切り出した話題の断面がちゃんと僕のぎこちなさと馴染んでいく。」という表現が好きでした。2024/02/12
-

- 電子書籍
- 一間飛車で行こう! 将棋世界編集部 (…
-
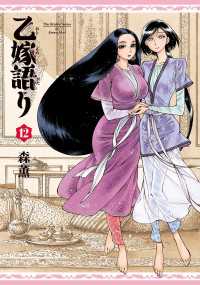
- 電子書籍
- 乙嫁語り 12巻 青騎士コミックス