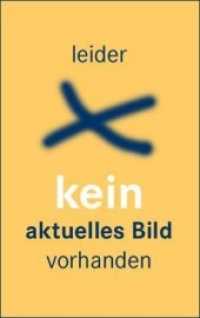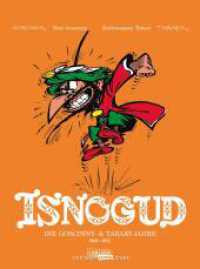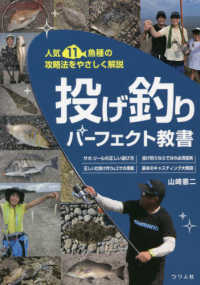内容説明
戦争は兵士たちの身体を無慈悲にかつ無意味に破壊する。失明、火傷、四肢切断…ピュリツァー賞受賞ジャーナリストが、イラク戦争に従軍したアメリカ陸軍歩兵大隊に密着。若き兵士たちが次々に破壊され殺されていく姿を、目をそらさずに見つめる。話題作『帰還兵はなぜ自殺するのか』に劣らぬ衝撃の前編、ついに翻訳!
著者等紹介
フィンケル,デイヴィッド[フィンケル,デイヴィッド] [Finkel,David]
ジャーナリスト。「ワシントン・ポスト」紙で23年にわたり記者として働き、2006年ピュリツァー賞受賞。その後イラク戦争に従軍する兵士たちを取材するために新聞社を辞めバグダッドに赴く
古屋美登里[フルヤミドリ]
翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケイ
116
New York Timesの最初の書評から、読む前の期待を高めてしまった。図らずも今年は既に2冊でこの誌との相性の悪さを感じている。「イリアス」以降最も素晴らしいとはいくらなんでも…。ブッシュ氏を非難するという姿勢が全面に出ている気がして、章の進め方に途中から嫌なものを見ている気分になった。独裁国家ではないのだから、徴兵制ではないのだから、向かう兵士達にも責任の一旦はありはしまいか。原題は「Good Soldiers」爆弾の前には、人は柔らかい肉でしかないのだと、まざまざと見せられた。2021/01/09
harass
99
『帰還兵はなぜ自殺するのか』の前編。著者はイラク派兵された中隊に帯同し取材しまとめたもの。一人称を廃し、中隊長や兵士たちを第三人称で客観的に描く。解説でトム・ウルフのニュージャーナリズムの後継者とあるが、なるほどと。現実の細々とした描写と容赦ない現実が短編小説のような読み応えがある。兵士たちを何度も襲う自己鍛造弾というのがでてくるが、これは成形炸薬弾とまた違うものだと、wikiで調べて理解。これは怖い。報道での戦争と違う実際の戦場を生きて死んで苦しむ兵士たち。良書。2019/09/22
白玉あずき
41
各章の冒頭、ブッシュ大統領のスピーチの「恥知らずなあさましさ」。世間知らずの若者達の肉体と人生を破壊し、「英雄」に仕立てる集団の欺瞞。いつものうんざりする光景がここにある。アメリカ合衆国の若者達の血を流さない為に、ドローンによる暗殺、ロボットによる戦闘を進めるなど、今はさらに「敵」に対する共感性と想像力を失わせる方向に向かっているらしい。いつもの事だが、読了後しばらくは「人間」なんてどうでもいいや病が再燃します。戦場とワシントンの距離を縮める事の不可能性と、現実を他人とは共有できない虚しさとやるせなさ。 2017/09/17
テツ
30
戦争は経済的なメリットがあったり、少なくとも古の時代においては様々なテクノロジーを進歩させるという側面も確かにあったんだろう。でもさ。イラク戦争当時、まだ成人して間もないこどものような兵隊達が、手を汚さず血を見ることもない国家の上層部の人間が煽る愛国心に翻弄されて、肉体も精神も苛まれて破壊されていく様子を見たら、そんなメリットなんていらないからやめてやれよと思うよな。戦争は人が死ぬから問題なんじゃない。膨大な数の人間から人間性を奪い去るから問題なんだ。神様がいるなら何とかしてやってくれ。2017/07/08
かもめ通信
25
これはもうとにかく読んでみてとしかいいようがない。ピュリツァー賞経歴を持つジャーナリスト、デイヴィッド・フィンケルが、2007年、イラクに派兵された大隊に同行して丹念に取材した従軍記。1人称を使わない「イマージョン・ジャーナリズム」という手法で書かれているのだが、 聞き役の「私」が仲介しない分、取材対象となった証言者たちの声がダイレクトに読者の耳に届き、臨場感がある。あの『帰還兵はなぜ自殺するのか』に登場していた兵士たちがいったいどんな体験をしていたのか、人が壊れていく様を克明に記した記録でもある。 2017/09/04