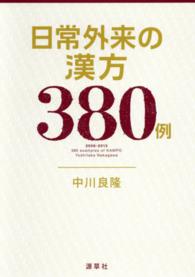出版社内容情報
二足歩行すらぎこちない――体を思い通りに使えない世界。極端な不器用が「発達性協調運動症(DCD)」であれば、日常のあらゆる場面が壁となる。本書は「知られざる発達障害」であるDCD当事者の生きづらさを共有し、「できて当然」という社会の圧力を問いなおす。
内容説明
二足歩行すらぎこちない―体を思いどおりに使えない世界とはどんなものか。極端な不器用や運動音痴は努力不足と見なされがちだが、それが「発達性協調運動症(DCD)」の症状であれば、日常のすべてが壁となる。運動が苦手なだけでなく、ボタンを留める、文字を書く、転ばず歩く―そんな「当たり前」ができない現実。本書は、「知られざる発達障害」である発達性協調運動症の当事者が抱える生きづらさを内側から共有し、社会が無意識に課す「できて当然」の圧力を問いなおす。
目次
プロローグ そしてディストピアが始まる
第1章 発達性協調運動症に関する基本事項
第2章 私のオートエスノグラフィー―床でゴロゴロしながら人生の大半を過ごしてきた
第3章 当事者の親へのインタビュー
第4章 当事者へのインタビュー
第5章 問題をどう解決するか
エピローグ もし発達性協調運動症の人が多数派だったら?
著者等紹介
横道誠[ヨコミチマコト]
京都府立大学文学部准教授。1979年生まれ。大阪市出身。文学博士(京都大学)。専門は文学・当事者研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ネギっ子gen
64
【床でゴロゴロしながら人生の大半を過ごしてきた】発達性協調運動症は、協調運動能力の障害を特徴とする発達障害。略称はDCD。この障害の当事者が抱える生きづらさを共有し、社会が無意識に課す「できて当然」の圧力を問い直す書。巻末に文献。「あとがき」で、<発達性協調運動症に関する書物はいまだに少なく、一冊まるまる発達性協調運動症をテーマとした「当事者本」や「インタビュー集」となると、国内では本書が初めてだと思われる。これから発達性協調運動症に関する認知が広がり、多くの当事者が救われていくことを願う>と。同感だ。⇒2025/09/30
haruka
29
ケーキが切れない非行少年たちは"境界知能"だったけど、こちらは知能ではなく、運動神経が悪くて不器用な人たち(DCD)のお話。あまり知られていないがそれも「障害」 の一種なのだ。 逆上がりができない、大縄跳びにうまく入れない。自転車が苦手、ドッジボールが恐怖。こういう子はたいてい字や絵も下手で、裁縫や折り紙も苦手だという。私の子は運動ができず、それで悩んで読んでみたが、絵や字や工作は得意だから違ったかな。 体育のせいで学校行きたくない気持ち分かる。学校って、努力でどうにもならないことで晒し者になる場所。2025/05/17
於千代
3
極端な不器用さを特徴とする発達障害「発達性協調運動症(DCD)」を取り上げた一冊。 本文中でも「知られざる発達障害」と紹介されるとおり、発達障害について学んでいたつもりの自分でも、恥ずかしながら本書で初めて存在を知った。 本書では当事者や家族へのインタビューを通じ、日常生活の困難が丁寧に描かれる。 問題は学校の体育や美術の授業での困難に留まらず、大人になっても解剖実習や自動車運転で困難が続くことが語られる。 運動が苦手な人を笑いものにするメディアの企画も、この特性を知ると罪深く思えてくる。2025/04/30
Humbaba
3
他者と比べるというのは必ずしも正しいことではない。他の人ができたからと言ってそれが自分にもできるとは限らない。同じように努力をしてもそれが報われる人もいれば、残念ながら報われないという人もいる。親としてはつい他の子どもと比較をしてなぜできないのかを悩んだり、同じようになれるようにやらせたくなることもあるだろう。しかし、それが必ずしも幸せにつながるわけではないし、そもそもできないことはある。2025/04/24
金平糖
3
B。2025/01/27





![モーニング 2016年7号 [2016年1月14日発売]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0299986.jpg)