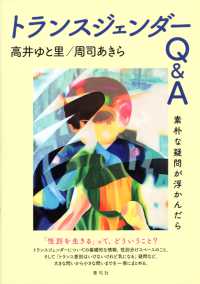内容説明
「多様な教育機会確保法案」をきっかけに誕生した「多様な教育機会を考える会」(rethinking education研究会)。教育学、社会学、社会政策・社会保障論などの学際的な研究者と、フリースクールや子どもの貧困対策に尽力する実践者・運動家が結集。現場と理論の架け橋を模索した考察の軌跡。
目次
第1部 教育機会を問う、その問い方を問う(多様な教育機会とその平等について考える―ケイパビリティ・アプローチを手がかりに;“教育的”の公的認定と機会均等のパラドックス―佐々木輝雄の「教育の機会均等」論から「多様な教育機会」を考える;「バスの乗り方」をめぐる一試論―教育社会学の「禁欲」について;不登校や多様な教育機会に関する社会学的研究は議論を開き継続させていけるのか)
第2部 不登校への応答・支援を問う(多様な子どもの「支援」を考える―登校/不登校をめぐる意味論の変容を手がかりに;フリースクールにおける「学習」の位置と価値―行政や学校との連携事例に着目して;不登校児への応答責任は誰にあるのか―1970年代以降の夜間中学における学齢不登校児の受け入れをめぐる論争に着目して)
第3部 教育と福祉の交叉を問う(教育と福祉の踊り場―「居場所」活動の可能性についての考察;教育制度と公的扶助制度の重なり―就学援助と生活保護を対象として;子ども支援行政の不振と再生―トラスト設置手法を導入したイングランドのドンカスター)
第4部 学校・教師を問う(教員はどのように居場所カフェを批判したのか;教員の「指導の文化」と「責任主体としての生徒」観;後期近代における社会的に公正な教育の実践的理論―批判的教育学からの示唆)
著者等紹介
森直人[モリナオト]
筑波大学人文社会系准教授。専門は教育社会学、社会階層論、歴史社会学。東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻博士課程単位取得退学。多様な教育機会を考える会事務局
澤田稔[サワダミノル]
上智大学総合人間科学部教授、同教職・学芸員課程センター長。専門は教育学、カリキュラム・教育方法論。名古屋大学大学院国際開発研究科博士課程単位取得満期退学。多様な教育機会を考える会事務局
金子良事[カネコリョウジ]
阪南大学経済学部准教授。専門は社会政策、労働史。東京大学大学院経済学研究科企業・市場コース博士課程修了。博士(経済学)。多様な教育機会を考える会事務局、職務分析の可能性を検討する委員会(日本職務分析・評価研究センター)委員長、松原市バリアフリー基本構想策定等協議会会長の他、障害者の更なる雇用促進と職場定着に向けた課題と労働組合の役割に関する調査研究委員会(連合総研)等を歴任、大阪では学習支援や居場所活動にも携わった(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いとう
ぺろりん
無題