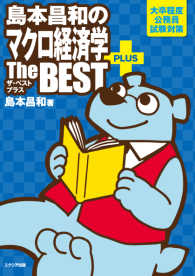目次
1 中世~近世のチェコ(国土と名称―なかなか複雑な歴史的由来;中世ヨーロッパとチェコ―モラヴィア国家からプシェミスル朝時代まで ほか)
2 チェコ近代社会の形成(民族再生―現代チェコ文化の創造と「チェコ史の意味」;19世紀の社会と政治―「近代化」のなかを生きた人々 ほか)
3 チェコスロヴァキア共和国(第一共和国の政治―1920年憲法と議会政治;第一共和国時代の外交―ヴェルサイユ体制とベネシュ ほか)
4 体制転換以降(体制転換と連邦解体―社会主義の連邦共和国からチェコ共和国へ;チェコ共和国としての歩み―連邦解体後の政治的展開 ほか)
5 文化・芸術(チェコ語はどのような言語か―系統・屈折・情報構造;チェコ語文学の始まり―スラヴ語、ラテン語、ドイツ語に囲まれて ほか)
著者等紹介
薩摩秀登[サツマヒデト]
明治大学経営学部教授。1959年生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了。専門は東欧・中欧の中世史および近世史
阿部賢一[アベケンイチ]
東京大学大学院人文社会系研究科准教授。1972年生まれ。東京外国語大学外国語学部卒。カレル大学、パリ第4大学留学を経て、東京外国語大学大学院博士後期課程修了。博士(文学)。専門は中東欧文学、比較文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Nat
30
図書館本。プラハに旅行に行く前に読もうと思って借りたが事前には読めず、復習として読了。ウィーンから電車でプラハに向かった時に通過したブルノという街は、プラハに次ぐ第二の都市で、モラヴィアの中心都市だった。やっぱり旅行前に訪れる国や都市の歴史や文化を予習しておかなきゃと思いつつ、いつも後手後手になってしまう。次回はもっと予習しなきゃなと反省。今回は特にプラハについてもっと予習すべきだったな。2024/08/24
秋良
17
国の成り立ちの関係で歴史に関する記述が多い。学生時代にぴんと来なかったボヘミア・モラヴィアあたりの概観をやっと理解できた。多民族国家に暮らす人々の精神的背景や意識の違いは、日本人には心底から理解することが難しい気がする。チェコ語はスラヴ語系なので馴染みが薄く、名前や地名が覚えにくいのが辛い。〜ヴァーとか〜ニェイヌリチ的な口がもにゃもにゃするやつが多い。カフカ、ミュシャ、チャペックなど日本でも有名な文化人が多く、深掘りするための参考文献が多いのが嬉しいところ。ちなみにご飯はそれほど美味しそうではない。2024/09/28
Fumitaka
3
2025年10月初頭時点の日本の首相も参考にしているという概説書シリーズのチェコ史を扱ったもの。いくつかの話題はかなり深いところに突っ込んでいる。『「民族自決」という幻影』でカルパチア・ルーシを扱った篠原琢先生も寄稿しており、自分が気に入って読み返した箇所は篠原先生の担当部分が多かった。チェコがスロヴァキア人やドイツ人、そしてユダヤ人やルシーン人の混住してきた地域である点が繰り返され、チェコの民族主義者も共産党も依拠した、ドイツ人に対する「スラヴ諸国民の闘争」(スターリン)という図式の脱構築が試みられる。2025/10/13
takao
2
ふむ2024/05/05
みわ
0
チェコという国を知るための基礎知識をあっさり網羅できます。現代の話題も知れるのが嬉しい。 また読みます。 2025/06/07
-

- 電子書籍
- 時事英語 DE リーディング&リスニン…