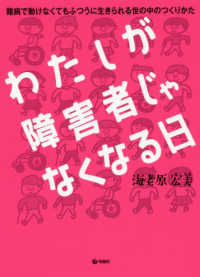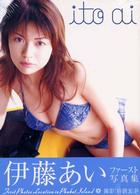内容説明
トン族は天籟の響きを奏でる美しいハーモニーで知られる。「歌の海」といわれるほど歌声が生活のなかに溢れている。歌好きの民族はどこにでもいるが、トン族は高音部と低音部が積み重なるように立体的にうたわれるポリフォニーに優れている。この多声部合唱が聞こえるのは、男女が集団となって歌をかけあうさまざまな行事のなかである。たくさんある行事のなかでも、歌声は春節のときおこなわれるワヒェという社交の場において、もっともにぎやかに交わされる。ワヒェはある村が別の村の住民をみんな招待してもてなす大饗宴である。いくら友好的とはいえ、数百人もの人を数日間、寝食ともに接待し、歌舞を楽しむというのは、尋常ではない。多声性と歌のかけあいをたんなる音楽的特徴として評価するのではなく、トン族の人びとの生活意識や社会の基盤となる機構との相関にまで思考を拡げられないだろうか。饗宴もたんなる娯楽ではなく、人と人を結いあげる「もやい(舫い)」の綱となっているのではないだろうか。トン族の歌と饗宴には、柳田國男が日本の民俗社会のなかに見いだし尊んだような共同体の精神があり、「世の常を組み立てる」「生存の力」があるのではないか。その普遍性を明らかにすること。本書の出発点がここにある。
目次
第1章 トン族社会の組織と構造
第2章 岩洞村の概況
第3章 トン族歌謡とその生態
第4章 歌謡の伝承体系
第5章 ワヒェ
資料
著者等紹介
牛承彪[ニウチェンビャオ]
関西外国語大学教授。中国吉林大学で日本語・日本文学を学ぶ。1998年に日本へ留学。博士前期課程は奈良教育大学で真鍋昌弘先生に師事して日本古典文学を学び、博士後期課程は名古屋大学で櫻井龍彦先生に師事して文化人類学を学ぶ。日本の民俗文化、特に稲作にかかわる文化に関心をもち、日本・中国・韓国における農耕歌謡を総合的に比較する視点から調査・研究してきた。2007年に関西外国語大学に着任。中国語と日本学研究の科目を担当。2011年から科研費(計9年間)の支援を受けて歌謡文化の伝承がまだ存続している中国貴州省のトン族地域で実地調査を行った
櫻井龍彦[サクライタツヒコ]
名古屋大学名誉教授。名古屋大学文学部で中国古典文学を学ぶ。博士課程のとき北京師範大学に留学し、鍾敬文先生(1903~2002)に師事。民間文芸・民俗学をまなび、研究の関心と方向が西南少数民族の民俗学・文化人類学の分野に移っていった。帰国後は華北、黄河流域の廟会や民間祭祀・芸能組織(香会)に関する調査もかさねた。貴州省のトン族・ミャオ族地区には1982年にはじめて入る。本格的にトン族の歌謡と生活文化の現地調査をはじめたのは、牛承彪氏が科研費を得た2011年の共同研究からになる。龍谷大学、中京大学でも教鞭をとり、名古屋大学大学院国際開発研究科および同人文学研究科教授を歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。