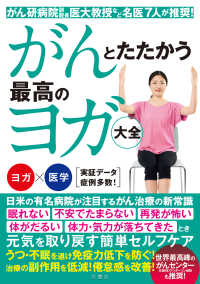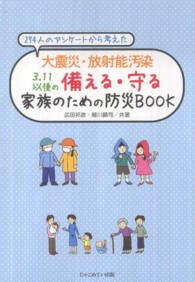目次
1 アフガニスタンの国の輪郭
2 国の歩み
3 生活の基盤
4 多声的な文化
5 文明の十字路
6 アフガニスタンの旅
7 日本とアフガニスタン
8 戦後復興
9 アフガニスタンはどこへ向かうのか
補論 アフガニスタン情勢の変化
著者等紹介
前田耕作[マエダコウサク]
アフガニスタン文化研究所所長。1957年名古屋大学文学部卒業。1975年より和光大学教授(アジア文化史・思想史)。2003年和光大学退職、名誉教授。東京藝術大学・帝京大学客員教授。1964年名古屋大学アフガニスタン学術調査団一員として初めてバーミヤンを訪れ、以来アフガニスタンほか、西アジア、中央アジア、南アジアの古代遺跡の実地調査を行う。現在は主にアフガニスタンに関する文化研究を進めると共に、2003年7月から開始されたユネスコ日本信託基金に基づくバーミヤン遺跡の保存・修復の事業に参加している
山内和也[ヤマウチカズヤ]
帝京大学文化財研究所教授。1984年早稲田大学第一文学部(東洋史専攻)卒業。1988年早稲田大学大学院文学研究科修了。1992年テヘラーン大学人文学部大学院修了。シルクロード研究所研究員、独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所文化遺産国際協力センター地域環境研究室室長を経て現職。専門はイラン、中央アジアの考古学。現在、アフガニスタンのバーミヤン遺跡の調査研究、保存修復事業に従事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
榊原 香織
鯖
にゅ
takao
Ahmad Hideaki Todoroki
-
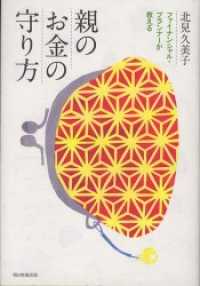
- 電子書籍
- ファイナンシャル・プランナーが教える …
-
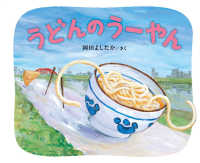
- 和書
- うどんのうーやん