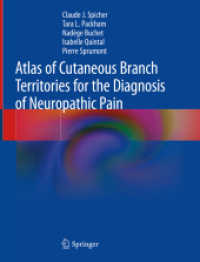内容説明
2020年春以降、生活困難な層が急速に拡大し、貧困の現場でも緊急事態が到来した。「誰も路頭に迷わせない」と立ち上がった著者たちの支援活動記録と政策への提言。
目次
はじめに 2019年~2020年、冬
第1章 2020年春
第2章 2020年夏
インタビュー 居住支援の活動から
第3章 2020年秋
第4章 2020~21年冬
第5章 2021年春
あとがき アフターコロナの「せめぎ合い」のために
著者等紹介
稲葉剛[イナバツヨシ]
1969年、広島県広島市生まれ。1994年から路上生活者を中心とする生活困窮者への支援活動に取り組む。一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事、認定NPO法人ビッグイシュー基金共同代表、住まいの貧困に取り組むネットワーク世話人、生活保護問題対策全国会議幹事、いのちのとりで裁判全国アクション共同代表、立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科客員教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ミライ
27
2020年春~2021年春までの1年間のコロナ禍の日本の貧困事情が描かれたノンフィクション。路上生活者がいなくなりネットカフェで暮らすようになり、緊急事態宣言でネットカフェに休業要請がだされたことで、行き場がなくなったりといろいろ知らなかった日本の貧困の実態が理解できた。生活保護の利用を拒否する最大の要因である扶養照会(身内への問い合わせ)の問題は奥深いなと思ったし、貧困対策としてここの改善が急務だと思った。2022/07/30
Sakie
18
2020~2021年の、各支援団体の状況がわかる。新型コロナでもともと不安定だった雇用が奪われ、困窮の末住まいも失った人が急増した。そして福祉崩壊、相談崩壊。支援団体の人々は支援をしながら行政に申入れし、抗議し、地道に変えていく。一方で政治家によるネガキャンは大々的に報道され、確実に人々の心を侵食していく。国の組織としてのしなやかさの欠如が、日本をますます生きづらい場所にする。行政の支援を受けるのに、やりとりを録音しておくべきだなんて常態は酷すぎる。「自助も共助も限界に来ている。今こそ、公助の出番だ」。2022/09/03
Mc6ρ助
16
「自助、共助、公助」なんて理解の外の爺さまは憤懣やるかたない。2019年の勤労者世帯の実収入、一ヶ月あたり512,534円に対して税・社会保険料95,554円と18.6%になるそうだが、役にも立たないマスクの保管料やら飛んでくるミサイルも落とせない戦闘機に使い~の、お友達に中抜きさせたんで後は宜しくと言われているようで納得しがたい。共助に奮闘する人々には頭が下がるが、我々は、寝ている「公助」を叩き起こすことができるのだろうか?2021/12/05
羊山羊
10
著者は困窮者の住居問題を中心に取り組む人。本著中では救われた人が中心に取り扱われているが、その一方で本の端々に数字となって表れるネカフェ難民→ホームレス化4000万人、その中でたった一人、一件の家の確保の為に投げ出さずに奔走する著者や仲間の賢明さと、その裏でまだ広がる圧倒的な量の貧困を叩きつけられる1冊。ホームレスの"home"の為に走る、そんな人のコロナ記。2021/11/18
どら猫さとっち
9
コロナ禍は、貧困を引き起こす。仕事をなくし、明日の生活に不安を感じて過ごす。貧困層が広がる一方で、管政権の「自助・共助・公助」を掲げている。その公助を引き出すために、活動し続ける著者が日記として綴ったコロナ禍の日々。自助では充分に生活できず、共助でも限界がある。それなのに、政府は何も動くことがない。著者は怒りも悲しみも綴り、それでも活動していく。その姿勢を、政治家たちに見せてあげたい。2021/11/30
-
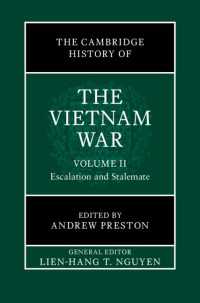
- 洋書電子書籍
- ケンブリッジ版 ベトナム戦争史(全3巻…
-

- 洋書電子書籍
- Nineteenth-Century …