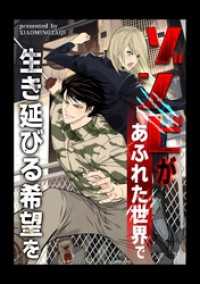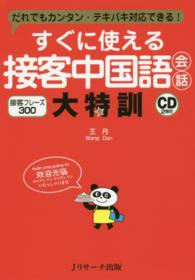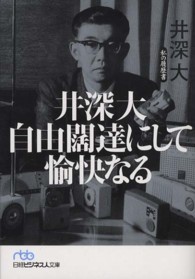目次
第1部 QOLに基づく交通と都市の新たなプロジェクト評価法―公共事業評価からSDGs、GNHまで(なぜQOLなのか?;最終帰着効果で測るQOLアクセシビリティ法;QOL評価における価値観の比較分析 ほか)
第2部 国際シンポジウム:交通と都市の計画評価におけるQOLの主流化―Wider Economic ImpactからGNH、SDGsへ(欧州と日本におけるプロジェクト評価の歴史的変遷と代替アプローチ(拡張効果から変革新果へ:大規模プロジェクトにおいて展開されるイギリスのアジェンダ;広範な経済効果(WEI):ドイツにおけるプランニングの実践
フランスにおける費用便益分析と都市交通への投資:アクセシビリティ転換を目指して ほか)
QOLアクセシビリティアプローチ(QOLアクセシビリティ法とそのケーススタディ:シンガポール、南京、高蔵寺ニュータウン、インド高速鉄道、バンコク、COVID‐19パンデミック;SDGs達成に向けた運輸部門の貢献度評価のためのQOLアクセシビリティ法の拡張;日本におけるQOL評価の実践:高速道路とストリートデザインへの適用 ほか)
ポストコロナ社会におけるプロジェクト評価)
著者等紹介
林良嗣[ハヤシヨシツグ]
中部大学卓越教授、持続発展・スマートシティ国際研究センター長、名古屋大学名誉教授。ローマクラブの執行委員・日本支部長、世界交通学会(WCTRS)の会長(2013~2016年)、COVID‐19Taskforce議長などを歴任。東京湾アクアライン、つくばエクスプレス、中央リニア、バンコク都市鉄道導入、インド新幹線などの効果分析に携わる。集計経済便益による事業評価に代わる、個人の幸福度を計測し、コンパクト・プラス・ネットワーク、都市縮退、SDGsの包摂性の評価にも使えるQOLアクセシビリティ評価法を発案し、多方面に応用
森田紘圭[モリタヒロヨシ]
大日本コンサルタント株式会社インフラ技術研究所主任研究員。博士(環境学)。名古屋大学大学院環境学研究科修了後、同社入社。道路計画および設計、エネルギー事業の調査・計画に関する業務を経て、現職。現在は、中心市街地における都市・地域再生や気候変動やSDGsなどに対応する持続可能なまちづくり、スマートシティなど様々な事業の企画設計に関わる。その他、名古屋の錦二丁目エリアマネジメント株式会社取締役等を務める
竹下博之[タケシタヒロユキ]
中部大学持続発展・スマートシティ国際研究センター特定講師。2010年に名古屋大学大学院環境学研究科にて博士(工学)取得後、一般財団法人運輸政策研究機構にて、高速鉄道をはじめとする本邦の鉄道インフラ海外展開や、ASEAN諸国の低炭素交通のロードマップ作成といった研究プロジェクトに従事した後、民間企業にて交通事業の動向調査や海外展開、グループ全体の法務担当を含む経験を積む。現在はQOLと脱炭素社会を同時に実現するための都市や交通のあり方に関する研究に取り組んでいる
加知範康[カチノリヤス]
東洋大学情報連携学部情報連携学科准教授(博士(環境学))。名古屋大学大学院環境学研究科都市環境学専攻博士課程修了後、公益財団法人豊田都市交通研究所、九州大学大学院工学研究院附属アジア防災研究センターを経て、現職。人口減少・少子高齢化や気候変動に伴い、自然災害に対する都市・国土の脆弱性が増大する中で、情報技術を活用し、その実態を把握するとともに、安心して快適に暮らせる都市・国土のあり方を研究している
加藤博和[カトウヒロカズ]
名古屋大学大学院環境学研究科附属持続的共発展教育研究センター教授、滋賀大学データサイエンス学部特別招聘教授。土木計画学分野の研究者として運輸・交通サービスの低炭素性評価手法の開発を四半世紀続け、2017年に日本LCA学会功績賞を受賞。さらに「人にも地球にもやさしく災害にも強い都市空間構造」究明と実現手法確立に携わる。地域公共交通の再生も全国各地の現場で支援。以上の経験を活かし「臨床環境学」創成に取り組む。国土交通省交通政策審議会委員として交通・環境関連の制度や計画の見直しにも深く関わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Go Extreme