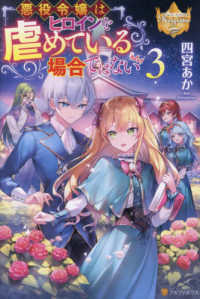- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
内容説明
「寄り添う」の本当の意味は何なのか―根こそぎ失われた被災地の風景のなかを、著者はジャーナリズムが果たす役割の意味を問いながら、取材者として歩き続けてきた。忘却に抗い、声をつなぎ続けた10年の記録。
目次
第1章 被災地の風景の中で―他者の壁を越えてつながる
第2章 被災地10年の変容を追って 2013.8.‐2020.3.(アベノミクスの狂乱の影で、置き去りにされる東北の被災地;どう乗り越えるか、風化と風評 マスコミ倫理懇談会全国大会で見えてきた課題;現実の遠い彼方にある幻夢 東北の被災地からみた“復興五輪” ほか)
第3章 震災取材者の視点から 2012.7.‐2020.9.(ブログは新聞の発信力を強める―風評、風化の「見えない壁」の向こうにつながりを求め;被災地で取材者はどう変わったか?当事者との間の「壁」を越えるには;「自殺」から「自死」へ 当事者取材の現場で知る言葉の違いの意味 ほか)
第4章 ルポルタージュ 被災地のいま 2020.1‐11.(原発事故10年目の「福島県飯舘村」―篤農家が苦闘する「土の復興」はいま;丸9年の「3・11」―変貌する古里「飯舘村長泥」のいま;「新型コロナ禍」で閉ざされた「交流」―福島被災地の「模索」と「きざし」 ほか)
終章に代えて 被災地をめぐる若者との対話―早稲田大政経学部「メディアの世界」受講生への返信
著者等紹介
寺島英弥[テラシマヒデヤ]
ローカルジャーナリスト、尚絅学院大客員教授。1957年、福島県相馬市生れ。早稲田大学法学部卒。河北新報社編集委員、論説委員を経て2019年から現職。02~03年にフルブライト留学で渡米。東北の暮らし、農漁業、歴史などの連載企画を長く担当し、「こころの伏流水北の祈り」(新聞協会賞)、「オリザの環」(同)などに携わる。11年3月以来、東日本大震災、福島第一原発事故を取材。朝日新聞社『Journalism』、新潮社「Foresight」に被災地をめぐる論考、ルポを執筆中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 古文答案作成マニュアル