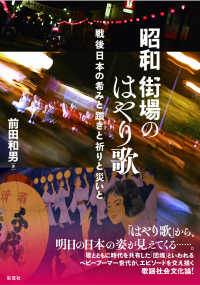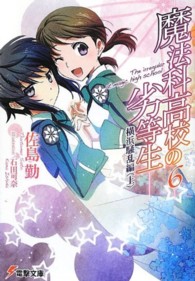目次
今、「人種」「民族」を問う意義
第1部 教育において「人種」「民族」はどう認識され、論じられてきたか(「人種」とヒトの多様性―学校でのまなびのために;「人種」「民族」とは何か;「人種」に関する認識;社会系教科の教科書記述に見る「人種」「民族」)
第2部 日本と外国で「人種」「民族」について授業でどう教えられてきたか(日本における「人種」「民族」を取り上げた授業構想;アメリカの初等・中等学校の人類学教育における「人種」言説と実践―1930年代~1960年代を中心に;外国では「人種」「民族」をどのように教えているか;「人種」と「先住民族」に関する学習)
第3部 学校で「人種」「民族」をどう教えるか(「人種」をテーマにした授業づくりのために;「人種」を問い直す授業実践;小学校における授業構想;中学校における授業構想;高等学校における授業構想)
著者等紹介
中山京子[ナカヤマキョウコ]
帝京大学。専門は社会科教育、国際理解教育
東優也[アズマユウヤ]
海老名市立東柏ヶ谷小学校。専門は国際理解教育、英語教育
太田満[オオタミツル]
奈良教育大学。専門は、社会科教育、国際理解教育
森茂岳雄[モリモタケオ]
中央大学。専門は多文化教育、国際理解教育、社会科教育(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
崩紫サロメ
21
本書のスタンスはアメリカやオーストラリアの教育現場同様、人種を(1)近年人間によって創られたものである(2)人種の考えは文化に関するもので生物学ではない(3)人種と人種主義は教育組織や日常生活において埋め込まれている、と捉え、小学校から高校までのそれぞれの発達段階においてどのように教えるかを検討したものである。第三部では各段階での実践案が提示されている。高校くらいになると人種概念を問い直すということができるが、小学校低学年など「概念」が定着するまでにどのように教えるか、など考えさせられる。2021/04/30
入江・ろばーと
0
〝「和人」「日本人」と自らを名乗る集団が、「土人」「アイヌ」と侮蔑を伴う感覚とともに「日本人」感覚を形成してきた。学校教育においては、「和人」「日本人」「土人」「アイヌ」があたかも始めから存在していたのではなく、ヒト集団を括るべく創られた概念であり、その創られた概念によって差別が存在していたことを教えるべきであろう。〟(p.155)とあった。なんでこう、デカく括るんだろう……2024/07/21
-
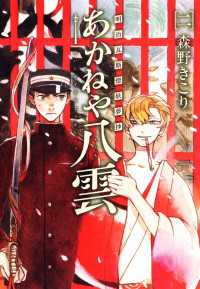
- 電子書籍
- 明治瓦斯燈妖夢抄 あかねや八雲(2) …