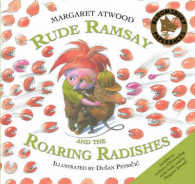内容説明
悪意の有無に関係なく存在する偏見、バイアス。それがいかにして脳に刻まれ、他者に伝染し、ステレオタイプを形作っているかを知ることなしに、人種差別を乗り越えることなどできない。米国の学校・企業・警察署の改革に努める心理学者が解く、無意識の現実とは。
目次
1 私たちの目に映るもの(互いの見え方―認知とバイアス;何が育むのか―カテゴリー化とバイアス)
2 自らをどう見出すか(悪人とは?―警察とバイアス1;黒人男性―警察とバイアス2;自由な人の考え方―刑事司法とバイアス;恐ろしい怪物―科学とバイアス)
3 抜け出すための道はあるか(ホームの快適さ―コミュニティとバイアス;厳しい教訓―教育とバイアス;シャーロッツビルの出来事―大学とバイアス;最後に得るもの、失うもの―ビジネスとバイアス)
著者等紹介
エバーハート,ジェニファー[エバーハート,ジェニファー] [Eberhardt,Jennifer]
スタンフォード大学心理学部教授。全米科学アカデミー、米国芸術科学アカデミーに選出され、フォーリン・ポリシーの「世界をリードする100人の思想家」の一人に選出。人種問題の研究における世界の第一人者の一人として知られる
山岡希美[ヤマオカキミ]
翻訳家。16歳まで米国カリフォルニア州で生活。同志社大学心理学部卒(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 洋書電子書籍
- Lateral Flow Assays…