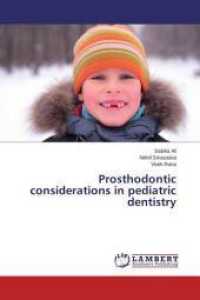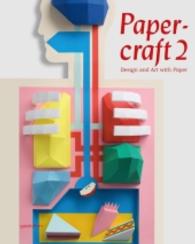出版社内容情報
日米のNPO活動実践・教育研究および、女性の権利擁護運動に関わってきた二人の著者が、これまでのNPOを通じた女性の活動を振り返るとともに、今後、女性がNPOをどのように活用し新たな働き方を探っていくべきかについて、展望する。
はじめに
第1章 地域での保育所づくりから国際的活動、そしてNPOとの出会い[金谷千慧子]
第1節 ジェンダー平等をめざして
(1)女性が輝くとは、自ら「光源」となること
(2)フェミニズムは意識変革を求める
(3)女性が働くことと労働組合運動
(4)生活者としての女性と住民運動
コラム1 「なければつくる」をスローガンに保育所を開設
第2節 1980年代、「女性差別撤廃条約」に結集して
(1)「国連女性の10年」と女性運動の広がり
コラム2 「働くことを譲り渡してはいけない」(女性差別撤廃条約)
(2)ナイロビ将来戦略と女性運動の変化
コラム3 ナイロビ大会でみた、「焼かれる花嫁」(インド)の衝撃
コラム4 「主婦の再就職センター」の立ち上げ
(3)差別撤廃条約批准に必要だった「男女雇用機会均等法」
コラム5 欧米や豪州への女性の再就職視察
(4)男女雇用機会均等法
コラム6 女性学と女性学教育ネットワーク
第3節 1990年代、男女共同参画への道
(1)「女性の権利は人権!」を継承した第4回世界女性会議
コラム7 ワークショップ「M字型を超えて」
(2)NGOの役割が拡大した北京会議
(3)女性センターの設立
(4)男女共同参画社会基本法
第4節 住民運動からNPOへ
(1)NPOの発見と参加の拡大
(2)NPOの揺籃期をつくった女性センター
コラム8 NPO学習会で「ネットワーキング」を知る
コラム9 カタリスト(Catalyst)をモデルにしよう!
コラム10 女性と仕事研究所・国際交流基金主催「国際パートシンポジウム」
(3)女性と市民活動
(4)NPOと女性のリーダー
第2章 バックラッシュに抗しつつ、期待したいN女の今後[金谷千慧子]
第1節 バックラッシュの波
(1)バックラッシュの経緯と時代背景
(2)「基本法」そのものの問題
(3)現代の「魔女狩り」
コラム11 「みなとNPOハウス」が消えた
コラム12 ある日突然、「女性のための」はだめだ、と
コラム13 企業の評価基準をつくる
第2節 経済のグローバル化と女性労働の変貌
(1)男女共同参画法下での女性の貧困
(2)子づれシングルの貧困
(3)ひとり親世帯の貧困率の国際比較
第3節 男女格差の国際比較
(1)ジェンダー・ギャップ指数、111位(2017年度は114位)
(2)研究者・大学教員の女性比率の低さ
(3)やり直しのための職業教育
コラム14 NPOの継承問題
コラム15 キャリアアドバイザーとコミュニティカレッジの夢
第4節 アベノミクスで女性は輝くのか
(1)「女性の活躍」はアベノミクス(Abenomics)の中核
(2)アベノミクスの背景になった2つのレポート
(3)日本型雇用慣行では女性活躍は進まない
第5節 NPOで働く女性
(1)2016年、「N女」の登場
(2)「N女」がNPOを選ぶ背景
(3)「N女」の今後
第3章 ジェンダー平等をめざす日本のNPOの実像[金谷千慧子・柏木宏]
第1節 NPOの経営とジェンダー
(1)経営課題の中心、「資金」と「人材」
(2)「女性代表NPO」の経営課題
(3)財政規模が大きい「女性代表NPO」
(4)大規模NPOの運営能力をもつ女性
第2節 女性NPOの機能と類型
(1)「自分のことはさておき」という姿勢の実態
(2)フロントランナーから経営強化へ
(3)NPOのもつ特異な能力
第3節 ジェンダー平等をめざして活躍する女性NPO
(1)女性関連のサービス提供型NPOの事例
事例1 NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西
事務局長の声 山口絹子
事例2 NPO法人日本フェミニストカウンセリング学会
事例3 ウィメンズカウンセリング京都
代表者の声 井上摩耶子
事例4 特定非営利金融法人「女性・市民コミュニティバンク」
代表者の声 向田映子
(2)指定管理者制度でサービスを提供するNPOの事例
事例5 NPO法人男女共同参画フォーラムしずおか
事例6 NPO法人姫路コンベンションサポート
代表者の声 玉田恵美
(3)女性に関連するアドボカシー型NPOの事例
事例7 ワーキング・ウィメンズ・ネットワーク(WWN)
代表者の声 越堂静子
(4)女性関連NPOを資金支援するNPOの事例
事例8 NPO法人グループみこし「藤枝澪子基金」
事例9 公益財団法人パブリックリソース財団「あい基金」
事務局長の声 岸本幸子
第4章 アメリカの女性の権利擁護運動の歴史とNPO[柏木宏]
第1節 18世紀から20世紀初頭までの女性の運動
(1)女性による女性のための教育の促進
(2)移民支援の隣保館と労働運動における女性の役割
(3)社会を変えた女性篤志家
第2節 男女同権運動にみるNPOの多様性
(1)婦人参政権からERAへ
(2)ERAに反対した女性の運動
第3節 女性・少女向けの伝統的なNPO
(1)YWCAの成立と発展
(2)少女を対象にしたNPO
第5章 トランプ政権下のNPOと女性[柏木宏]
第1節 反トランプを掲げた女性大行進
(1)ひとりの女性のフェイスブックでの呼びかけから
(2)数々の課題を乗り越え実現した行進
(3)きめ細かい配慮とNPOの専門性の活用
(4)多様な課題に取り組む団体を糾合した運動
第2節 トランプのNPOに関する政策
(1)トランプ財団を通じたNPOへの支援の実態
(2)「熱烈なフィランソロピスト」への疑念
(3)新政権によるNPO関連予算削減
(4)ジョンソン修正廃止案に異論続出
第3節 トランプ政権の女性政策
(1)選挙公約に盛り込まれた働く女性への支援策
(2)伝統的な家族観を重視するオルトライトの影響
(3)閣僚人事における女性の少なさ
(4)女性に関する行政執行措置の問題点
第4節 トランプに対する女性とNPOの姿勢
(1)クリントンを支えた女性の政治献金
(2)NPO関係者や女性団体の財政支援
(3)閣僚候補の承認問題への女性団体やNPOの対応
(4)ニール・ゴーサッチの最高裁判事指名反対の活動
(5)トランプ政権とNPO、女性の今後
第6章 アメリカの女性の現状とNPOにおけるジェンダー問題[柏木宏]
第1節 政治面における女性の進出
(1)参政権獲得後も少ない女性連邦議員
(2)半数を超える州で誕生した女性知事
第2節 経済面におけるグラスシーリングと女性の貧困
(1)男性に比べ高いパートの割合と低い給与水準
(2)大差ない男女間の学歴
(3)グラスシーリングと女性の貧困
第3節 NPOにおける女性のボランティアと理事
(1)ボランティア活動における男女差
(2)NPOの理事や企業の取締役の男女差の問題性
(3)NPOにおける女性理事の現状
第4節 NPOの有給職員におけるジェンダー問題
(1)NPOの有給職員数や給与水準
(2)NPOのトップにおける男女の給与差
(3)格差是正に求められる理事の役割
第7章 社会変革に向けてNPOに求められる政策力と経営力[柏木宏]
第1節 NPOに必要な力、政策力と経営力
(1)政策力と経営基盤からみた4分類
第2節 日米のNPOの政策力に関連する活動
(1)日米のNPOの政策関連活動の比較
(2)法律をテコに社会変革をめざすリーガル・アドボカシー
(3)調査研究を通じて公共政策に影響を与える活動
(4)選挙への取組みの重要性
第3節 NPOの経営力の強化に向けた活動
(1)人材育成を進める経営指導組織
(2)女性によるNPOへの資金確保の取組み
おわりに
参考資料
索引
金谷 千慧子[カナタニ チエコ]
著・文・その他
柏木 宏[カシワギ ヒロシ]
著・文・その他
目次
第1章 地域での保育所づくりから国際的活動、そしてNPOとの出会い
第2章 バックラッシュに抗しつつ、期待したいN女の今後
第3章 ジェンダー平等をめざす日本のNPOの実像
第4章 アメリカの女性の権利擁護運動の歴史とNPO
第5章 トランプ政権下のNPOと女性
第6章 アメリカの女性の現状とNPOにおけるジェンダー問題
第7章 社会変革に向けてNPOに求められる政策力と経営力
著者等紹介
金谷千慧子[カナタニチエコ]
NPO法人女性と仕事研究所前代表理事。大阪市立大学法学部卒、同大学院法学部・経済学部前期博士課程修了。1980年金谷研究室の設置(研究会と調査活動の実施)、1986年主婦の再就職センター設立。再就職講座・相談事業開始。1993年女性と仕事研究所設立、2000年女性と仕事研究所NPO法人化、代表理事。関わった審議会などの委員に、京都府女性政策推進専門家会議(委員)、三重県生活部女性活躍推進委員会委員(会長)、大阪府大東市男女協働社会懇話会(会長)、兵庫県少子化対策総合推進計画策定委員会(委員)、大阪府吹田市女性政策推進懇談会(会長)など、多数。東大阪市立男女共同参画センターディレクター、中央大学研究開発機構教授を歴任。関西大学、同志社大学、中央大学などの非常勤講師。2014年女性と仕事研究所代表を退職。著書・共著書多数
柏木宏[カシワギヒロシ]
大阪市立大学大学院教授・法政大学大学院教授。同志社大学卒業後、渡米。移民、労働、福祉などのNPOの理事やスタッフに従事。1982年、カリフォルニアで日米の市民活動の交流やNPOの人材育成を進めるNPO、日本太平洋資料ネットワーク(JPRN)設立。2003年まで、理事長兼事務局長。2003年に大阪市立大学大学院、2017年に法政大学大学院に赴任。大阪ボランティア協会評議員、関西NGO協議会代表理事。編著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。