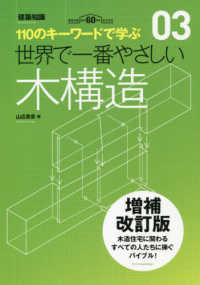出版社内容情報
肥満の増加が社会問題となっているアメリカ。「肥満=悪」という反肥満イデオロギーが叫ばれるが、一体「太っている」とは誰のことを指し、それが意味するものは何なのか。気鋭の文化人類学者が肥満をめぐる問題から人間の多様なあり方を考える意欲的な著作。
はじめに――なぜ肥満/ファットに注目するのか?
序章 現代アメリカの「ファット/肥満」の民族誌に向けて
はじめに
?.先行研究
1.人類学の対象としての肥満/ファット
2.フェミニズムのなかの太った女性
3.逸脱の医療化、社会問題論
?.本書の視座
1.「肥満エピデミック」
2.「リスク社会」――「未来の操作可能性」と「未来の非決定性」の矛盾
3.「リスク社会」の新たな主体――「生物学的市民権」
4.新しい「人びとの種類(human kinds)」
5.ファット・アクセプタンス運動を理解するための本書の視座――「リスク社会」のアイデンティティ・ポリティクス?
?.フィールドワーク
1.本書の舞台――アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ・ベイエリア
2.フィールドワーク概要
3.本書の構成
4.用語の問題
第1部 肥満・リスク・制度
第1部導入
第1章 集合のリアリティ・個のリアリティ――アメリカの「小児肥満問題」から考えるリスクと個人
1.集合的事象としてのリスクと個人
2.錯綜する病因論と不確実性との対峙――「リスクの医学」の誕生と確率論的病因論
3.「肥満問題」とリスクの個人化
(1)「肥満エピデミック(Obesity Epidemic)」
(2)BMI小史
4.累積的リスクと「肥満になる」意思決定
(1)子どもの肥満をめぐる責任ゲーム――ジョージア州の小児肥満対策キャンペーンから
(2)責任主体と累積的リスク
(3)交錯する集合のリアリティと個人のリアリティ
第2章 空転するカテゴリー――福祉・公衆衛生政策から見る「貧困の肥満化」
1.リスクの犯人探し――「貧困の肥満化」という問題
2.貧困の肥満化
(1)貧困対策におけるアメリカ農務省による公的扶助の役割
(2)貧困の肥満化
3.公的扶助としての食料支援プログラムと肥満対策
(1)カリフォルニア州の「肥満の原因となる環境」への取り組み
(2)WICプログラムの概要
(3)栄養カウンセリングの現場を中心に
4.引き受け手のないリスク
(1)貧困層の肥満対策の複雑な構図
(2)引き受け手のないリスク
5.リスク・コンシャスなのは誰なのか――第2部に向けて
第2部 ファット・社会運動・科学
第2部導入
第3章 ファット・アクセプタンス運動の展開に見る「ファット」カテゴリーの特殊性
1.遅れをとるファット・アクセプタンス運動
2.ファット・カテゴリーを精査するために
(1)社会運動とカテゴリー
(2)マイノリティ・カテゴリーとしてのファット
3.ファット・アクセプタンス運動の歴史
(1)ファット・アクセプタンス運動の誕生――1969年
(2)第二波フェミニズムのなかの「ファット」――1970年代
(3)「障害」との連携――1980年代?1990年代
4.ファット・アクセプタンス運動のジレンマ
(1)名乗りにおける齟齬
(2)公民権法が想定する個人観とADAが想定する個人観とその両立――「集合としての差異」と「集合のなかの差異」
5.「ファット」とインターセクショナリティ
第4章 ファット・アクセプタンス運動とフェミニズムの「ぎこちない」関係――ファットである自己、女である自己、その自己規定の困難
1.女であるからファットなのだ
2.フェミニズムを乗り越えようとする人びと
(1)なぜフェミニズムは太った女性が受ける差別や抑圧に無関心なのか
(2)美的・性的な身体としてのファット――1970年代から1990年代前半におけるフェミニズムからの影響、そして、フェミニズムとの距離
3.スージー・オーバックとの同盟をめぐる出来事
(1)フェミニズムとの同盟が招いた騒動――年次大会のゲスト・スピーカーをめぐって
(2)フェミニストの「特権」
(3)小括――フェミニズムとファット・アクセプタンス運動の「ぎこちない関係」
4.ファットのなかの「多様性」――「ファット鶴プロジェクト(1000 Fat Cranes Project)」をめぐる人種差別批判
(1)「ファット鶴プロジェクト(1000 Fat Cranes Project)」
(2)「ファット鶴プロジェクト」に対する人種差別批判と文化的他者
(3)普遍主義と文化相対主義、ポジショナリティをめぐる問題
5.ファットであること、女であること、その自己規定の困難
第5章 「ファット」であることを学ぶ――情動的関係から生まれる共同性
1.なぜ集うのか?
2.共同性について考えるために
(1)結果として生成する共同性
(2)社会運動の場において生成する情動的関係性
3.「ファット」であることを学ぶ
(1)「ファット」から連想されるもの
(2)年次大会の概要
(3)転倒する「ファット」と「痩せ」の意味
(4)「ファット」として生きることを語り合う
(5)配慮の空間――身体実践から立ち現れてくる「ファット」
(6)ユーモラスな空間
(7)笑いの効果――言語使用実践から見る「ファット」
4.折り重なった矛盾の交渉、そして、笑いによる自他の跳躍
5.運動を持続させる力
第6章 ファット・アクセプタンス運動による対抗的な〈世界〉の制作
1.〈世界〉を制作するということ
(1)公民権としての「ファット」の危機
(2)不確実性を生きる
(3)〈世界〉という言葉と本章の目的
2.カテゴリーのもとに作られる〈世界〉
(1)生まれつきの「ファット」
(2)疫学理解の「誤謬」――相関関係と因果関係の混同
(3)対立するカテゴリー――「肥満」と「ファット」
3.「Health at Every Size」の組織化と事実作製
4.制作中の〈世界〉と既存の世界
(1)世界間の通じなさ
(2)「パラダイム・シフト」、あるいは、同時にある二つの世界
5.〈世界〉制作と世界間の通約(不)可能性
(1)制作中の〈世界〉とすでにある世界の関係
(2)世界間の連続性と同一性について
6.「徹底した相対主義」――「リスク社会」とファット・アクセプタンス運動の世界
(1)部分的に通約(不)可能な存在として生きること
(2)あらゆる視点から離れた世界はない
終章 多様性のために
1.本書で論じたこととファット・アクセプタンス運動のゆくえ
(1)世界の概念化
(2)ファット・アクセプタンス運動のゆくえ
2.多様性のために
(1)自然と文化の二分法的思考法から抜け出すこと
(2)「普通」を相対化する
(3)マークについて
(4)「普通」であること
3.多様性のゆくえ
おわりに
参考文献
碇 陽子[イカリ ヨウコ]
著・文・その他
目次
現代アメリカの「ファット/肥満」の民族誌に向けて
第1部 肥満・リスク・制度(集合のリアリティ・個のリアリティ―アメリカの「小児肥満問題」から考えるリスクと個人;空転するカテゴリー―福祉・公衆衛生政策から見る「貧困の肥満化」)
第2部 ファット・社会運動・科学(ファット・アクセプタンス運動の展開に見る「ファット」カテゴリーの特殊性;ファット・アクセプタンス運動とフェミニズムの「ぎこちない」関係―ファットである自己、女である自己、その自己規定の困難;「ファット」であることを学ぶ―情動的関係から生まれる共同性;ファット・アクセプタンス運動による対抗的な“世界”の制作)
多様性のために
著者等紹介
碇陽子[イカリヨウコ]
1977年福岡県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。博士(学術)。現在、明治大学政治経済学部専任講師。専門は文化人類学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
田中峰和
maqiso
M
-
- 洋書
- Dream mother
-

- 電子書籍
- 生命科学のための基礎シリーズ 化学