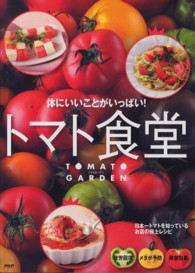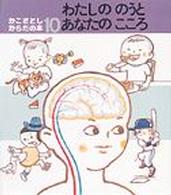出版社内容情報
中国から日本に伝わり、1000年近い歳月を経て世界的な人気料理となったラーメンの歴史を英国のアジア研究者が紐解き、明治維新以降の近代化と食、戦後の対米関係やポップカルチャーとの関連も含め縦横無尽に論ずる、新たなラーメン学の誕生。
日本語版への序
地方のブランド化――B級グルメ大国日本
日本とラーメンを輸出する
ラーメンをめぐる果てしない問い?
めん食日本地図
序 麺王国の歴史と現在――象徴としてのラーメンヘ
ラーメンをめぐる問い
ラーメンは日本料理か?
麺とナショナリズム
第1章 古代中国の食卓から――麺の誕生
中国における麺のルーツ
謎に包まれた古代の食生活
近代以前の麺――中国から日本へ
第2章 宮廷食と庶民食
神道と食物
僧が持ち帰った食品技術
武士の台頭と食生活の変化
第3章 日本の国際化、外国の食べ物、鎖国
様変わりする食習慣
長崎に花開いた文化
中国の影響による食文化の変化
江戸で人気を博した蕎麦
麺料理が全国に広まる
第4章 江戸時代の食文化とラーメン伝説
朱舜水がラーメンの作り方を教えた?
富と飢餓の混在
食べ物屋がひしめく江戸の街
江戸と肉食
第5章 明治維新――ラーメンへと通じる食の革新
開港都市
文明開化における食の役割
肉食の流行
軍隊の食事をめぐる論争
文明開化と新しい味覚
長崎ちゃんぽんと南京そば
第6章 外交と接待術
国民的料理という概念
帝国主義と食
明治期の中国人
加速する食生活の変化
第7章 帝国と日本の料理
うま味の発見
衛生状態へのこだわり
食品化学の発展
ラーメンの誕生
ラーメン誕生をめぐる複数の説
盛り場とラーメン店の急増
「栄養学」への関心の高まり
大正期の中国料理ブーム、そして戦争へ
第8章 第二次大戦中の料理――迷走する世界
飢えた日本と豊かなアメリカ
戦争への道
戦時と国民食
日本兵と食べ物
否定された食糧不足
日本人のアイデンティティと米
飢えと栄養失調
銃後の社会と食べ物
降伏と国民食の崩壊
第9章 食の歴史――戦後のインスタントラーメン
敗戦と食糧不足
余剰小麦の輸入
新しい食べ物の必要性
インスタントラーメンの誕生と人気
インスタントラーメンはなぜ開発されたか?
インスタントラーメンとラーメンブーム
フードツーリズムとラーメン
ラーメンの海外進出
ラーメンブームは続く
「日本料理」とは?
ラーメンは日本そのもの
第10章 ラーメンに関わる大衆文化
音を立てて、ズルズル!
落語家とラーメン
熱狂的ラーメンファン
ラーメンミュージアム
ラーメンテーマパーク
漫画とラーメンの歌
寿司とラーメン
ラーメン――ニューヨークの精神で
国際的な注目を浴びるラーメン
大衆文化の人気の高まりとともに
結び
食べ物のもつ負の側面
日本食のイメージはヘルシー
新たな食の革命
ラーメンの歴史が物語るもの
さぁ、歴史を食べに行こう!
訳者あとがき
参考文献
索引
バラク・クシュナー[バラク クシュナー]
著・文・その他
幾島 幸子[イクシマ サチコ]
翻訳
目次
麺王国の歴史と現在―象徴としてのラーメンへ
古代中国の食卓から―麺の誕生
宮廷食と庶民食
日本の国際化、外国の食べ物、鎖国
江戸時代の食文化とラーメン伝説
明治維新―ラーメンへと通じる食の革新
外交と接待術
帝国と日本の料理
第二次大戦中の料理―迷走する世界
食の歴史―戦後のインスタントラーメン〔ほか〕
著者等紹介
クシュナー,バラク[クシュナー,バラク] [Kushner,Barak]
プリンストン大学から博士号を取得。ノースキャロライナのデイヴィッドソン大学歴史学研究科、米国国務省東アジア課等を経て、ケンブリッジ大学アジア・中東研究科日本学科准教授。主な著書にMen to Devils,Devils to Men:Japanese War Crimes and Chinese Justice.Harvard University Press,2015.(米国歴史学会ジョン・K・フェアバンク賞受賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Miyoshi Hirotaka
ゲオルギオ・ハーン
白義
yyrn
tama
-
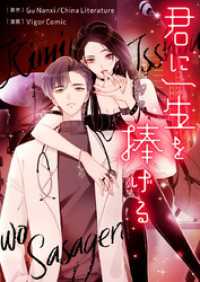
- 電子書籍
- 君に一生を捧げる【タテヨミ】第85話 …