出版社内容情報
算数や国語の学力、粘り強さ、自己制御力、思いやり……、生まれた瞬間から最初の数年間に、親や保育者が子どもとどれだけ「話したか」ですべてが決まる。日本の子育て、保育が抱える課題とその解決策を、科学的な裏づけと著者自身の具体的な実践から示した書。
第1章 つながり:小児人工内耳外科医が社会科学者になったわけ
第2章 ハートとリズリー:保護者の話し言葉をめぐる先駆者
第3章 脳の可塑性:脳科学革命の波に乗る
第4章 保護者が話す言葉、そのパワー:言葉から始めて、人生全体の見通しへ
第5章 3つのT:脳が十分に発達するための基礎を用意する
パート1:科学から実践へ
パート2:「3つのT」の実際
第6章 社会に及ぼす影響:脳の可塑性の科学は私たちをどこへ導くのか
第7章 「3000万語」を伝え、広げていく:次のステップ
エピローグ 岸に立つ傍観者であることをやめる
解説 子どもの言葉を育む環境づくり(高山静子)
訳者あとがき(掛札逸美)
ダナ・サスキンド[ダナ サスキンド]
著・文・その他
掛札 逸美[カケフダ イツミ]
翻訳
高山 静子[タカヤマ シズコ]
解説
内容説明
算数、読み書き、粘り強さ、思いやり…人生の基礎は3歳までの言葉環境でつくられる!家庭や保育園、子育て支援の場で使える「3つのT」を初めて紹介!
目次
第1章 つながり―小児人工内耳外科医が社会科学者になったわけ
第2章 ハートとリズリー―保護者の話し言葉をめぐる先駆者
第3章 脳の可塑性―脳科学革命の波に乗る
第4章 保護者が話す言葉、そのパワー―言葉から始めて、人生全体の見通しへ
第5章 3つのT―脳が十分に発達するための基礎を用意する
第6章 社会に及ぼす影響―脳の可塑性の科学は私たちをどこへ導くのか
第7章 「3000万語」を伝え、広げていく―次のステップ
著者等紹介
サスキンド,ダナ[サスキンド,ダナ] [Suskind,Dana]
シカゴ大学医科大学院・小児外科教授。同大学小児人工内耳移植プログラム・ディレクター。3000万語イニシアティブThirty Million Words Initiativeの創設者兼ディレクター。このイニシアティブに先立っては、自身が関わった患者が社会経済的に恵まれない環境にあったとしても、聞き、話す能力を十分に発揮できるようにと創設したProject ASPIREのディレクターでもある
掛札逸美[カケフダイツミ]
心理学博士、NPO法人保育の安全研究・教育センター代表。1964年生まれ。筑波大学卒。健診団体広報室に10年以上勤務。2003年、コロラド州立大学大学院に留学(社会心理学/健康心理学)。2008年2月、心理学博士号取得。2008年6月から2013年3月まで、産業技術総合研究所特別研究員。2013年4月、センター設立、現職
高山静子[タカヤマシズコ]
東洋大学ライフデザイン学部准教授。九州大学大学院人間環境学府博士課程修了。教育学博士。研究テーマは、保育者の専門性とその獲得過程。保育と子育て支援の現場を経験し、2008年より保育者の養成と研究に専念。2013年4月より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
小鈴
りょうみや
tellme0112
てってけてー
うっかり呑兵衛
-
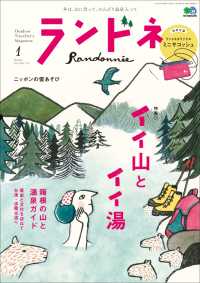
- 電子書籍
- ランドネ 2019年1月号 No.103
-
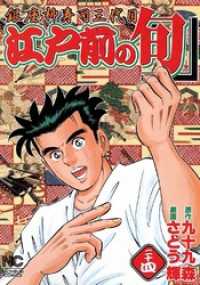
- 電子書籍
- 江戸前の旬 24




