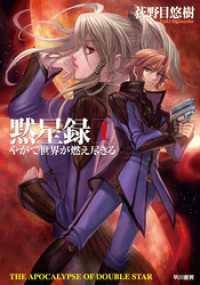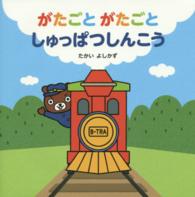目次
1 戦略上の要衝(石油・天然ガスの輸送ルート・供給源をめぐる問題;戦略上の要衝―コーカサスと黒海)
2 民族の問題(民族の十字路―コーカサス概略史;南コーカサス三国;北コーカサス;民族抑圧の根源に向き合う)
著者等紹介
中島偉晴[ナカジマヒデハル]
1939年東京目黒生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。産業団体勤務・定年退職。国際政治経済、ソ連論、アルメニア高地・コーカサスの民族問題研究。1980年以来アルメニアを中心にコーカサスを訪問。1984年日本アルメニア研究所(後の「日本アルメニア友好協会」)設立。1984、87年アルメニア高地訪問。1993、98年ナゴルノ・カラバフに入る。2000年和光大学オープンカレッジ講座「アルメニアの民族・文化、歴史」講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
(k・o・n)b
2
コーカサス関係は廣瀬陽子さんの書籍に続き2冊目。少し知識は付いてきたが、まだ慣れない固有名詞が多くしんどい…。08年の南オセチア戦争後に書かれたため、ジョージアに関する記述が多い。ロシアに侵略された被害者という印象が強かったが、ジョージアが民族主義を掲げ「国内」マイノリティを抑圧したのが原因だった模様。民族が違うから戦争になると抽象的に語っても無意味で、具体的に誰が誰を抑圧していて、どんな問題があるのかに注目すべきだとの主張が印象的。ともすれば、アルメニア善玉・アゼル悪玉論みたいになりそうとも思ったが…。2020/11/02
宵子
2
コーカサス地域の民族問題について、日本語で書いた数少ない本。特に北コーカサスの民族については日本語資料が少ないため、ある意味貴重かもしれない。ただし、恐らく著者はアルメニア側の立場であることを注意して読む必要がある。また一部誤植及び間違いがあるのも注意。あと固有名詞のカタカナ表記が統一されていない(英語由来なのかロシア語由来なのかなど)のも気になった。2015/09/26
MORITA
2
本書の舞台となった3国を旅したが、どの国の人も朗らかで親切で隣国と領土問題を抱えているとは信じられなかった。西洋諸国がもたらした”民族主義”に正しい一面があることは認めるが、それが全てではないことも忘れてはいけない。2015/05/04