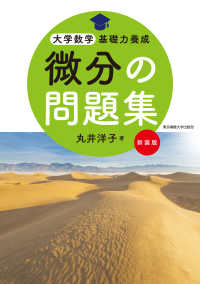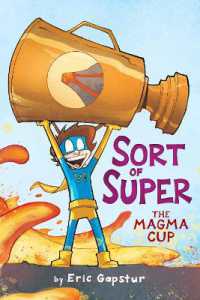目次
タイ国史の見方
政治と法
タイ経済の構造
諸産業
教育
宗教と信仰
タイ語
エスニック・タイ
タイ社会の諸断面
タイ・イメージの輪郭
タイの都市
現代タイ点描
日タイを架橋するもの
著者等紹介
綾部真雄[アヤベマサオ]
1966年、福岡県生まれ。筑波大学第二学群比較文化学類卒。東京都立大学大学院社会科学研究科博士前期課程修了。チェンマイ大学社会学部客員研究員を経て、東京都立大学大学院社会科学研究科博士後期課程単位取得退学。成蹊大学文学部国際文化学科専任講師、助教授を経て、首都大学東京大学院人文科学研究科教授。博士(社会人類学)。文化(社会)人類学、タイ少数民族研究、エスニック・セキュリティ研究を専門とする(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
(k・o・n)b
7
最近タイ語の勉強を始めたので、国自体についても知るために手に取ったが、意外と高度な内容。せめて先にある程度の歴史の流れと地理くらいは把握しておくべきだったなと反省。それでも、想像以上に多様性に溢れたタイの姿を垣間見ることはできた。ラーンナー等、単線的王朝史観から外れたタイ族の歴史は今後もっと勉強したい。バンコクに行った際、少し市街地から離れると運河が発達していて驚いたが、むしろ水運が先で道路は後から整備されたと知れて目からウロコだった。高貴な人との会話だけで使う「王語」があるというのはユニークで面白い。2023/07/08
isao_key
7
前作『タイを知るための60章』が2003年5月発行だったので、11年ぶりの改訂になる。第2版とあるが、内容はすべて新たに書き直され、項目、執筆者、頁数も大幅に増やし現在のタイを反映した内容になっている。タイ全般についての知識を得るためには過不足ないたいへん優れた一冊である。内容面についても、これまで一般論を語っていた部分も、執筆者の踏み込んだ考えが投影されていておもしろい。また前作では取り上げられていなかったキック(ギック)、カトゥーイについてもコラムと1章を設けて考察している。売れ行きがいいのも分かる。2014/09/16
fumi
5
タイにはうるち米(炊飯)圏ともち米(蒸し飯)圏があること、チェンマイは京都をハイブリッドにしたような街だということ、93%は仏教徒だがムスリムやキリシタンも数%いること、仏教徒の中には華人も多数いて独自の宗教文化を擁していること、カンボジアとの長く続く領土紛争などを初めて知った。タイは本文中のことばを借りれば「中進国」で、先進国を自称する我々はついかの国の人たちを「純朴で、温かく、信仰心に篤い」などと一言でまとめがちなのだが、それもタイ王室が喧伝し都市部の人々が信じている幻想では、という視点が一番の収穫。2017/12/23
うちこ
4
前回タイへ行ったあとに、あれはなんだったのだろう? という光景について、この本を読みながら回想しました。 テレビのニュースやドラマで見る様子とか、学生さんや若い人たちの行動、街に貼ってある張り紙の意味がふわっと気になって残っていました。 この本はコラムで取り上げている題材がおもしろく、やっとタイ独特の日常的な文化を少し感じられたように思います。 テレビを見ていると、どこかの機関や組織、学校にたぶん王族と思われる人が来てなにかの式典をやっている様子がよくニュースで流れていたりして、その謎が少し解けました。2023/07/01
くまパワー
3
タイ研究の学者たちが書いた教養本である。執筆者紹介を見るとほぼ一人が記事1本や2本を書き、おそらく日本のタイ研究者の大半が参加していたでしょう。4ページくらい程度で一つの論点を紹介することで入門者に対し読みやすいと思う。「タイ国史の見方」から始まることが極めて面白い、史学史から見るとタイの国民国家史観が結構強いし、タイ研究のベースになっている。「タイ社会の諸断面」と「現代タイ点描」でいくつかの新しい論点を紹介したこともよき。最後のブックガイドで各文献に何行くらい簡単な紹介があるため使いやすい。2023/04/17