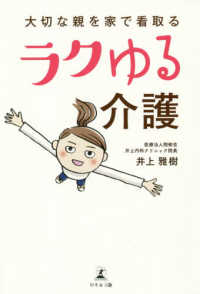目次
序章 人類学はなんの役に立つのか
第1章 贈るモノ、売るモノ、売っても贈ってもダメでとっておいて継承しなくてはならないモノ
第2章 家族や親族に基礎をおく社会など存在したことがない
第3章 子どもをつくるには男と女のほかに必要なものがある
第4章 人間の“性”は根本的に非社会的である
第5章 個人はいかにして社会的主体となるのか
第6章 複数の人間集団はどのようにして社会を構成するのか
結論 社会科学をたたえる
著者等紹介
ゴドリエ,モーリス[ゴドリエ,モーリス][Godelier,Maurice]
1934年生まれ。フランス国立科学研究センター(CNRS)研究部長を経て、社会科学高等研究院研究指導教員(教授級)。2001年にフランス国立科学センター金メダルを授与される
竹沢尚一郎[タケザワショウイチロウ]
1951年生まれ。九州大学大学院教授を経て、国立民族学博物館教授
桑原知子[クワハラトモコ]
1968年生まれ。熊本学園大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
7
人類学は人間集団の横の繋がりと縦の繋がりを記述してきた。が、経済学に依拠した構造主義を採る人類学は、贈与や交換を横の繋がりを中心に考察する傾向があった。『贈与の謎』で「神々への贈与」を検討した著者は、本書第2章で「贈るモノ」や「売るモノ」でない「贈っても売ってもダメなもの」=「聖なるもの」を伝える縦の繋がりを作り出す人間の関係構築の仕方を前景化し、人類学の再構築を試みる。その際、非社会的な性を人間社会にどう取り込むのか、家族や親族に基礎をおく社会はあるのかというラディカルな問いが提示される(2007刊)。2024/05/08
Teo
0
期待した人類学の壮大な再構築と言う話ではなかった。しかし、そう言う面よりも各論の中にある著者が三年間ニューギニアのバルヤで行ったフィールドワークの話は興味深いものであった。そっちに特化した本を選べば良かった。2011/08/03