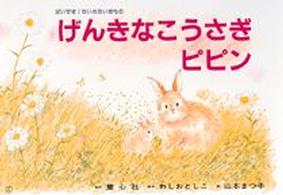内容説明
特別支援学校に通う児童生徒が急増し、現場では混乱が起きている。1学級に定員以上の児童生徒を在籍させ、それでも教室が足りず、会議室や相談室を教室に転用。学校を新設しても、それを上回る勢いで生徒が増加している。子どもたちの教育環境は低下する一方だ。なぜ、特別支援学校に児童生徒が集まってくるのか。養護学校の元校長であり、牧師でもある著者が、現場での豊富な体験をもとに、学校の「排除」の問題と、理想の教育や社会はどうあるべきかを語る。
目次
第1章 なぜ特別支援学校の児童生徒は急増しているのか(特別支援学校の過大規模化;過大規模化の背景にあるもの;特別支援教育への無理解;特別支援教育をめぐる排除の実態)
第2章 学校の非寛容(高等学校教育を考える;学校と警察との連携が意味するもの)
第3章 特別支援教育から支援教育へ(障害と特別な教育的ニーズ;特別支援教育の視座から見える教育課題;神奈川の支援教育)
第4章 「自立活動」必修化のすすめ(特別支援教育における自立活動の役割;すべての児童生徒に自立活動の授業を)
第5章 インクルージョン社会の実現に向けて(インクルージョンとは何か;社会変革を教育目標に掲げた学校)
著者等紹介
鈴木文治[スズキフミハル]
田園調布学園大学教授(特別支援教育、インクルーシブ教育担当)。1948年長野県生まれ。中央大学法学部法律学科卒業、立教大学文学部キリスト教学科卒業。川崎市立中学校教諭、神奈川県立第二教育センター、神奈川県教育委員会、神奈川県立平塚盲学校長、神奈川県立麻生養護学校長などを経て、現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
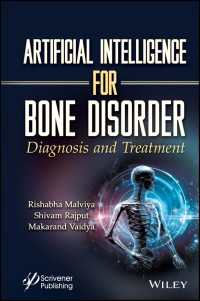
- 洋書電子書籍
- Artificial Intellig…
-

- 洋書電子書籍
- コンピュータ科学と数学におけるファジィ…