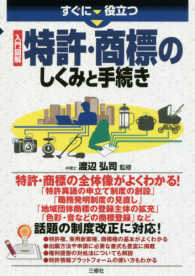出版社内容情報
わたしたち一人ひとりが希望をもち、心おだやかに生きることのできる社会を保障するためにある憲法。憲法とはどういうものなのか、わたしたちのくらしとどういう関係があるのか、子どもからおとなまでその意義を再確認できるはじめての憲法絵本。
内容サンプルイメージ(明石書店HPより)
憲法でささえるくらし
さまざまなくらし
わたしのことはわたしが決める
心は自由
考えたことを伝えたい
教育への権利
行きたいところに行く自由、働く権利
ふたりは平等
生きることは権利
いやなことはいやと言える
みんなが平等にもっている人権
国のやくわり
日本国憲法のできる前
制限されていた人権
自由をもとめる人たち
戦争への道
日本国憲法の誕生
大きなぎせいと新しい憲法
武力から平和は生まれない
平和は人権の実現から
憲法を使ってしあわせになるしくみ
はじめての永久の権利
みんなのことはみんなで決める
みんなで決めても、うばえない人権
憲法をまもるのは、国
憲法にもとづいておこなう政治
憲法のちから
裁判所は人権保障のとりで
希望の憲法
手ばなしてはいけない自由
みんなでまもるみんなの権利
希望をあきらめない
もう少し知りたい憲法の歴史(野村まり子)
すべての人が自由な社会のために憲法がある(笹沼弘志)
日本国憲法
困ったときに相談できるところ 他
もう少し知りたい憲法の歴史
●ギリシャ悲劇アンティゴネーの「神のおきて」
紀元前500年ころのお話です。テーバイの王オイディプスの娘、14歳のアンティゴネーには、ふたりの兄がいました。父王が王位を去った後、兄たちは交代で王位につきました。しかし、弟王が約束をやぶったために、兄王は他国と手をむすんで自分の国を攻め、兄弟は刺しちがえて亡くなります。あとを継いで王となったおじは、弟王の遺体は丁重にとむらいましたが、兄王の遺体はむほん人として野に放置し、「埋葬者は処刑する」という命令をだしました。
アンティゴネーは、放置された兄王の遺体を埋葬しようとして捕らえられ、王の前に引きたてられます。命令に従わないことをせめる王に対し、少女は「善悪をこえて死者を等しくとむらうことは、神のおきてであり、人間にはくつがえせないこと」だと反論します。死者をいたむ感情やとむらう習慣は、人がつくる法にまさるというのです。
2500年前のこの話は、現代の憲法の思想に受けつがれています。14歳の少女でも、おかしいと思えば、相手が王であろうと、自分の意見を言えること。その根拠として、人間のつくる法にまさる神の法(自然の法)があると言っていることです。
古代ギリシャ時代には、国家ではなく個人を尊重する考えが生まれ、民主政治がおこなわれていました。
●自然法思想と市民憲法の誕生
人間は、ながい歴史のなかで、どのような社会をつくって集団で生きてゆくか、さまざまな経験をしてきました。国王などの権力者や権力をもった宗教が、身分制度をつくり、人びとを支配した時代もありました。戦争もくり返しおこなわれました。そのような経験をとおして、人間は人としてよりよく生きることを考えてきました。
ヨーロッパでは16世紀のルネサンス時代に、古代ギリシャ、ローマに学んで、個としての人間の解放がもとめられました。それは、のちに、人は自然状態でくらしていたころは、みな独立、平等で、自然法によりだれからもうばわれない人権をもっていた、という自然法思想の誕生に影響をあたえます。
18世紀、新たな社会のあり方をさぐっていた人たちは、自然法思想をとりいれて、個人の自由や権利を保障するために、みんなで協力して国をつくることを提案しました。アメリカやフランスでは、生まれながらの自由と平等をかかげて革命がおこり、身分制度をなくした、国民主権の近代国家が誕生します。そして、憲法は、国が権力を濫用して、個人の自由をうばうことがないように、国が守らなければならないルールとしてつくられました。
ですから、憲法は伝統的に、国をつくった目的である人権を宣言する部分と、その人権を実現するための国の機構のあり方を定めた部分からなりたっています。
みんなで国をつくり、みんなのことをみんなで決める民主主義と、人権保障を目的として憲法で国の権力を抑える立憲主義は、多くの人びとの共感をよび、世界にひろがりました。でも、平等と言いながら、女性の人権は認められず、少数者への迫害や奴隷制、植民地支配もつづきました。また、経済活動の自由に保障された近代産業の発展は、劣悪な条件で働かされる、子どもをふくむ労働者階級と、貧富の差を生みだします。
すべての人の人権を実現させるには、みんなの意識の変革が必要でした。アメリカの公民権運動のように、人権を獲得し、尊厳を回復しようとする人びとのいのちがけのたたかいが、社会全体の人権状況を改善させることもありました。
(…後略…)
内容説明
くらしと憲法をつなぐはじめての絵本。12歳から学ぶ市民のための人権ガイド。憲法がどういうものなのか、わたしたちのくらしとどういう関係があるのか、を中心に、えがいている。
目次
憲法でささえるくらし(さまざまなくらし;わたしのことはわたしが決める ほか)
日本国憲法のできる前(制限されていた人権;自由をもとめる人たち ほか)
日本国憲法の誕生(大きなぎせいと新しい憲法;武力から平和は生まれない ほか)
憲法を使ってしあわせになるしくみ(はじめての永久の権利;みんなのことはみんなで決める ほか)
希望の憲法(手ばなしてはいけない自由;みんなでまもるみんなの権利 ほか)
著者等紹介
野村まり子[ノムラマリコ]
1949年、高知県高知市生まれ。アニメーションの作画から、児童書、雑誌などのさし絵の仕事にたずさわる。その間に地域で、共同購入や不登校、環境にかかわる活動に参加。『えほん日本国憲法』の出版を機に、村田から野村に改姓
笹沼弘志[ササヌマヒロシ]
1961年生まれ。早稲田大学大学院法学研究科博士課程単位取得。静岡大学教授、憲法学専攻。人権理論、とくにホームレスの人びとの権利に関する研究にとりくむ一方、地元でホームレスの人びとの支援活動をおこなっている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
千加
絵本専門士 おはなし会 芽ぶっく
絵本専門士 おはなし会 芽ぶっく
小林だいすけ
ぺそ