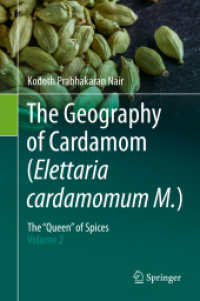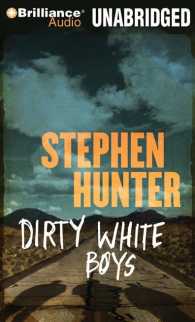出版社内容情報
学力低下論は総合学習批判としても表れたが、国際学力調査から学ぶべきは、競争や数値によらない新時代の学びとしての総合学習の可能性の追求。オランダなど世界の学びの方向に着目しつつ、日本での意欲的実践を紹介。小山内美江子氏の寄稿にも励まされる。
はじめに(佐藤 隆)
第1章 新しい時代の世界の学び
オランダ
個性を伸ばし共同性を育てる
――オールタナティブ教育とともに発展した総合学習(リヒテルズ直子)
コスタリカ
統合的価値観に基づく教育
――「軍隊をすてた国」の平和文化教育(足立力也)
韓国
「開かれた教育」と民主主義への課題
――画一的統制を乗り越える教育現場の試み(石坂浩一)
エコロジカルな学びに向かって
――ゲディスに学び、ゲディスを超える(安藤聡彦)
フィンランド
〈自己物語〉を世界へつむぐ
――物語のある(ナラティブな)学び(narrative learning)の探求(庄井良信)
第2章 学校を変え地域とつなぐ学び
多様な学びのしかけとしての「総合」
――観の形成を促す自由の森学園の教育(鬼沢真之)
学びの力は想像と創造の力
――都市と地域とアートとお年寄り、世代をつなぐ総合の学力(佐藤広也)
ひとつのテーマを貫いて広がる学び
――動物介在教育を行う障害児学級(渡辺克哉)
学社融合と総合学習
地域と協働してつくる総合学習
――今を生きる力、明日を生きる力(越田幸洋)
学び合いから生まれる地域デザイン
――総合学習を支えるコーディネーター(藤尾智子)
第3章 総合学習を支えるまなざし
学びの質を高め学校を変える総合学習
――「もの」探しから出発し、学びの共同体へ(千葉 保)
学びの意味を取りもどす場に
――「総合的な学習の時間」を取材して(松本由佳)
第4章 未来の人間を育てる総合学習(小山内美江子)
第5章 学力を問う総合学習
「総合的な学習の時間」が意図していたもの
――学校カリキュラムがもつべきバランスと調和(奈須正裕)
子どもの「問い」と響き合う
――生活綴方の精神を総合学習の思想に(佐藤 隆)
あとがき(鬼沢真之)
はじめに
未来と世界に逆行する日本の教育改革
21世紀を迎えて世界の教育は、その大すじにおいて、ユネスコ学習権宣言や子どもの権利条約がさし示す、「世界とつながり自己を育てる」教育を成熟させる方向に足を踏み出している。ところが、日本の教育はむしろこれに逆らうかのような動きを示しているとはいえないだろうか。特にここ数年間の「学力低下」論議は、「〈テスト〉の得点さえ上げられればそれでよい」とするような風潮を生み出し、教育と学習を、教師にとっても子どもにとっても魅力の感じられないものに向かわせているように思えてならない。
こうした動きを加速させたものに、2004年末にOECD(経済協力開発機構)と国際到達度評価学会という二つの団体からほぼ同時に発表された調査結果に対するマス・メディアや教育行政の過剰な反応と誤った対応がある。日本のメディアの多くは、調査内容の吟味もほとんどないままに「子どもたちの『学力』が前回調査よりも下がった」と大きく報じた。これに「あわてた」当時の中山成彬文部科学大臣は「『ゆとり教育路線』は誤りだった」として、こんどは「子どもたちに社会に出たらきびしい競争の世界が待っていることを自覚させ、互いに切磋琢磨して学び合う環境をつくり世界のトップレベルの学力の復活をめざさなければならない」という発言まで行った。
しかし、「競争によって学力を上げる」という文科相の主張にどれほどのリアリティがあるといえるのだろうか。また、「社会がきびしい競争の世界」であることをア・プリオリに肯定し、それを子どもたちに認識させるのが教育だとするような「教育観」を簡単に認めてしまってよいのだろうか。
確かに、このような認識は、学校での業績達成(学力)競争が、企業社会内での序列構造と密接に結びついていた、そしてそれを人々が「あたりまえのこと」として受け入れていた1990年代前半までの日本社会のなかでは、一定のリアリティをもちえたかもしれない。しかし、状況はこの10年間で一変した。「終身雇用・年功序列」「新規学卒一括採用」などをはじめとする「日本型雇用」慣行が崩れ、かつてのように「ある程度がんばれば、『人並みの進学』ができ、『人並みの就職』ができる」などという実態は、もはやどこにも存在しない。そのような事態の到来によって、限られた「勝ち組」枠をめぐっての競争は、この競争に参加できる「文化的・経済的資本」のもち合わせのある人々による競争として、これまで以上の激しさをともないながらも局部化し始めている。
そしてその対極には、早くから「競争からおりる」子ども・若者が大量に生み出されている。「ニート・フリーター」問題の背景の一部にはこうした問題が存在していることは明らかである。しかし、このことからもわかるように、若者たちが「競争からおりた」からといっても、彼らの内面に平穏がもたらされたわけではない。実際にはその反対に、子ども・若者たちは、仕事や生活についての知識も技術の準備もないまま、社会的な競争に直接的にさらされるであろう未来への不安をもって生きざるをえなくなっている。今、日本社会の構造的な変化のなかで、子どもや若者たちは「自分は何をしたいのか」「どんなおとなになれるのか」といった「人生イメージ」を描き出せずに、とまどい苦しんでいるように見える。その「とまどいや苦しみ」が、自傷行為も含んだ攻撃性や「勉強離れ」行動に表れてきたのだ、と言っては言いすぎだろうか。
子どもたちが示した学習意欲の低下と学校知識への疑念
先にあげた二つの国際的調査の結果も、文科相のいうような「ゆとり教育」が原因なのではなく、日本社会の構造的な変化によって引き起こされた子どもたちの学習意欲の総体としての低下であることを物語るものといえるのではないだろうか。
たとえば、PISA(OECD生徒の学習到達度調査)において得点が高いとされる「レベル5」以上の生徒がこれまでと同様にかなりの割合で存在する一方で、得点の低い「レベル2」以下の生徒が急速に増えており、それが全体の平均点を押し下げるまでになっていることもその一つである。しかも、問題(出題の形式)によっては、解答を試みようとさえしない「無答」の割合が高いことも明らかになっている。また、家庭での学習時間も、平均すると他の国々に比べるとかなり低いところにとどまっていることも気になることの一つである。
これらを通じていえることは、おそらく、これまでどおりに「勉強をしている」子どもたちと、家庭での勉強どころか授業を受けることさえ苦痛と感じているいわゆる「勉強離れ」が著しい子どもたちとの二つの層にはっきり分かれてきていると考えられることである。
次に指摘したいことは、学校で教えられ、学ばれるべきものとされる知識(学校知識)の意味やその有用性についての疑念が、得点の高低にかかわらず、子どもたちから提起されていることである。国際到達度評価学会が行った調査では、「数学がすき」「数学に積極的にとりくんでいる」と答えた日本の中学生はわずか17パーセントにすぎず、国際平均の55パーセントとは大きな開きが確認されている。
PISAにおいても同様な傾向が確認できる。そのほかにも「学校なんて時間の無駄だった」という質問に対して「全くその通りだ」「その通りだ」という回答の合計は10パーセントを超えており、OECD加盟国の平均を上まわっている。また、「学校は仕事に役立つことを教えてくれた」とする質問項目に対しての否定的な回答の割合は40パーセントにのぼっている。これは加盟国平均の約4倍という驚くべき数値となっている。
これらの結果は、学校知識が、子どもたちにとって必ずしも魅力的ではなく、自分にとって意味のあるものと感じられていないことに起因するものとみるべきである。
このように、「学力低下」問題の本質は明らかである。しかし、教育行政や一部の教育関係者のこの問題への対応は、現在の学校や授業のあり方の抱える問題を解明するのとはまったく反対に「勉強をしないのは子どものほうに問題がある」からだとして、これまで以上に「子ども・若者バッシング」を強めようとしている。さらには、この機会を利用して、競争こそが学力を高めるのだというレトリックを用いながら、実際には、学校での教育活動をマニュアル化し、およそ教育実践とは呼べないものに変質させたうえで、掲げた数値目標への達成度によって教員評価・学校評価ができるしくみをつくり出そうとしている。それだけではない。一見すると公平のように見える「テスト」をくり返すことによって、競争に勝ち残ったものが優遇されて当然であるという「弱肉強食」の原理を社会と教育のすみずみにまでゆき渡らせる雰囲気づくりに利用しようとしているのである。
総合学習が切りひらく新しい学びの姿
私たちが見据えなければいけないのは、今日の教育行政が行おうとしている「競争によって学力を上げ」ようという虚構のうえに成り立つ主張には、成長・発達の当事者であり主体である子どもの声に深く耳を傾けて、生活や学習に関わる切実な関心や要求を誠実に受けとめるという姿勢が決定的に欠けていることである(田中孝彦『生き方を問う子どもたち』〈岩波書店、2004年〉参照)。
すでに述べたように、「学力低下」や「勉強離れ」は、日本の学校を支配し続けてきた「競争の教育」がゆきづまり、勉強をすることが自分にどう役立つのかが見えにくくなっている状況と相まって、これまでのようには「受験」などの競争刺激がはたらかない事態を背景にしている。その意味では、「競争の教育」に由来する「苦役としての学習」システムが崩壊する兆候であるとともに、これに代わるべき教育の内容と方法を、子どもたちが待ち望んでいることの表れであると理解するべきである(久冨善之「競争の教育のゆくえ」〈『教育』2000年3月号〉など)。
そうだとすれば、「学ぶ」とはどういうことか、そして「学力」ということばに託すべき内実とは何かを、子どもたちとともに、今ある現実の世界のなかに描き直していく努力が、ますます重要かつ緊急なものとなってきているといえる。
この点で、改めて「総合的な学習の時間」のもつ可能性と課題を今日の時点で整理してみることがどうしても必要となってくる。
教科書も評価もない「学び」。何をどのように学ぶのかということすら、極端にいえば当事者である教師と子どもたちとのコミュニケーションにすべてゆだねられている「学び」。こうした「学び」から探し出されるものの意味をどのように位置づけるのかという「実験」が始まっているのである。
確かに2002年に実施された『学習指導要領』のなかで提起された「総合的な学習の時間」は、「時間」という制約や、条件整備のないままの「強行的な実施」のもとで、さまざまな意味で混乱を招いたのは事実である。しかしそれでもなお、「総合的な学習の時間」が提起している理念のなかに、競争によって支えられてきた「日本型高学力」を生み出した学校のあり方を鋭く問い、新しい学習のあり方を展望する契機があると、私たちは考えている。
総合学習の思想を確かなものに
本書は、こうした問題意識のもとで編まれたものである。とはいえ、「総合的な学習の時間」にせよ総合学習にせよ、その実態を正確に把握するのはむずかしいのも事実である。
本書に登場する日本の教育実践も、さまざまな語り口で語られ、受け取り方によっては総合学習と呼ぶのをためらわれるものまで含まれているかもしれない。しかし、それらの底流には、今求められている「学び」とは、単に知識の量を増やすということではなく、それらの知識や技術を子ども自身の経験と感覚をとおして編み直していく過程が強く意識されている。これらの「学びの記録」のなかから読み取ってほしいのは、これまで「教えられる側の者」として位置づけられてきた子どもたちが、教師やおとなたちの手を借りながらも、しだいに「学びの主人公」として立ち現れてくる姿である。
本書のもう一つの特色は、日本の教育と同質の課題を抱えている韓国の状況の紹介を含めて、各国での総合学習のとりくみやそのための条件などを検討していることである。これらを読んで気づかされることは、フィンランドやオランダ、コスタリカなど、そのどれをとっても、「持続可能な」社会の責任あるメンバーとして子どもを迎えることが教育の第一の仕事であるという国民的な共通理解に支えられてとりくまれていることである。方法や内容はさまざまではあるが、そのダイナミックな制度設計と、子どもたちに対する教師のていねいな向き合い方は、総合学習の思想そのものが要請しているものであることはまちがいない。
それだけに、形式だけを日本の教育に「輸入」したところでほとんど意味はないし、そもそもそのようなことは不可能であろう。私たちに必要なことは、目の前にいる「学びの主人公」である子どもたちとの対話を重ねながら、一つひとつの「学び」をていねいにつくり出していくことである。それこそが、日本における総合学習の思想を確かなものとする唯一の方法であり、私たちの教育改革の出発点なのだから。
2006年 7月
佐藤 隆
内容説明
学力低下論は総合学習批判としても表れたが、国際学力調査PISAから学ぶべきは、競争や数値によらない新時代の学びとしての総合学習の可能性の追求。オランダ・コスタリカ・フィンランドなど世界の学びの方向に着目しつつ、日本での意欲的実践を紹介。
目次
第1章 新しい時代の世界の学び(オランダ 個性を伸ばし共同性を育てる―オールタナティブ教育とともに発展した総合学習;コスタリカ 統合的価値観に基づく教育―「軍隊をすてた国」の平和文化教育;韓国 「開かれた教育」と民主主義への課題―画一的統制を乗り越える教育現場の試み;エコロジカルな学びに向かって―ゲディスに学び、ゲディスを超える;フィンランド 「自己物語」を世界へつむぐ―物語のある学び(narrative learning)の探究)
第2章 学校を変え地域とつなぐ学び(多様な学びのしかけとしての「総合」―観の形成を促す自由の森学園の教育;学びの力は想像と創造の力―都市と地域とアートとお年寄り、世代をつなぐ総合の学力;ひとつのテーマを貫いて広がる学び―動物介在教育を行う障害児学級;学社融合と総合学習 地域と協働してつくる総合学習―今を生きる力、明日を生きる力;学社融合と総合学習 学び合いから生まれる地域デザイン―総合学習を支えるコーディネーター)
第3章 総合学習を支えるまなざし(学びの質を高め学校を変える総合学習―「もの」探しから出発し、学びの共同体へ;学びの意味を取りもどす場に―「総合的な学習の時間」を取材して)
第4章 未来の人間を育てる総合学習
第5章 学力を問う総合学習(「総合的な学習の時間」が意図していたもの―学校カリキュラムがもつべきバランスと調和;子どもの「問い」と響き合う―生活綴方の精神を総合学習の思想に)
著者等紹介
鬼沢真之[オニザワマサユキ]
1960年、茨城県生まれ。1986年より自由の森学園社会科担当教師。2004年4月から、同学園高等学校校長。自由選択授業「林業講座」を担当し、毎週木曜日の午後は作業服に地下足袋、ヘルメット姿に変身する。2004年から、学園で日常目にしていることを「自由の森日記」というブログで綴っている
佐藤隆[サトウタカシ]
1957年、北海道生まれ。都留文科大学教授。教育学、教育実践学、教師教育論。地域民主教育全国交流研究会編『現代と教育』編集長として、全国の教師と交流を深めている。現在は、教師(特に若い教師)たちが抱えている困難や苦悩の根源に迫ることと、そこに生まれつつある新しい教師像の探求を課題としている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。