出版社内容情報
中学・高校で待ったなしの職場体験とキャリア教育。社会的自立を支え働く権利を保障する理念と、兵庫「トライやる・ウィーク」や町田市「押しつけられた『職場体験』にどうとりくんだか」など全国的に注目される実践を紹介。ハウツーでない新しい学びに挑戦。
1章 いま「職場・体験」を考える(綿貫公平)
2章 働くことをどう学ぶか
生きることと労働に学ぶ学校に!
兵庫・「トライやる・ウィーク」をつくりかえる(小川嘉憲)
平和を希求し生きることと働くことを
学年でとりくむ中学校3年間の「総合」(持田早苗)
出会いを重ね人間の生き方を学ぶ
大東学園高等学校福祉コースの実践(十二雅子)
「働くためのルール」を考える
「キャリア教育」をつくりかえる試み(藤掛沖幸)
仕事へとわたっていくことをサポートするベーカリー
「若者自立塾」の現場から(佐藤洋作)
3章 しなやかに、したたかに
東京・町田市 押しつけられた「職場体験」にどうとりくんだか(宮下 聡)
4章 シンポジウム いま働く若者の現場は…
(菅原良子/山本賢司/菊池 謙/佐藤洋作)
5章 いま「働くことを学ぶ」ということ
「キャリア教育」にふれながら(菊地良輔)
あとがき(綿貫公平)
●全国進路指導研究会(全進研)紹介
あとがき
昨年(2005年)の全進研大会参加者アンケートで「全進研として、いま職場体験についてまとめるべきではないか」という、期待を込めたご指摘をいただきました。確かに、ここ数年私たちは、進路教育・進路指導の課題として、「学校から学校へ」の接続問題だけでなく、そのつなぎ・わたりの部分を重視するからこそ「学校から職場(仕事・職業・社会)へ」の問題に目を向けざるをえませんでした。企業犯罪ともいうべき「サービス残業」など、働き方・働かされ方の克服が課題となる一方で、若者の就職難・非正規雇用化が常態化している状況。それは、「学ぶこと」と「働くこと」のあいだにくさびを打ち込んでいるようにも思え、さらに混乱に拍車をかけるような「キャリア教育」の登場もあいまって、力不足を承知しつつも一度交通整理しなくてはならないと考えていました。
子ども・青年を「一人前にする!」ことを前提に、彼らの自立を援助するため、中学校・高校でなすべきことは何か、その接続はどうあるべきか、と年齢をさかのぼる問いの立て方にたどりついたのです。
この間の、大会講演・報告内容をふり返れば、それは明らかです。
・第39回大会(2001年)記念講演:熊沢誠氏「職場と教室――日本的能力主義とこれからの進路・職業教育」
・第40回大会(2002年)記念シンポ:木ノ内博道氏+小杉礼子氏+平塚眞樹氏「青年の働く道をどう切り拓くか――卒業の先に自立が見えない」
・第41回大会(2003年)記念講演:宮本みち子氏「今、若者が直面しているもの――大人になる夢と困難」、特別報告:小川嘉憲氏「『生きること』と『労働』を学ぶ学校に」シンポジウム:「子ども・青年の進路をどう拓くか」首都圏青年ユニオンの若者たち+林萬太郎氏
・第42回大会(2004年)記念講演:児美川孝一郎氏「現代社会を生きる子ども・青年の学びと進路」
・第43回大会(2005年)記念講演:中西新太郎氏「社会に出るとはどういうことか――若者たちの将来像と進路獲得」、特別報告:藤掛沖幸「働くルールを考える」
そして毎回現代の若者が集い、ともに語り・学び合う分科会も設定してきました。
この夏、第44回大会(2006年)では、記念講演に過労死弁護団の川人博弁護士に依頼しました。世界的にも異常で、違法ともいえる長時間過密労働から派生する現実を「過労死社会と学校」というテーマで話していただきます。精神的に追いつめられ、死ぬまで働かざるをえない職場の状況の背景に、問い直さねばならない学校教育のあり方があるのではないか。「過労死」を下支えする学校教育の姿を明らかにし、改善の糸口を探りたいというのが目標です。
こうした緊急性を抱えながら、満を持して、『働くことを学ぶ―職場体験・キャリア教育』を刊行いたします。
まず、第2章は「働くこと」について学び考えるための実践報告です。
◆最初に「中2の秋・連続5日間」を押しつけられる「職場体験」のモデルとなった、兵庫の「トライやる・ウィーク」について、そのねらいを批判し、「生きること」と「労働」を学ぶ機会としてつくりかえた兵庫・西宮市の小川嘉憲さんの実践レポートです。第41回全進研大会(2003年)で特別報告していただいたものです。小川さんには、第34回大会(1996年)でも、阪神・淡路大震災で街の大半が全半壊した地域で、教え子の3人を含め多くの犠牲、大きな被害のなかから「中学生は主権者として生きる力をはぐくんでいた――大震災と中学生たち」と題した感動的な報告を受けています。県の行政からトップダウンで下ろされた「奉仕と順応の『心の教育』」を推し進め、「地域総動員体制をつくろうとする」施策のねらいを明らかにし、子どもたちのためにほんとうに必要な力を育てる機会としていったドラマ。そのカギとなるのは、体験をやりっぱなしにせず、「問い」をもって参加し検証する「問いを立てる」力に期待し、そして事後のディベートで、共同化する作業で裏打ちしているところです。
◆実践の二つ目は、今春(2006年)の全進研春季集会で報告を受けた、神奈川・持田早苗さんの実践です。副題にあるように、「職場体験」は、「中2の秋」突然現れるわけではなく、3年間を見通した「平和を希求し『生きること』と『働くこと』を」掲げたとりくみの一つとして位置づいています。こうしたねらいと、ていねいなとりくみ方からは、体験日数が5日間でなければならない根拠は見当たりません。
◆三つ目の実践は、共学化と同時に、普通科に福祉コースを設けた東京・私立大東学園高校の実践について、その立ち上げから関わった十二雅子さんのレポートです。第43回全進研大会(2005年)で、最初の卒業生2人と在校生4人がともに出席して、先駆者としてのきびしさと醍醐味(だいごみ)を語ってくれました。3年生になると毎週木曜日の一定時間に参加する「施設でのボランティア体験」があります。それは、(1)働くことは持続・継続すること、(2)体験と体験のあいだに、少し時間をおくことによって、思うようにやれなかったことを見つめたり、次回への工夫や意欲がわいてきたりすることが引き出されていきます。「連続5日間」とは異なり、限られた時間のなかでも、持続・継続するなかで、働くことの本質が伝わってきます。
◆そして、藤掛沖幸さんの「『働くためのルール』を考える」は、第42回全進研大会(2004年)で話題を呼んだ報告「働くルールを教える」という、大阪の新谷威さんのレポートに触発された実践です。中3の3学期、「卒業論文」作成のために、学年教員が3コマずつ担当した「総合」の時間に、「埼玉版」として3回にわたって実践した、藤掛さん自主編成の内容です。
◆最後は、前述の「若者自立・挑戦プラン」において、厚生労働省の担当する「ニート対策」の目玉に位置づけられた「若者自立塾」の現場からのレポート。全国20か所で展開されている「働けない」若者たちへの社会的支援(若者政策)の一つとして、佐藤洋作さんらの東京・三鷹NPO文化学習協同ネットワークが委託されました。あらためて「働くこと」を学び直すとりくみの一つです。
第3章「押しつけられた『職場体験』にどうとりくんだか」は、「政策」として出され、上から押しつけられた「職場体験」に対して、現場から・教職員組合としてどのようにとりくんだか。東京都教職員組合町田支部の1年間の「たたかい」を、支部長の宮下聡さんにふり返ってもらいました。まさに「しなやかに、したたかに」トップダウンの無理難題を、ていねいに解きほぐして、押しつけの「企み」をはね返す運動のとりくみ経過は感動的です。特に市議会での意見陳述内容は、無法な押しつけの実態とそれへの適切な批判、あるべき職場体験の教育的意味を明らかにしています。このとりくみについては、第43回全進研大会(2005年)で渡辺真理子書記長から、さらに9月末の「一斉実施」直後の2005年10月拡大学習会では、検証プロジェクトの責任者阿部真一さんの報告を受けています(阿部真一「町田からの報告」『進路教育』No. 168、’06冬号)。
第4章「シンポジウム『いま、若者の働く現場は……』」では、現代の若者の姿や「働くこと」をリアルにとらえるために、第43回全進研大会(2005年)シンポジウムの内容を掲載しました。
シンポジストは、フリーターの若者たちの個人加盟組合・首都圏青年ユニオンの菅原良子さん。ユニオンは、若者の違法な「働かされ方」を告発し、団体交渉や訴訟をとおして一つの学習運動を展開し、今や全国に広がっています。「ひきこもり」や「働けない」若者たちを支援するNPO法人「育て上げネット」の山本賢司さん。ワーカーズコープという、自分たちが出資して、より働きやすい場をつくるという「働き方」にとりくむ労働者協同組合の菊池謙さんの3人です。
第5章では、ここ数年夏の大会で3日間の「総括講演」を担当してきた菊地良輔さんが、この本の「総括」もかね「いま『働くことを学ぶ』ということ」と題した論文をまとめています。特に一昨年(2004年)の全進研大会総括講演「いまを生き未来をひらく学びをつくる」を下敷きにしながら、あらためて現在の情勢や「キャリア教育」の課題にふれて書き下ろされたものです。
以上のように、この本には、ここ数年の全国進路指導研究大会で報告を受けたレポートや講演・シンポジウムのなかから、いま焦点とされる「職場体験」に関するものをはじめ働くことを学ぶために、広く深く考えるために必要な実践や論文・資料を掲載しました。当初の報告から大幅に書き換えていただいたものもあります。いわゆる「HOW TO」本のように、「すぐ役立つ」という簡便さはありませんが、そもそも「職場体験」をどうとらえるか、子どもたちに「体験」をとおして学ばせたい課題や、「体験」前後のとりくみスタンスなど、実施する前に職場や地域で集団的に論議してほしい柱が、テーマがたくさん立ち上がっています。単に上からやれといわれたから、押しつけられたから、といった「理由のから」でやるのではない、やらされるのではない。自分から、自分たちから、学校から、地域から、の「始まりを示すから」でいく、そのためのヒントが満載です。子どもたちと「職場体験」を実施する前に、一歩進めた「職場体験」を成功させるために、職場や地域での学習を深めるための一助としていただければ幸いです。
最後になりましたが、本書の刊行はゴール目標が決められたなかでのタイトな日程の刊行でした。にもかかわらず執筆依頼に積極的に応えてくださったみなさんに、深く感謝いたします。また、編集のプラン段階から相談に乗ってくださり、また、編集実務にあたってくださった明石書店スタッフのみなさんの献身的なお力添えがあり、はじめて形にすることができました。ありがとうございました。感謝に堪えません。
2006年夏の大会を前に
全国進路指導研究会常任委員長
綿貫公平
目次
1章 いま「職場・体験」を考える
2章 働くことをどう学ぶか(生きることと労働に学ぶ学校に!―兵庫・「トライやる・ウィーク」をつくりかえる;平和を希求し生きることと働くことを―学年でとりくむ中学校3年間の「総合」;出会いを重ね人間の生き方を学ぶ―大東学園高等学校福祉コースの実践;「働くためのルール」を考える―「キャリア教育」をつくりかえる試み;仕事へとわたっていくことをサポートするベーカリー―「若者自立塾」の現場から)
3章 しなやかに、したたかに―東京・町田市押しつけられた「職場体験」にどうとりくんだか
4章 シンポジウム いま働く若者の現場は…
5章 いま「働くことを学ぶ」ということ―「キャリア教育」にふれながら
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
すのう@中四国読メの会コミュ参加中





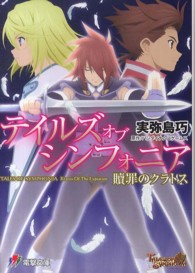
![電話のかけ方・手紙の書き方・資料請求の仕方 〈[’93]〉 - 入りたい会社に就職するための](../images/goods/../parts/goods-list/no-phooto.jpg)


