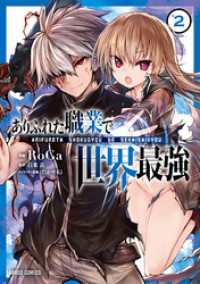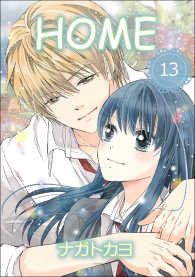出版社内容情報
『出雲国風土記』の現地調査が可能な最後の段階との認識を基に著者が足でひもといた十余年の研究の集大成。現場主義に裏打ちされた「生成」的検討の成果は『風土記』の文字に息吹・生命を与え、現地から古代世界への繋がりを再認識させる一級の資料・註論。
序
1 総 記
2 意宇郡条
3 嶋根郡条
4 秋鹿郡条
5 楯縫郡条
6 出雲郡条
7 神門郡条
8 飯石郡条
9 仁多郡条
10 大原郡条
11 巻末条
関係近世資料の解題
あとがき
序(抜粋)
1 はじめに
『出雲国風土記』注釈に関してはすでに優れた幾つかの成果を共有している。そういう中でここに新たな注釈を作成した意図について述べておきたい。
近年の古代史研究の特色として木簡、墨書土器などの出土資料の検討を通して今までの古代史像を再検討する方法が一大潮流となりつつある。その資料は発掘による新出資料であり、古代史研究者から熱い視線を受ける。しかし、古代史研究の基礎文献史料が十分な歴史的・「生成」的検討を受けず、「死蔵」的な状態のまま放置されていることも忘れてはならない。「生成」的検討とは史料・資料、そして文字一字一字に息吹・生命を与えることである。
本書の基になる『出雲国風土記註論』を書きはじめたのは実に十年余り昔である。島根県古代文化センターの客員研究員の一人として古代出雲の共同研究に参加する中で、出雲各地の現地調査に携わり、風土記に記された故地に浸る機会を多く得るようになった。しかし、同時にその故地に周囲から開発の波が少しずつ押し寄せるのを目の当たりにして、近い将来にはその姿が消え失せるとの確信も持たざるを得なかった。また各地での聞き取り調査の中で、地域伝承の担い手の高齢化にともない、伝承が希薄化し、場合によっては絶えたという現実に会い、現時点が伝承を収集する最後の時になりつつあることを実感したのも事実である。
考えてみれば先学の時代は、風土記的世界が濃厚に残っている中で調査ができるという恵まれた研究環境であったが、逆に調査に臨む交通手段が殆どないという問題を含んでいたのである。逆にわれわれは開発の進展により風土記的世界は薄れつつあるが、確かな交通手段を自由に操ることが出来るという至便さを手に入れているのである。この点は深く認識すべきであろう。何故なら今後の研究者は交通手段はあるが、風土記的世界が喪失している状況で研究に臨まねばならないからである。思えば、今、この時点が『出雲国風土記』研究において最も好条件なのではなかろうか。
本『註論』は現在が『出雲国風土記』の現地調査が可能な最後の段階との認識を基に、出来る限り五体を投げ打ち、地域地域に密着する形でまとめたものである。今後の研究者に十分な情報を提供できるような内容でなければならない。また、本『註論』が世に出ることにより、風土記時代を感じさせる歴史的環境が県・市町村、そして地域の人々によって再認識され、保護・保全されることを願うものでもある。
当初は勢いに任せ、十分な計画もないまま秋鹿郡より筆を起こしたが、結果的に執筆期間だけで九年間を要したことになる。当然、九ヶ年という歳月は、開発の進展と共にあり、そこに調査の濃淡を生むことにもなった。また調査の時期、天候、人との出会いなどでその成果に色々な意味で濃淡に彩りを添えたようである。また、新資料の発見、筆者自身の「成長」と「惰性」などがその上に重層し、文体・論調、そして論究の強弱など多くの面で多様性を醸し出すことになったことは遺憾である。
しかし、われわれが『出雲国風土記』、出雲古代史研究の範として仰ぎ見てきた加藤義成氏の『出雲国風土記参究』を聖書とみなす今までの研究に決別する一つの道を切り開くことができたのではないかと思っている。『出雲国風土記参究』は近世の天和三(一六八三)年に成立した岸崎佐久次時照の『出雲国風土記抄』に多くを依存しており、考えてみれば『出雲国風土記』の基本的研究は近世初頭以来のままにあるとみなすこともできるであろう。実は筆者もその延長線上で古代出雲史の研究を行い、本書を書き始めたことを正直に告白しなければならない。しかし、そこで学んだことは近世の国学の「成果」を、ただ寄り掛かる「成果」としてではなく、古代を見つめる資料として改めて吟味、評価しなければならないということであった。
また、現地を歩き、生活・社会に浸る中で、『出雲国風土記』が出雲国という地域社会の中で育まれ、成立したという事実を体感し、古代世界への繋がりを再認識することができたことも幸いである。生まれ育った地域の歴史を語る「古老」の一言に魅きつけられ、新たな事実を見いだし感動することもしばしばである。それは畦道、民家の庭先、時には民家で茶菓子を御馳走になり、現代の「古老」が語る出雲弁の伝承に耳を傾け、埋もれた史跡の案内などを請う中で得られたものである。また、公民館の書棚に眠っている郷土史家の郷土愛に溢れた冊子と出会う時、今まで顧みられることもなかった歴史研究の源泉が湧出しているのを身をもって知るのである。「古老」、郷土史に礼節を以て向き合うことが肝要である。
今までの『風土記』の神社の研究には大きな問題が宿されている。その要因は近世以降の『風土記』神社研究の「成果」に多く依ってしまった点に求められる。近世には『風土記』社の多くは不明になっていたと考えられる。果して近世の研究者の『風土記』社の比定が正しかったかを改めて問わなければならないのである。果して本『註論』の神社比定には色々と問題を孕んでいると思うが、一度はこのような研究が必須と信じたい。
出雲地域の人々の間では、明治初頭に比定された『風土記』社が古代以来連綿と『風土記』社であったという認識が何の疑念もなく息づいている場合がある。しかし、今、その『風土記』社の幾つかに疑念が出される。『風土記』社と思い、厚い信仰で守ってきたその社が非『風土記』社とされた時、社を守ってきた宮司、氏子の人々には私見に対して不満が沸き上がるであろう。しかし、出雲世界全体としては、現在でも『風土記』社を考察できる信仰空間が残されているという奇蹟的・歴史的環境を評価すべきであろう。その出雲の人々に尊敬の念を抱かざるをえないのである。
今までの『出雲国風土記』の研究は加藤氏の研究の「一雲立つ出雲」の状態であったが、ようやく「八雲立つ出雲」の世界に入ったのではなかろうか。また本『註論』では加藤氏の研究で高く評価された岸崎時照の『出雲国風土記抄』の陰の存在となりつつあった春日信風・千家俊信・横山永福・岡部春平・渡辺彜・小村重義、そして朝山皓氏の研究も出来る限り取り込むことが出来た。本『註論』の特色は出雲に足を運んでからの三十年間に及ぶ出雲の現地調査の中で出雲世界の変化を体で感じつつ、多くの方々からうかがった生の声を活かそうとした点にあると思う。
本書では『出雲国風土記』の原文校訂を行い、今までに欠けていた(1)実地調査の徹底、(2)地名の析出、(3)郷土史家の研究成果の吸収、(4)古代語の検討など「生成」的な分析方法を通し近世以来の『出雲国風土記』研究の枠を打破し、新しい古代史像を構築する「技」、歴史職人的な「技」を磨きながら、延いては日本古代史研究そのものに迫ってみたい。今、古代史研究に望まれるのは史料を読むその「技」であると考える。