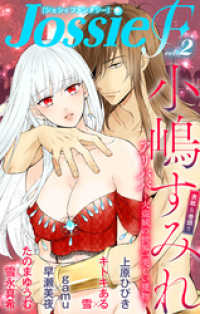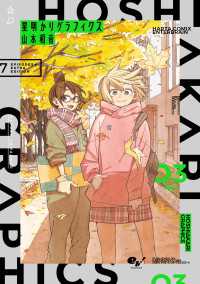出版社内容情報
国際交流・国際協力の現場で働くこととはどういうことか。これからどのような人材が求められていくのか。国際交流・国際協力の仕事を切りひらいてきた人たちが自らの経験を語る。これからこの分野をめざす人たちへの先輩からのメッセージ。
はじめに
1章 先人からのメッセージ
1.生きがいとしての国際協力
2.常に学び続ける姿勢を崩さない
2章 国際交流・国際協力の人材育成
1.グローバル化の時代を勝ち抜く人材をめざして
2.国際交流の人材育成
3.国際協力の人材育成
3章 国際交流・国際協力を仕事として
1 国際機関で働くということ
1.国際機関をめざす人へ
2.国際文化交流を仕事として
3.JICAの仕事を通じて
2 国際交流団体で働くということ
1.国際交流協会で働くということ
2.市民社会の構築をめざして
3.知的交流の担い手としてのプログラム・オフィサー
3 NGO/NPOで働くということ
1.NGOの労働環境
2.なぜNGOを志すのか
3.知ったことを伝えるために
4.社会を変える勇気と技術をどん欲に求めてほしい
5.NGOで働く喜びはミッションの実現
4 助成財団で働くということ
1.プログラム・オフィサーに従事して
2.日本財団で働いて
4章 国際交流・国際協力で求められる人材
1.国際社会と日本のシビル・ソサエティ
おわりに
はじめに
国際交流活動の実践および研究に携わってきた私たちは、日本の国際交流・国際協力が今、大きな転換期を迎えているとの共通認識を持ち、この分野の活動の重要性を社会に認識していただくとともに、この分野の仕事を志す人たちに、「国際交流とは何か」を語り継ぐ本をつくろうと、この出版を企画した。
日本の国際交流・協力活動が転換期を迎えている要因には、グローバル化の進展という国際情勢の変化に伴うものと、構造改革に伴う組織的なものがある。
自由貿易や多国籍企業のボーダレス生産など経済のグローバル化は、同時に情報通信ネットワークの進展や労働力の国際移動の拡大をもたらすとともに、地域化(ローカル化)をも伴い、地方が中央(国家)を超えて直接、海外の地方と交流し、地方同士の連携が進んでいる。一方、グローバル化には光と影の部分があり、影の部分におかれた人たちは生活が向上する機会がないばかりか、貧困、環境破壊などはますます深化しており、こうした経済格差の問題にも目を向けなければならない。また、9.11(2001年)やイギリスの地下鉄爆破(2005年)のテロリストたちは、欧米の人々のイスラム諸国への無理解と偏見に怒り、変貌していったといわれる。
もうひとつの要因は、構造改革と公益活動の見直しである。これまで、日本社会では、公共領域は行政が、私的領域は民間が担う「公私二分論」の考えで区別されていた。例外的に、公益性の高い民間活動には行政の外郭である公益法人などが担っていた。ところが、行政の財政状況が厳しくなるとともに、多様化・複雑化する社会課題に対して、行政だけで公共を担うことはできなくなってきた。そこで、NPOへの注目が集まるとともに、行政とNPOや企業セクターとの「協働」が重要課題となってきた。確かに、21世紀のキーワードのひとつは「コラボレーション(協働)」であるといえる。「協働」は、それぞれの経験や特性、得意分野が違うからこそ、その経験や情報、特性を持ち寄って連携していこうというものである。日本社会が直面している少子高齢化、在住外国人の増加による多民族化をはじめ、教育、環境、まちづくりなどの社会課題の解決においては、NPO、行政、企業などによる協働という新しい協力関係と社会システムの変換が重要となっている。また、国際社会においても、従来は国家(政府)の権限領域とされた分野を含め、平和、環境、開発、人権のあらゆる分野において、NPO/NGOが大きな役割を担うようになり、地球社会の公正かつ民主的な運営のためには多セクター間の協働が不可欠となっている。
では、こうした転換期において、国際交流・協力活動の担い手たちに求められる能力とは何か。国際交流・国際協力とはどのような仕事なのか。それを伝えようというのが本シリーズの3巻目のテーマである。
私たちがこの出版を企画して、1巻から3巻を刊行するまでに4年が経過した。この間は、まさに転換期であった。国際協力事業団(JICA)や国際交流基金(JF)の特殊法人は独立行政法人化し、自治体設立の国際交流協会においては、自治体財政の悪化による補助金の削減、行財政改革における外郭団体の見直しによる統廃合、地方自治法の改正に伴う指定管理者制度の導入など組織運営に関する問題に晒された。また、公益法人制度改革による公益法人のあり方の検討も行われている。一方、市民活動を促進するために創設された特定非営利活動促進法が施行されてから7年が過ぎ、全国には2万5000を超える特定非営利活動法人(通称NPO法人)が設立され、地方自治体では市民活動促進のための条例の成立など活動環境の整備も進んでいる。
では、国際交流・国際協力活動は地域社会の発展にどれだけ寄与できたのか、というと、社会や時代の変化に総体的に十分対応しきれていないのではないかという思いがある。近年のNPOやボランティア活動への関心の高まりに対して、公益の担い手は誰かの議論が不十分であったり、増加する外国籍住民に対しては問題対処型になっている。深化する地球規模の課題を地域住民が取り組める小さなテーマにブレイクダウンして活動を考えきれていない。日本で、地域レベルの国際交流・国際協力が広がりを見せないことの原因のひとつは、地域の活動の担い手であるNPO/NGOや自治体、大学、企業など個々の団体・機関や個人が有する経験やノウハウ、情報が社会全体のものとして共有化されていないことにもある。
これからの地域レベルの国際交流・国際協力に重要なのは、教育や福祉、環境など多分野のNPO/NGO、ODA実施機関、国際機関、大学など高等教育機関、企業・経済団体、自治体など多様なセクター間の協働である。この協働を推進していくためには、明確な問題意識を持ち、多様な人々・機関と信頼関係を築き上げることのできる「人材」の「コーディネート力」が重要になってくる。
「実践者」編は、国際交流・国際協力の仕事を志す人たちに、「仕事」を伝えようというものである。この仕事の多様性を知っていただきたく、国連や日本政府の外郭団体などの国際機関、市民レベルの活動の推進者であるNPO/NGO、地域の国際交流協会、そして、それらの活動を支援する助成団体というジャンルの仕事に携わっている方たちに執筆を依頼した。団体の創設者から管理職、中堅、若手など立場もさまざまである。第一線で活躍されている方ならではの「仕事への熱い思い」「社会変革への志」と「次世代へのメッセージ」のあふれる原稿をお寄せいただいた。また、この分野の人材育成に関しても、包括したものがなかったことから、人材育成の現状と求められる人材についてもまとめることができた。
原稿依頼から刊行までの間に、イラク攻撃、中越地震・スマトラ沖地震、ニューオーリンズのハリケーン被害などの緊急事態も起こり、発行が遅れてしまった。これも国際活動を仕事とする方たちならではである。だが、緊急人道援助だけでなく、地道な開発援助、市民の意識啓発・参加促進という活動も忘れてはならず、この間の国内外の変化に改めて、国際交流・国際協力を仕事とすることの意味を考えさせられた。
「国際交流は人に始まり、人に終わる」。これは、国際文化会館を創設された故・松本重治氏の言葉である。この言葉は、信頼関係の構築に資する人物交流の大切さをいわれたものであるが、同時に、国レベルであれ、地域レベルであれ、また組織規模の大小を問わず、活動は一人ひとりの担い手にかかっていることを言われていると思っている。いつの時代にあっても、普遍性を持ち、心の指標となる言葉だ。このシリーズの最後の巻を編集するにあたり、あらためて「人」の大切さと豊かさを知った。
この本を手にしてくださる読者、つまり、国際交流・国際協力、あるいは市民活動に携わっておられる方、今後関わりたいと思っておられる方々に、少しでも指針となり、参考になることを願っている。
そして、一人でも多くの担い手たちの実践によって、平和で豊かな市民社会が一日でも早く実現することを心から願うものである。
2006年 6月
編者 有田 典代
目次
1章 先人からのメッセージ(生きがいとしての国際協力;常に学び続ける姿勢を崩さない)
2章 国際交流・国際協力の人材育成(グローバル化の時代を勝ち抜く人材をめざして;国際交流の人材育成;国際協力の人材育成)
3章 国際交流・国際協力を仕事として(国際機関で働くということ;国際交流団体で働くということ;NGO/NPOで働くということ;助成財団で働くということ)
4章 国際交流・国際協力で求められる人材(国際社会と日本のシビル・ソサエティ)
著者等紹介
毛受敏浩[メンジュトシヒロ]
(財)日本国際交流センター、チーフ・プログラムオフィサー。兵庫県庁に勤務後、1988年より日本国際交流センターで自治体の国際化戦略、NGOや市民社会のグローバルな連携についてコーディネーション及び調査研究を担当。慶應義塾大学及び静岡文化芸術大学非常勤講師。草の根技術協力事業外部有識者(JICA)、地球市民賞選考委員(国際交流基金)。第一回及び第三回国際交流・協力実践者全国会議実行委員長。慶應義塾大学法学部卒。米国ワシントン州立エバグリーン大学行政管理大学院修士。1954年生まれ
榎田勝利[エノキダカツトシ]
愛知淑徳大学文化創造学部多元文化専攻教授。南山大学外国語学部卒業。(財)名古屋国際センター交流事業課長を経て、米国ポインツ・オブ・ライト財団の客員研究員として、NPO、ボランティア活動および日米間の国際交流の実態調査・研究をする。帰国後、国際交流基金日米センターシニア・コーディネーターとして草の根レベルの国際交流活動の推進に努める。(特活)アジア車いす交流センター理事長、愛・地球博ボランティアセンター理事長、IGL(Institute for Global Learning)代表等。専攻は国際交流論、国際協力論、ボランティア論。1945年生まれ
有田典代[アリタミチヨ]
特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会事務局長。新聞記者を経て、1997年から現職。新聞記者時代に在日韓国・朝鮮人、インドシナ難民、日系人、留学生、国際結婚をした人たちの取材を通して、人権や多文化共生、経済格差などの問題に関心を持ち、市民活動に参加。関西国際交流団体協議会は関西に拠点を置いて活動する日本で唯一の国際交流・国際協力団体の連合体。設立主体の多様な団体が多数加盟しているのが特徴。中間支援組織として、NPOの環境基盤整備、人材育成、NPOと行政機関、企業、教育機関の協働の推進、内外のネットワークの推進、市民の活動への参加促進などの業務に携わる。国際関係や市民活動に関する審議会、委員会等の委員も多数務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。