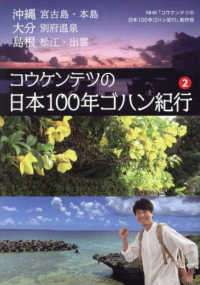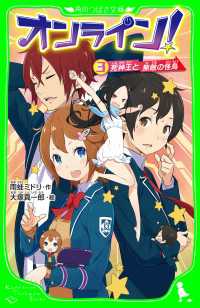出版社内容情報
主にアジアの外国人を対象に日本の技術を習得させることを目的に作られた研修生・技能実習生制度。しかしこの制度を悪用し、彼らを安価な労働力として利用しようとする企業等は跡を絶たない。本書は、その実態を描き出し、日本人の人権意識を根底から問う。
はじめに:「銚子事件」以降、何が変わったのか!?(莫邦富)
研修・技能実習制度のながれ
研修・技能実習の実態
研修・技能実習制度キーワード
外国人研修生物語――壊れる人権と労働基準
【中国・岐阜県】 寒さが厳しい岐阜の夜
――1ヶ月250時間の残業、時給は300円(安田浩一)
資料:中国人実習生Aさんからの手紙(岐阜県H縫製・2005年秋)
【中国・和歌山県】 労働組合結成から裁判へ
――残業は中国人だけ(早崎直美)
【インドネシア・徳島県】 あるインドネシア人研修生の日記
――外出、電話使用、そして礼拝と断食の禁止(イコ・プラムディオノ)
【中国・福井県】 殴る!蹴る!が日常茶飯事
――福井で起きた暴行事件(高原一郎)
資料:トウ岩(とうがん)さんの手記から(要約)
【モンゴル・長野県】 町営の施設から失踪
――国際交流と「安価な労働力」の狭間で(高橋徹)
【中国・埼玉県】 実習生の労災かくし
――資格もなしにクレーン作業(甄凱)
【ベトナム・北関東】 パスポートは誰のもの
――元研修生と難民カップルが出会うまで(平野良子)
【インドネシア・新潟県】 残業し、指を失い、それでも労働者じゃない研修生
――研修生の労災申請(川上園子)
分析と提言
数字(データ)から見る外国人研修生・技能実習生(川上園子)
外国人研修・技能実習制度をどうするか(旗手明)
――「技能実習」を廃止し、本来の「研修」に純化すべきだ!
政策提言(外国人研修生問題ネットワーク)
外国人研修生・技能実習生からの相談カード――最近の事例から
巻末資料集
.外国人研修生・技能実習生関連年表(クリッピング・データ)
.外国人研修生・技能実習生関連法令集
1.出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(基準省令)(抄)
2.出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の研修の在留資格に係る基準の五号の特例を定める件(五号告示)(抄)
3.出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の研修の在留資格に係る基準の六号の特例を定める件(六号告示)(抄)
4.出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の研修の在留資格に係る基準の七号の特例を定める件(七号告示)(抄)
5.技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針
6.研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針
あとがき(鳥井一平)
外国人研修生問題ネットワークと関係団体
執筆者紹介
はじめに
「銚子事件」以降、何が変わったのか!?(莫邦富)
私は、1998年の銚子事件(「全国生鮮食品ロジスティックス協同組合」が、中国人研修生・実習生の手当、賃金をピンはねしていた事件)で、研修制度に最初の衝撃を受け、「現代版強制連行」と表現して、その取材と報道に力を入れた。あれから年数はたったが、この制度は、その後どのように変化し、現在どのような姿をとっているのだろうか。
そもそも研修生問題は、なぜ生じたのだろうか。研修制度が、安価な労働力の受入れとして活用され始めたのは、バブル経済崩壊後である。当時、景気が非常に悪く、企業が競争力を確保するためには、少しでも人件費を削減する必要があった。そのために、企業は何でもしようと考えており、そこで飛びついたのが、研修制度だったのである。
研修制度は本来、アジアを主とした外国の人に、日本の技術などを習得させるという名目で、できた制度である。実際に大手企業などでは、海外への進出に伴って、研修生をたくさん受け入れ、技術などを覚えさせ、現地に戻して、現地での生産に日本で研修した内容を生かしている。
しかし他方で、これを単なる安い労働力として使おうとする会社、利権団体、一部のブローカーなどが現れ、彼らが結託した中で起きた一番象徴的な事件が、98年の銚子事件だった。この事件は、外国人の研修生を受け入れる協同組合の責任者が刑事責任を問われた、当時としては画期的な事件だったのである。
本来、私のジャーナリストとしての仕事は、問題を提起して、その解決の方法までたどり着けば、ある意味では終わりで、次のテーマに移ることになる。しかし、外国人研修生の受入れ問題での日本国内のいろいろな対応は、実際には、ほとんど大きな改善が見られず、一部の地域では旧態依然である。それどころかむしろ、手口がより巧妙になってさえいる。そこに、この事件を最初に報道した人間としては、ある種のむなしさを感じるし、もちろん、憤りも覚える。
さて、現在の日本を構造的に見ると、少子高齢社会を迎えている。同時に、産業構造の変化で、今までの人件費で続けていくことのできる産業が、どんどん少なくなってきており、アパレル・縫製業界がその典型である。こうした労働集約型の産業は、実際には日本では成り立たなくなってきている。そして、このような労働集約型の産業が、研修生の主な受入れ先となっているのである。したがって、研修生問題の背後には、そういう産業を無理やり日本で維持させようとしている構造的な問題があると言えるだろう。つまり、経済の面で採算が取れない産業を維持させようとすると、必ず無理が生じ、どこかにそのしわ寄せがくる。今回の場合、一番弱者の研修生こそが、このしわ寄せさせられた先に他ならない。
その意味では、経済大国と自他共に認めている日本に、こんな問題が1年、2年ではなくて、10年以上も続いてきたことは、日本の恥でもあるし、日本政府も、日本社会も正視しなければならない問題だと言える。
というのも、この問題を抜本的に解決しようとせずに、外国人研修制度を悪用する形で問題の先送りを繰り返しているだけのために、こうした外国人研修生の不幸な物語が延々と続いているからである。昔の『女工哀史』に出てくる若い女性が、飛騨の山脈を越えて、ふるさとを目前にして、雪道に倒れて、命が絶えてしまったというような悲惨な物語が、現代版の形で演じられ続けているのだ。21世紀を迎えた日本でそんなことがあっていいのだろうか。明治・大正時代の日本ではないのだ。明治・大正時代同然の現代版悲惨物語、『女工哀史』が、この日本を舞台に演じられ続けることに、私のような日本に対して理解と愛情を持っている人間としては、恥ずかしくて仕方がないのである。
以上のように、銚子事件以降、研修制度をめぐる問題は解決に向かうどころか、巧妙な手口になって広がっている。言い換えれば、矛盾が膨らんでいるということである。と同時に、問題は、非常に深刻化してもいる。たとえば、銚子事件の時代は、送出し機関としては政府系の企業が主だったのだが、今はビジネスとして広がってきている。逆に、企業も送出し機関を「派遣会社」と呼んでいる。とはいえ、彼らが言っているのは、ある意味では、非常にまともなことである。これらの派遣会社の宣伝文には、研修という言葉よりも、少子化、高齢化、農村部の過疎化、産業の空洞化など、ずばり本音が表れているのである。
もちろん、大手企業などが中国で新しい工場を立ち上げるときに、その生産ラインのキーポイントに就く人たちを日本に呼んで、事前に研修させることはある。そういう人たちは、正真正銘の研修生と言えよう。たとえば、生産ラインに問題が起きたから、調整して、数値を正常に戻すといったことに習熟した彼らが、中国に工場ができ上がったときに、班長、係長などになり、他の社員を束ねてやっていくことになる。その意味では、研修制度に合理的な一面があることは事実である。
しかし、研修生は、フル稼働の労働者ではない。そのため、彼らの賃金は、フル稼働の労働者としてではなく、研修手当という名目で支給されるだけである。したがって、不良経営者たちから見れば、そこが付け込める法的な隙間ということになり、この制度を悪用している。逆に言えば、研修制度には、このような悪用を許す隙間があるということである。
とはいえ、制度を悪用している産業構造の末端の社長たちだけを、責めても意味がないだろう。零細企業の彼らも、生き残るために必死だからだ。むしろ、この問題は、本来は産業構造という大きな流れをつかんで、解決しなければならないものである。これに対して、このような解決を先送りにし、研修生を彼らの企業に導入し続けるということは、産業構造の転換を無視した延命策をとっているだけなのである。研修生の背後にある産業構造の問題は、そのような延命策ではなく、抜本的な解決を必要としているのである。
抜本的な解決を図るためには、企業や市民団体の努力だけでは、やはり無理がある。政治家や経済団体、大手企業のトップ、そしてより多くの日本国民にもっと外国人研修生問題に関心をもち、もっと積極的に問題解決のための行動を起こしてもらわなければならない。その意味では、本書は外国人研修生問題に目を向けさせるための一つのきっかけであり、行動である。行動である以上は、問題が解決されるまで継続する必要がある。この権利白書とでも言うべき本書の継続出版をまず期待する。そして、本書の出版を必要としない社会になってほしい、と大きな期待を心の中で膨らませている。
目次
外国人研修生物語―壊れる人権と労働基準(中国・岐阜県 寒さが厳しい岐阜の夜―1ヶ月250時間の残業、時給は300円;中国・和歌山県 労働組合結成から裁判へ―残業は中国人だけ;インドネシア・徳島県 あるインドネシア人研修生の日記―外出、電話使用、そして礼拝と断食の禁止;中国・福井県 殴る!蹴る!が日常茶飯事―福井で起きた暴行事件;モンゴル・長野県 町営の施設から失踪―国際交流と「安価な労働力」の狭間で;中国・埼玉県 実習生の労災かくし―資格をもなしにクレーン作業;ベトナム・北関東 パスポートは誰のもの―元研修生と難民カップルが出会うまで;インドネシア・新潟県 残業し、指を失い、それでも労働者じゃない研修生―研修生の労災申請)
分析と提言(数字から見る外国人研修生・技能実習生;外国人研修・技能実習制度をどうするか―「技能実習」を廃止し、本来の「研修」に純化すべきだ!;政策提言 外国人研修生問題ネットワーク)
外国人研修生・技能実習生からの相談カード―最近の事例から
巻末資料集
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
燃えつきた棒
ナナ
msy3a