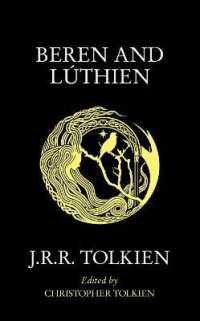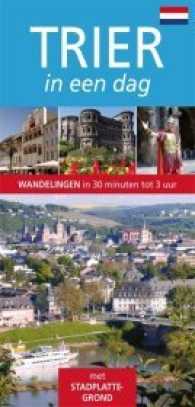出版社内容情報
幕末から明治期に滞在したコルフ島出身の英国籍カメラマン、F.ベアトが撮った貴重な写真の数々を、初公開の写真やオリジナル彩色写真を中心に収録。横浜・江戸・長崎など各地の風景、人々の風俗など、全130点(彩色78点)。巻末には新事実を網羅した解説「横浜写真小史再論」を付す。
刊行にあたって
[写真編]
1.彩られた幕末・明治
2.パノラマ風景
3.横浜とその近郊
4.各地の風景
5.アメリカの朝鮮出兵
6.サムライ
7.さまざまな職業
8.生活点描
[解説編]
横浜写真小史再論
刊行にあたって(斎藤多喜夫/横浜開港資料館)
ベアト復活
幕末開港後の横浜は、海外情報の受信基地であるとともに、日本情報の発信基地でもあった。異なる歴史と文化のもとで、それぞれ独自の道を歩んできた民族が接触する時、その歴史や文化、生活環境や人々の習慣などを情報として伝達するためには、画像が大きな役割を果たす。
15世紀後期に始まる大航海時代の当初、未知の海陸に乗り出していったポルトガルやスペインの探険者たちは、復命書の添付資料のようなつもりで、「発見」した土地の住民を捕虜にして連れ帰ったものだった。やがて画家たちが船に乗り込み、世界各地の風景や人々をスケッチするようになる。かれらの作品は、木版画や銅版画・石版画に直されたうえで、書物や新聞の紙面を飾った。
19世紀後半になると、画像情報のソースの一つとして写真が登場する。写真は迫真性のゆえに、報道と結びつくのも早く、旅行写真家や従軍写真家が世界各地で活動を始める。そのうちの何人かが幕末の日本にも足跡を印している。かれらによって、横浜の外国人居留地に画像情報の発信基地が構築される。幕末・明治の横浜は、輸出入貨物の集散地であるだけではなく、画像情報の生産地であり、集散地でもあった。
F.ベアト(Felice Beato)はもっとも活動的で多産なカメラマンであった。芸術的なセンスや技術にも優れており、多数の作品が伝えられている。しかし、顧客がもっぱら外国人だったため、日本ではほとんど知られていなかった。かつてはきまって「幻の写真家」とか「謎の写真家」などという形容が付いて回ったものだった。
日本でベアトが復活するに当たっては、横浜を中心に考えると、三つの画期があった。
一つは昭和32年5月、イギリス人F.D.バロウズ(F. D. Burrows)氏が、ベアトのアルバムを2冊携えて横浜を訪れ、1冊を横浜市へ、もう1冊を英国大使館へ寄贈された時である。開港百年祭の行われた翌33年には『横浜市史』の第1巻、34年には第2巻が刊行されたが、第2巻の口絵として、アルバムから「生麦事件現場」が収録され、ベアトの写真が知られるきっかけとなった。アルバムは市史編集室が保管し、現在は横浜開港資料館が継承している。当館の古写真コレクションの核となったアルバムである。
しかし、ベアトの存在はなお一部の人々に知られるだけだった。その作品が多くの人々の目にとまるようになるのは、バロウズ氏が横浜市へ寄贈したアルバムを紹介した『市民グラフ・ヨコハマ』24号や、英国大使館へ寄贈したアルバムの一端を紹介した『週刊読売』昭和56年4月19日号が刊行された頃からであろう。時を同じくして、昭和54年から翌年にかけて、ニューヨークのジャパン・ソサエティー・ギャラリーで「日本の写真 1854-1905」という展示会が開催され、欧米の写真史家や美術史家の間でも、ベアトの作品が注目されるようになった。この昭和53年から56年にかけてが第2の画期である。
第3の画期は昭和61年から翌年にかけての時期である。61年には朝日新聞社がオランダのライデン大学絵画写真博物館の古写真コレクションを紹介する展示を各地で開催し、これに合わせて『甦る幕末』という図録を刊行した。そのなかにはベアトの作品が多数含まれていた。そして、翌62年の2月から4月にかけて、横浜開港資料館で企画展示「写真家ベアトと幕末の日本」が開催され、合わせて『F.ベアト幕末日本写真集』が刊行されたのである。
『F.ベアト幕末日本写真集』は5回の増刷を重ね、約1万人の方々に購読していただいた。また、同書の全国普及版が明石書店より『幕末日本の風景と人びと』(1987年、絶版)として刊行された。これも3回増刷され、全国の多くの方々に手にしていただいた。
初版以降約20年の間に、当館のベアト・コレクションもより充実した。写真史上の新事実も多く発見され、解説編も古くなった。そこで当初『F.ベアト幕末日本写真集』の増補改訂版の刊行を考えたが、そうするとかなり大部の書物になってしまうし、半分以上の写真は前書と重複することになる。そのため、増補改訂版ではなく、新たに収拾した写真を収録するとともに、新事実を網羅した解説編を付して、当館所蔵ベアト写真集の第2集として本書を刊行することとした。また、当館と明石書店が連携することにより、『F.ベアト幕末日本写真集』と『幕末日本の風景と人びと』のどちらの読者にとっても第2集となるようにした。
(後略)
目次
写真編(彩られた幕末・明治;パノラマ風景;横浜とその近郊;各地の風景;アメリカの朝鮮出兵;サムライ;さまざまな職業;生活点描)
解説編
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
punyupunyu
yossy
Mizhology
nizimasu
秋色の服(旧カットマン)