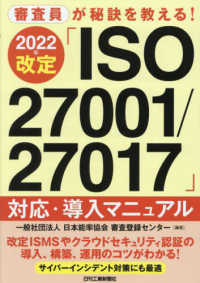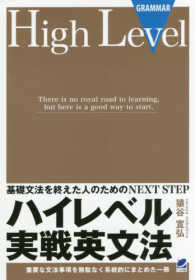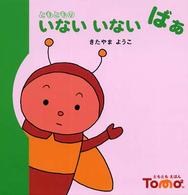出版社内容情報
生と死、ケア、バーンアウトなど心の問題から介護保険制度等、社会的制度の分析まで、看護や介護の現場で直面するさまざまな問題を社会学の視点から読み解く。本書は、看護師・介護福祉士を目指す人にとって、よい手引き書となるだろう。
はじめに
第1章 社会学とはどういう学問か
Column PTSDの症状が物語るもの
Column 映画が教える現代社会の意味1 「再生産労働力」とは何かを考える
第2章 高齢化・少子化の推移と福祉国家
Column 映画が教える現代社会の意味2 多様化する価値と崩壊するアメリカ的家族像
第3章 医療化と社会――医療の社会化の盲点
Column 病院における介護職とは
第4章 死を社会学する
Column 体で覚えている亡き利用者の感覚
第5章 キュアからケアへ――自立支援を目指す看護現場の実践的社会学
Column 患者1人ひとりが「自分らしく」生きるためには
第6章 看護師・介護士のストレスと支援の社会学
Column 病院に勤務する介護福祉士の生活
第7章 高齢者福祉政策の推移と介護保険制度改革
Column 訪問看護を体験して
第8章 研究発表をしてみよう
Column 実習で学んだ看護師の役割
Column 准看から看護婦への道
補論 高齢者福祉とボランティア――高齢者福祉ボランティアの比較調査をとおして
Column 「ニートの私」と「看護学生の私」
Column 看護師を目指している学生の皆さんへ
おわりに
執筆者紹介
はじめに
この本は看護や介護の専門学校等での講義を現在持っている教員が中心となって、看護専門学校、介護専門学校、大学看護学部、社会福祉学部等、看護師、介護福祉士を養成するコースの学生および、すでに看護師、介護福祉士として働いている方に向けて書いたものである。看護師、介護福祉士の養成コースにおいては、通常社会学の授業が置かれているが、医療、介護現場に直結するような社会学の知識や考え方を紹介するようなテキストはあまりない。また、看護師、介護福祉士が自分たちの専門性をより高めるための研修用教材にも、社会学から看護、介護の領域について考察したものもほとんどない。本書において私たちは、看護師、介護福祉士養成校における今までの教育経験から、学生たちがこれからの職業生活の中で身につけるべき、社会学の知識や考え方と、それを応用した看護、介護職現場の社会学的研究の知見を、看護師、介護福祉士のために厳選し、それぞれの立場から系統的に提示しようと思う。
現在、医療や介護の現場は技術的にも急激に変化しているのみならず、社会的使命という点においても急激に変化している。言うまでもなく、患者や利用者は1人で生きているわけではない。家族、地域社会、職場等の人間関係が患者、利用者を支えている。そして、医療施設、福祉施設は患者、利用者にとっては1つの社会であり、世界である。また、現代社会の中においては、医療施設、福祉施設は非常に重要な位置を占めており、それらのあり方が現代社会の1つの特徴を作り上げている。したがって、社会学の領域においては、医療や福祉の分野が次第に重要なものとなりつつある。看護師、介護福祉士が身近に接する患者、利用者の現状と現代社会のあり方との関係について、あるいは看護、介護という行為と現代社会のあり方との関係について、社会学の視点から見つめ直してみようというのが、この本のねらいである。
この本はまた、看護師、介護福祉士のための社会学であるだけではなく、看護師、介護福祉士自身の社会学をその中に含んでいる。看護師であること、介護福祉士であることにはどんな喜びがあるのか、あるいはそこにはどのような問題点があるのかについても多くのところで触れている。看護師、介護福祉士の(あるいはそれらになるために勉強をしている)方々が、ときに自分の立場を振り返りながら、自分を見つめ直して生きてゆくためにもこの本が扱っている社会学が大いに役に立つと著者たちは自負している。私たちはそういう意味において、この本が、看護師、介護福祉士の方々の職業生活の参考になればと願っている。
看護、介護の現場は専門性を高めつつあり、医療や福祉の専門家は常に急激な変化の中で自らを鍛えていかなくてはならない。常に変化する環境の中においては、伝統的な決まりきった枠組みはあまり参考にならない。ただ言われるままに仕事をするだけでは、その変化にはついていけなくなるであろう(専門性の低い受動的なルーティーン・ワークと専門性の高い能動的な仕事との二極化が進むことも考えられるが)。常に能動的に働きかけ、その結果を反省的にとらえフィードバックをする姿勢、このことを社会学では「再帰性」と呼び、現代社会においては、この再帰的な構えが、自己を反省的にとらえる習慣や、変化する世界の制度的なダイナミズムを作り出していると考える。医療や介護の領域では特に、この現代社会の特徴が顕著になるであろう。そういった点において、本書は専門職としての看護師、介護福祉士が専門性の高い反省的知を獲得するための知的訓練の書でもある。「再帰的」な姿勢を高めるための練習問題を各章の末尾に置き、また、最後の章は、各章を読んだ後の総合的な議論の仕方のために充てた。
須藤 廣
目次
第1章 社会学とはどういう学問か
第2章 高齢化・少子化の推移と福祉国家
第3章 医療化と社会―医療の社会化の盲点
第4章 死を社会学する
第5章 キュアからケアへ―自立支援を目指す看護現場の実践的社会学
第6章 看護師・介護士のストレスと支援の社会学
第7章 高齢者福祉政策の推移と介護保険制度改革
第8章 研究発表をしてみよう
補論 高齢者福祉とボランティア―高齢者福祉ボランティアの比較調査をとおして
著者等紹介
須藤廣[スドウヒロシ]
日本大学大学院人文科学研究科社会学専攻博士後期課程満期退学。北九州市立大学文学部教授。専攻、文化社会学、社会意識論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。