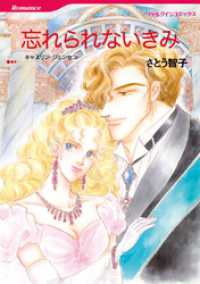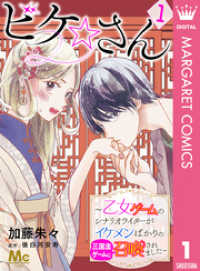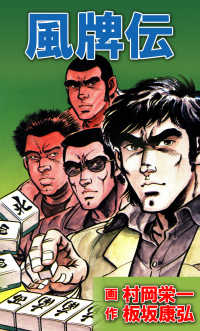出版社内容情報
現代世界の事象は、エスニシティとナショナリズムの問題を抜きにして語ることはできない。エスニック・アイデンティティの形成、国境を越えたナショナリズム、政治や宗教との関わりなど、欧米だけでなく、北欧やカリブ海地域など幅広い事例を取り上げ、人類学的視点から議論を展開する。
はじめに
第二版への序文
日本語版への序文
【翻訳に際して】
第一章 エスニシティとは何か
第二章 我と彼:エスニックな分類
第三章 文化的固有性を伴う社会組織
第四章 エスニック・アイデンティティとイデオロギー
第五章 歴史的視点から見たエスニシティ
第六章 ナショナリズム
第七章 少数派と国家
第八章 アイデンティティ・ポリティクス、文化そして諸権利
第九章 エスニックではないこと
訳者あとがき
参考文献
索 引
訳者あとがき
本書原著者エリクセン氏が指摘するように、エスニックやエスニシティという用語は、一九八〇年頃から人文社会科学の領域で盛んに登場するようになった。このことは日本にも当てはまるが、その使われ方には曖昧なことも多かったように思う。これは個人的な経験に基づく見解なので、異見をお持ちの方もおられるかもしれないが、少し触れておく。
わたしはオーストラリアでの大学院課程を修了して一九八三年の春に帰国した。留学中は、現地での少数派から見た多数派というエスニック関係にかかわる社会学的調査に基づいた修士論文で審査を受けた。日本に帰ってから、自分の論文について学部時代の先生方や仲間に報告したが、「エスニック」がなかなか分かってもらいにくかった。それで、わたしはエスニック関係を「移民研究」だと言い換えていた。もっとも、この時期日本で「移民研究」といえば、日本から新大陸、特にアメリカ合衆国へ労働移住した人びとにかかわる歴史研究を指していたように思う。その意味ではわたしの表現は正確だとはいえなかった。だが説明をしなくてもよかったので、敢えてこの表現を用いていた。これが許されたのは、当時エスニックやエスニシティという用語が、日本ではまだ新しかったからだろう。事実、一九八〇年代中頃に出版されている翻訳文献でもこれらの用語には曖昧な訳語が用いられている(たとえば本書の「翻訳に際して」参照)。
状況が変わるのは一九八〇年代後半だと思われる。その頃になると太平洋を囲む、北アメリカやオーストラリアさらには東南アジア地域での多文化・多民族状況を検証した社会学や人類学の研究が相次いで発表された。それらは学界やメディアでの注目を集めたこともあり、原語であるマルティ(マルチ)カルチャーやその派生語、さらにはマルティ(マルチ)エスニックという用語が活字メディアだけでなくテレビやラジオでも流れるようになった。それでも、エスニックやエスニシティなどの用語への対応は、依然として定まっていなかったようだ。
一九九〇年をはさんだ時期に、わたしは、ある翻訳の仕事に参加させてもらっていた。そのときエスニックを「民族」と訳すことについて、社会科学者や政治学者からはある種の留保がつけられた。学問領域によっては、「民族」という用語はネイションの訳語だと受け止める傾向があったからである。エスニックやエスニシティをめぐる論争が文化人類学界でも行なわれたのもこの時期であった。
エスニックにかかわる用語や概念が「移民」でもなく、「民族」でもなく、仮名表記で広く通用するようになったのは一九九〇年代の半ばくらいではないだろうか。この時期日本では世界各地(といっても主にアジア系)の目新しい食べ物や衣装を中心としたファッションでの色遣いが「エスニック・フード」、「エスニック・カラー」としてメディアに登場し、これらの用語の定着に一役をかった。
雑ぱくな言い方だが、こうしたマスメディアでの登場が、これらの用語をそのまま広く受け入れてもらえる土壌を作りあげたように思う(出版資本主義が国民国家形成に大きな役割を果たしたが、それは人びとの社会認識を醸成する日常的装置だからだ)。
エスニックにかかわる事象は研究しつくされたようにも思えるのだが、実際には相当な関心が今も続いている。ところがその割には、用語や概念をきちんと解説してまとめた文献となると数は意外に限られている。特に教科書的に初学者から専門家までが参考にできるように用語や意味を正面から取り上げ、事例で説明している文献となるとさらに少なくなる。そのなかで本書原著は、初版出版(一九九三年)以来、二〇〇二年の改訂を経て、一〇年以上も読者を獲得している。このことは本書原著が、数少ない好著の一つであることを示している。
日本語翻訳には二〇〇二年の改訂版を採用している。第二版では初版での第七章を二つの章に分けて、九〇年代に起こった事柄を取り上げた新しい章(第八章)が加わっている。
本書の特徴の一つは世界各地の事例を取り上げながらエスニックをめぐる事象を、従来の考え方をおさえながら、時代の先端の議論にまで言及していることであろう。加えて、興味深いのは、本書は英米の事例だけでなく、原著者の出身地である北欧の人類学の関心領域や、原著者本人の調査地であるカリブ海の状況が紹介されていることである。
エスニックやエスニシティをめぐる議論の展開などは本文を読んでいただくことにして、以下では原著者を紹介する。
原著者のトマス・H・エリクセン氏は一九六二年にノルウェーで生まれた。一九九一年に社会人類学で博士号を取得し、一九九五年以来オスロ大学の社会人類学教授の職にある。かれは学生時代から、カリブ海のモーリシャスやトリニダードで調査を実施し、現地のエスニック関係やエスニシティにかかわる事象研究を展開している。
著作活動も活発である。エリクセン氏の活動の特徴は、独自の調査研究論文を発表する一方で、初学者だけでなく専門家にとっても大変興味深い教科書的な出版を精力的にこなしていることであろう。以下にはご本人が知らせてくれた著作のなかから刊行されている文献を紹介する。
Ethnicity and Nationalism (1993/2002), Pluto Press(本書原書)
Small Places, Large Issues (1995/2001), Pluto Press
A History of Anthropology (with F. S. Nielsen, 2001), Pluto Press
What is Anthropology? (2004), Pluto Press
Engaging Anthropology: The Case for a Public Presence (2005), Berg Press
Globalisation - Studies in Anthropology (2003), Edited works included, Pluto Press
Tyranny of the Moment (2001), Pluto Press
Charles Darwin (1997), Gyldendal (Oslo)
Roots and boots: Identity dilemmas in the present era (2004), Aschehoug (Oslo)
わたし自身もこれらの著作の半分くらいを読んでいるが、どれもきわめてわかりやすく、さらには大学での授業を展開する際に大いに参考になる資料や示唆に富んでいる。人類学を中心として、英語での専門用語を学びたいと考えている人びとには参考になる文献であることを付け加えておきたい。
わたしは文化人類学を専門としてオーストラリアで調査を展開しながら、先住民を中心とする少数民族にかかわる社会・文化事象を研究している。その傍ら専門領域にかかわる文献の翻訳にも従事している。翻訳については特に専門的な教育を受けているわけではない。そのせいだろうと思うのだが、この作業は楽しいだけでなく、かなりの困難があることをいつも痛感している。
難しさの一つは、邦訳語の選択である。定着している訳語があったり、原語の仮名書きでもすでに日本語化していれば(たとえばテレビやラジオのように)、それらを使えばよいので支障はない。難しいのは、同一の用語でも専門領域の意味と日常生活での意味が必ずしも一致していないと思われるときや、邦訳するのが単純に難しいときである。
前者の例としてアプローチという言葉がある。学術の世界ではこれは分析視点というような意味で用いられている。一方日常生活では主に物理的に「近づく」という意味あいで用いられていると思われる。ゴルフの場合のパットを打つとき、男女の場合には誘いをかける際に用いられているのが、その例だろう。また、「ドライブ」というのも、「動機(づけ)」という意味で研究者は用いるが、一般には「自動車を運転する」とか、テニス、卓球などのスポーツの世界では、「ボールに回転を与える」ということが多い。これらが示すように、研究者が意図するような意味では理解されにくいような用語の例は他にも多数あるのではないだろうか。
意味の食い違いというのではないが、別の観点から一つ気にかかることがある。それは、邦訳語があるにもかかわらず、外国語の言語の発音をそのまま仮名書きにしている例である。確かに、commitやlocalのように訳出しにくい用語はたくさんあるのだが、だからといってそれらを仮名表記のままにしておくのは何となく落ち着かない。言語である以上翻訳できないことはないだろうと思うからである。それだけに、定訳としての漢字熟語がある概念などを、使用者が得意とする外国語――英語だったりフランス語だったり――を使って、それぞれの発音のまま仮名表記がなされていたりすると、どことなく釈然としないものをわたし自身は感じるときがある。
考えてみれば、fountain penの邦訳は卓越していると思う。これらの単語は、単独ではfoutainは「噴水」、penは「筆」と訳されている。ところが、二つがあわさってある種の筆記用具を意味すると「万年筆」と訳されている。一~数画ごとに墨をつけて書する日本の筆記具と比べると、西洋伝来のこの筆はなかに収納されているインク(西洋墨)がなくなるまで永々と文字や絵を描いていくことができる。この筆記用具を初めて目の当たりにした文人は、驚愕したことだろう。そして、日本の筆に対照させた訳語が生まれたのかもしれない。日本の文化・文物に対比させた、文化の翻訳のまことにうまい訳である。むやみやたらと原語の仮名表記で放っておかれていないし、訳語に文人の知ったかぶりを感じさせない。この訳を生みだした先人の才能に頭が下がる。わたしもこんな翻訳ができるようになりたいと思う。
自分の願望に反して、本書では中心的な題材のエスニックとその関連の用語が仮名書きになっている。冒頭で述べたように、これらはいつの間にか、原語の発音を仮名書きにしたままで定着しつつあるからだ、という弁解をしておくことにする。
翻訳に際しては原著者との連絡を取りあい、その意向を反映し原著以上の最新情報を取り入れている部分もある。そして正確を期すよう注意を払ったつもりである。それでもわたしの雑ぱくな性格から事実誤認や誤解があり、不明な点や誤りがあると思う。それらは訳者のわたしの責任である。皆様の叱咤とご教示、そして激励を、よろしくお願い申し上げる次第です。
二〇〇六年二月
鈴木清史
目次
第1章 エスニシティとは何か
第2章 我と彼:エスニックな分類
第3章 文化的固有性を伴う社会組織
第4章 エスニック・アイデンティティとイデオロギー
第5章 歴史的視点から見たエスニシティ
第6章 ナショナリズム
第7章 少数派と国家
第8章 アイデンティティ・ポリティクス、文化そして諸権利
第9章 エスニックではないこと
著者等紹介
鈴木清史[スズキセイジ]
総合研究大学院大学文化科学研究科修了。文学博士。帝塚山学院大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ドウ