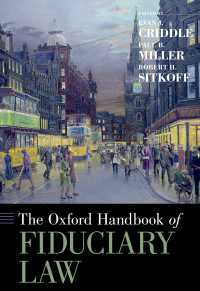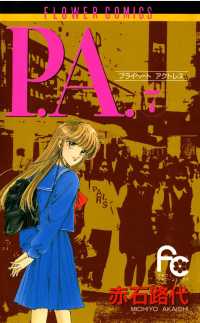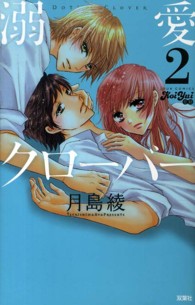出版社内容情報
グローバル化のなかで「普遍言語」として振る舞う英語の欺瞞性を暴き、「英語帝国主義」をラディカルに問う。強大言語間の言語ナショナリズムにもとづく言語戦争を否定し、思想問題として「英語支配」に対峙する言語ユートピアニズムの可能性を探る。
まえがき
〈主題の明確化のために〉
第一部 英語帝国主義の批判
第一章 英語帝国主義は実在する
第一節 「帝国」「帝国主義」「英語帝国主義」
第二節 「言語の消滅」と英語帝国主義
第三節 物事は逆さにしてみれば、本質が見えてくる─言語の非対称性
第四節 言葉は単なる基軸ではない─岩井克人批判
第五節 文化帝国主義について英語で論じることの文化帝国主義─その一
第六節 文化帝国主義について英語で論じることの文化帝国主義─その二
第七節 「世界文明戦争」における言語戦争の一端─その熾烈さ
第八節 「世界文明戦争」における言語と文化と倫理と─「卑屈支配(humiliocracy)」
第二章 言語の〈有用性・経済性〉と英語帝国主義
第三章 西欧言説の問題から西欧言語の問題へ―英語帝国主義の克服にむけて
第四章 酒井直樹の英語帝国主義論
第五章 いくつかの英語論―フィリップスン、ペニークック、クリスタル、グラッドル、立川健二の場合
第六章 英語帝国主義の憂鬱
第七章 船橋洋一の反英語帝国主義論について―『あえて英語公用語論』の場合
第二部 言語ユートピアニズム
第八章 序言―言語ユートピアニズムの必要性
第九章 世界-なき-世界性、故郷-としての-故郷喪失―言語ユートピアニズムの断想
第十章 言語における〈無・故郷〉論―反言語帝国主義的思念のための覚書き
第十一章 ジェイムズ・ジョイスの言語ユートピアニズム―インターナショナリズムにむけての断想
第十二章 ジョイス『フィネガンズ・ウェイク』の英語について―根源からの言語平等主義にむけて
結び
あとがき
主要参考文献
まえがき
本書は、英語だけが世界中に支配権を拡大行使していることに異を唱え、英語帝国主義的言語状況・言語思想を批判するための理念を語ることを目的としている。
この場合、私は、英語圏内とかフランス語圏内とか中国語圏内とかで、多言語が衝突し、さまざまな問題を生じさせていることを、『世界の言語政策』といった書物を通じて、知らぬわけではないが、ここでは、私の意識は、そういうことに注がれることなく、むしろ、それらの圏それぞれの最頂点を占める英語そのものフランス語そのものなどに注がれている。告白させてもらうと、私は、多言語共存・競合状態は言語帝国主義の許容枠内の事柄なのに――しかも“多言語”は「建前」「理想」にとどまる場合が多い――、人々が、その意識を言語帝国主義自体よりも多言語共存・競合状態のほうへと注いでいるのを、長年、あきたらない思いで眺めてきた。私の立場では、今日、全地球市民がもっとも意識を注ぐべきは、“人類の最高権力点”としての英語帝国主義それ自体以外にはないはずなのである。まずもって最高権力点のありようを問う、これは私の思考の長年の癖である。
本書を世に出すにあたって、私の想念と感慨を少しばかり語っておくこととする。
1「“世界戦争”の真只中にいるということ」
現在、私たちは暴力とテロリズムに充満した“世界戦争”の真只中に生きている、という認識は妥当な認識であると思う。たとえば、イラク戦争で、「帝国」アメリカは、「新しい中世」を始め、「世界規模の精神の敗北」をもたらし、「私たちの内面」を「蹂躙」し、「倫理の根源」を破壊した、との辺見庸の認識は誤ってはいないと思う。フランスの思想家ジャン・ボードリヤールも、「九・一一」以後、世界は「第四次世界戦争」の時代に突入したと述べている。『パワー・インフェルノ―グローバル・パワーとテロリズム』(塚原史訳、NTT出版、二〇〇三年)。
2「“英語テロリズム”“殺人言語”ということ」
こういう状況の中で、“世界語”“国際語”を僭称する英語は、世界中で、政治、経済、社会、文化、いや人間生活の全領域のみならず、人間の精神と意識の内面をも支配し、その覇権のあり方は“英語テロリズム”と称しても誤ってはいまい。このようなあり方の英語をドイツのある学術書は、“殺人言語”(the English “killer language”)と呼んでいる。ダニエル・ネトル、スザンヌ・ロメインの『消えゆく言語たち―失われることば、失われる世界』(島村宣男訳、新曜社、二〇〇一年)は「殺し屋の言語」と呼んでいる。このような形容辞を付されえる言語は、まさにボードリヤールのいうところの、あらゆる形態の他者性・異質性を排除する「グローバルの暴力」「アメリカ的システムの世界化の暴力」に見合う言語であるといえる。
3「詭弁・遁辞と思考停止は見苦しい」
“英語は、英米および他の英語国の言語という、特定の民族、国家、文化を背負った言語という枠を越えて、今や、中性的、つまり脱民族的、脱国家的媒体として、私たち自身と私たちの文化などを表現できる媒体として、ありがたい存在となっている”。この種の詭弁と遁辞。また、“もう勝負はついている”“なんといったって世界公用語だ”“しょせん必要悪なんだ”。この種の思考停止。圧倒的多数派からすれば私は大馬鹿者。だが、エドワード・サイードの「社会のなかで思考し憂慮する人間」=「アマチュア知識人」論などを念頭に、思うのである、「知識人ならば、とことんまで思考停止に落ち込まないようにしようではないか」「もっとラディカルに、つまり、もっと愚直なぐらい、ストレートに思考しようではないか」、と。
4「“感情的、倫理的、ナショナリスティック”な反英語支配論ということは妥当かどうか」
(a)私の論のような論は、非専門家による大仰な感情の吐露で、学問の没価値的純粋客観的記述となっていないと思われているらしい。しかし、「国連環境計画」、「ユネスコ」、幾人もの言語学者が、英語の世界席巻と世界の諸言語の消滅に明らかな関係があると示唆している危機的事態の中で、学問と価値・倫理の関係は根本的に再考してみる必要はないか。
(b)ナショナリズム云々については、私自身は、最初から、言語ナショナリズムの正反対の言語インターナショナリズムの精神をもって自論を語ってきたつもりである。
5「文学言語というものをもっと認めようではないか」
私は言語インターナショナリズムということをアイルランドの作家ジェイムズ・ジョイスの文学言語、また、ランボー、マラルメ、ベンヤミンなどに、学んだつもりでいる。ところが、専門的な(職業的な?)言語学者たちはどうも文学という営みがお嫌いらしい。私などは、詩人ランボーが「世界言語の時代がくるでしょう」と叫べば、それは、世界の六〇〇〇余の言語が合成されて唯一のエスペラントのような人口言語が登場するとは思わないけれども、それは、真の人間の思考には不可欠な予言的仮説、超越論的仮説として信じるに値する重要な言葉として考えるのだが……。そして、私見では、こういう仮説のいわば高みからしか、根源的な反言語帝国主義=言語ユートピアニズム=言語インターナショナリズムは考ええないのではないか、と思われるのだが……。
6「サイードの重視」
上記のことは、私の、元来、文学研究者だったエドワード・サイードへの大いなる尊重ということにつながる。サイードについては、言説と表象への彼の重視に関して、そのことは文学研究からして不可避なのだが、歴史学方面からは、批判が厳しい。が、しかし、彼の『オリエンタリズム』(今沢紀子訳、平凡社、一九九三年)は、私の『「英語」イデオロギーを問う―西欧精神との格闘』(開文社出版、一九九〇年)における言語的オリエンタリズムの批判を根本的に支えてくれている文献なのである。このことを鋭く見抜いてくれたのが右の『オリエンタリズム』下巻の「『オリエンタリズム』の波紋」という一文である。私の英語論が、「思想論」として、ある程度のオーセンティシティ(真正性)をもちえていると考える由縁である(拙著『英語帝国主義論―英語支配をどうするのか』近代文芸社、一九九七年、一八六、二三一頁、参照)。
と同時に、再びサイードだが、私は、彼の、諸専門・学問の枠を越えた“アマチュア知識人”の、世界への関わり方ということに心ひかれてきたのである。
7「“世界文明戦争”ということ」
本書の“世界文明戦争”という概念は、サイードの全業績、モロッコ有数の知識人マフディ・エルマンジュラの『第一次文明戦争―「新世界秩序」と「ポスト・コロニアリズム」をめぐって』(仲正昌樹訳、御茶の水書房、二〇〇一年)、『メガ帝国主義の出現とイスラーム・グローバル現象―イラク戦争後の世界』(仲正昌樹編、世界書院、二〇〇四年)、西谷修のいくつかの仕事、つまり、『戦争論』(岩波書店、一九九二年)、『世界史の臨界』(岩波書店、二〇〇〇年)、『増補〈世界史〉の解体―翻訳・主体・歴史―』(酒井直樹との共著、以文社、二〇〇四年)、『物騒なフィクション―起源の分有をめぐって』(フェティ・ベンスラマ著、西谷修訳、筑摩書房、一九九四年)に負うところが大きい。
ここで“世界文明戦争”というのは、軍事的戦争でも「文明間の衝突」といわれているものでもなく、もっと奥深く潜んでいて気付かれない、言説と言語のヘゲモニー性(“故郷”)をめぐる人間精神の根底に潜むギリギリの葛藤のことを指している。周知のようにサイードの「オリエンタリズム」思想は、人間のすべての発話、語り、言説がある種の偏向を蒙ってしまうことを教えてくれたが、一方の側だけが偏向をもつわけではなく偏向は相互的である。この点では、サイード『文化と帝国主義』(大橋洋一訳、みすず書房、一九九八年、二〇〇一年)「訳者あとがき」最末尾の言葉を借りると、〈諸悪の根元となってしまう相互の「故郷」〉ということが存在するのだが、そういう「故郷」と「故郷」の間の微妙きわまりない葛藤のことを、ここでは、“世界文明戦争”と呼んでいるのである。本書で第九章「世界-なき-世界性、故郷-としての-故郷喪失」、第十章「言語における〈無・故郷〉論」が書かれねばならない理由である。
エルマンジュラと西谷が示唆するように、この二一世紀初頭、“戦争の世界化”とも“世界の戦争化”ともいえるこの「世界戦争」の今、もはや、もっとも根底的に問うべきは、たとえば、西欧かイスラームか、などの問題ではなく、人類全体の文明、文化、倫理の危機の問題であって、この危機の問題は、私においては、人類の現在の完全にゆがんでしまった言語状況の危機の問題――「世界英語帝国主義」の問題――と重なり合ってしまっているのである。
二〇〇五年二月某日 著者
目次
第1部 英語帝国主義の批判(英語帝国主義は実在する;言語の“有用性・経済性”と英語帝国主義;西欧言説の問題から西欧言語の問題へ―英語帝国主義の克服にむけて;酒井直樹の英語帝国主義論;いくつかの英語論―フィリップスン、ペニークック、クリスタル、グラッドル、立川健二の場合;英語帝国主義の憂鬱;船橋洋一の反英語帝国主義論について―『あえて英語公用語論』の場合)
第2部 言語ユートピアニズム(序言―言語ユートピアニズムの必要性;世界‐なき‐世界性、故郷‐としての‐故郷喪失―言語ユートピアニズムの断想;言語における“無・故郷”論―反言語帝国主義的思念のための覚書き;ジェイムズ・ジョイスの言語ユートピアニズム―インターナショナリズムにむけての断想;ジョイス『フィネガンズ・ウェイク』の英語について―根源からの言語平等主義にむけて)
著者等紹介
大石俊一[オオイシシュンイチ]
1933年、兵庫県生まれ。京都大学大学院文学研究科修士課程修了、立命館大学、武庫川女子大学、神戸学院大学、安田女子大学、広島大学等の教壇に立ち、現在、広島大学名誉教授。ケンブリッジ大学客員フェロー。専門は現代イギリス文学(ジェイムズ・ジョイス)、モダニズム文学、イギリス地域研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゴリラ爺