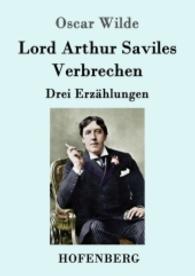出版社内容情報
9.11米同時テロ後のアフガン空爆、ターリバン政権の崩壊そして復興支援で改めて国際社会の注目を浴びたアフガニスタン。政治プロセス、治安改革、復興支援…「破綻国家」の再建に日本はどのような役割を果たしたのか?最前線で国づくりを支援した特命全権大使の2年半におよぶ駐在記録。
はじめに
第一章 国造りの柱1――政治プロセス
1 暫定政権――二〇〇一年一二月~二〇〇二年六月
暫定政権発足式/カルザイ大統領とアフガン復興支援東京会議/緊急ロヤ・ジルガ
2 移行政権――二〇〇二年六月~新大統領選出まで
憲法制定/大統領選挙と議会選挙/選挙と軍閥解体/大統領選挙成功の秘密
第二章 国造りの柱2――治 安
1 治安情勢
治安攪乱要因
2 対テロ作戦
アフガン国内の対策/パキスタンでの対策/米国の取り組みの変化
3 ISAF(多国籍治安維持支援軍)の活動
繰り返される主導国探し/NATOスケッフェル事務総長
4 治安改革
五つの問題/二〇〇三年は模索段階
第三章 国造りの柱3――復 興
1 復興への道のり
すさまじい破壊の跡/復興支援のシナリオ
2 アフガンの主導的役割
ガーニ財務相のがんばり/カブールの援助国会議/新通貨の導入/今後の開発目標
第四章 国際社会の取り組み
1 国連の役割
ブラヒミ代表の大きな存在/国連の役割を限定/国連アフガン支援団(UNAMA)
2 米国のベルリン会議での目標設定/ファヒーム国防相主催の国防評議会/DDRの手順/達成不可能となった中間目標/七・二三事件/DDRを急速進展させた出来事
6 DDRと外交
日本にとっての可能性/米中央軍本部とNATO本部を訪問
第七章 日本のアフガン支援
1 緒方総理特別代表のアフガン訪問
緒方代表の仕事/カブール・テレビ局で感動
2 緊急人道支援
教育支援/保健・医療支援/文化協力
3 治安分野での支援
対人地雷除去支援/DDR
4 緒方イニシアティブ――地域総合開発
アフガン難民の帰還/緒方イニシアティブの着眼/「人間の安全保障」の実施
5 日本の援助戦略
「平和の定着」構想/国別援助計画の策定――総花化を排す/草の根無償資金協力にも実施の指針
第八章 私のアフガニスタン
1 カブールの生活
カブールに金(きん)はなくとも/変貌してゆく町/家賃の騰貴/合宿生活/世界一小さな公邸/腸チフスを患う
2 大使の役割
宮原公使の着任/大使にしかできないこと
3 全国を旅する
地方へは簡単には行けない/交通手段と
はじめに
二〇〇一年九月一一日、米国における同時多発テロ事件の発生後、同年一〇月、米国を中心とする連合軍によるアフガニスタン(以下差し支えない限りアフガンと略記する)のアルカイダ・タレバン攻撃、一一月タレバン政権の崩壊とその後のアフガンの和平・復興支援と続く流れの中で、アフガンは、改めて国際社会からの脚光を浴びた。二一世紀の初頭、しかも、軍事・経済いずれをとっても世界ナンバー・ワンの米国の力の象徴である世界貿易センターのツイン・タワーとペンタゴン(国防総省)の建物が、ハイジャックされた民間航空機によって攻撃(前者については倒壊)されたことで、当然のことながら米国はもとより世界の受けた衝撃はきわめて大きかった。
未曾有の国際テロ事件を引き起こしたアルカイダとそれを擁護し国内に訓練基地を提供していたタレバン政権に対する軍事作戦の勝利はあっという間に成し遂げられたが、その後のアフガンの平和と復興作業はそうはいかない。タレバン政権時代も含めて二三年間にわたって内戦状態の続いたアフガンに残されたものは、文字どおり破壊と悲惨の二語である。私も現地に行って唖然とした。道路はがたがたに壊れ、水・電気・電話などの近代生勤務の条件を備えているものは少ないかもしれない。しかし、私とてアフガン行きを打診されて、ただちに受けたわけではない。
一九七〇年に外務省に入省して以来、私は、イランのシラーズで二年間ペルシャ語研修を受けたのを含め現地で計一〇年、東京の外務本省での勤務三年を加えれば合計一三年間をイランとかかわりながら過ごした。しかしながらアフガンとのかかわりとなると、イランでの二年間のペルシャ語研修の最後のころに、一度訪れたのみである。そのときは、往きは飛行機でテヘランからカブールまで行き、カブールでは新装成ったインターコンチネンタル・ホテルに宿泊したこと、ジープで悪路を振り落とされそうになりながらバーミアンを訪れ大仏を見たこと、帰りは陸路バスでカンダハール・ヘラートを経由しイランのマシャドまで戻ったことなどを、アフガン行きを打診された際にかろうじて思い出す程度であった。最近の十数年間はイランとも離れ、どちらかというと援助すなわちODAの関係の仕事に従事することが多かった。
そんなわけで、米国での9・11同時多発テロ事件以降、現地語に通じ経済協力の専門家でもある私にいずれお鉢が回ってくることはぼんやりとは覚悟していた。決心がついた。今、二年半にわたった現地での職務を果たして日本に戻って来て、改めて娘の言ったとおりだと思う。
これから、現地での私の個人的な体験を中心にアフガン復興の歩みを詳しく紹介させていただくが、一人の外交官が任国の大統領はじめ閣僚や地方指導者(軍閥)、また国連や各国の大使・司令官などと密接に付き合いながら、アフガン復興という共通の目標に向かって仕事ができ、しかもそうした努力の結果が、遅々としたものではあるが現実の変化として実感でき、任国の国民に喜ばれるというのは、そうめったにあるものではない。私の外交官生活で、もっとも苦しく、しかし充実した二年半であったと思う。一生の思い出となり財産となった。日本にいては、絶対に得られない体験であった。
(中略)
本書では、私が現地で実際に体験したことを中心として、アフガン復興の歩みを述べていく。
国が破綻し国民の生活状況も世界で最悪の部類に属するアフガンの平和と復興の実現のためには、三つの大きな事業を同時に進める必要があった。民主的な政治体制を築くための政治プロセス、新たな国軍造りや武装解除など治安回復のための諸改革、および、経済再建と福祉向上のための開発る見込みとなっている。DDRを進める過程で、カルザイ大統領はじめ関係閣僚、軍閥指導者、国連の代表や各国大使、アフガンや各国の軍司令官たちと密接に付き合うこととなり、こうした人たちとの協議や駆け引きを通して大変貴重な経験をさせてもらった。第六章では、DDRの技術的な側面のみならず、DDRを進めようとする努力の中で垣間見たアフガンと国際社会の奥行きといったものを中心に論じた。
私がアフガンに赴任する直前に、東京でアフガン復興支援会議が開催され、緒方アフガン支援総理特別代表が、共同議長として会議の成功に大きな役割を果たされた。緒方代表は〇四年一二月まで代表を続けられ、その間、毎年のように現地を訪問された。私も日本への一時帰国のたびに代表にお会いして、報告するとともに示唆を仰いだ。緒方代表には、その後もJICA理事長としてアフガン支援にはことのほか気を配っていただいている。第七章では、緒方代表の知恵が大きく反映している日本のアフガン支援計画形成の背景を論じた。
第八章は、現地の事情を紹介しつつ私の大使としての喜びと悲しみを綴った。現地の雰囲気を理解していただくためにはこの章からお読みいただくのもよいであろう。として私だけしか経験しえなかったような事柄を中心に記述している。
もとより日本の支援が現地で高く評価してもらえるようになったのも、厳しい環境の中で、邦人の一人一人が、また全員が一致してがんばった結果である。そのことを改めて指摘し、名前は列挙しないがお一人お一人への感謝の気持ちの表明としたい。
目次
第1章 国造りの柱1―政治プロセス
第2章 国造りの柱2―治安
第3章 国造りの柱3―復興
第4章 国際社会の取り組み
第5章 地方復興チーム(PRT)
第6章 軍閥解体(DDR)
第7章 日本のアフガン支援
第8章 私のアフガニスタン
第9章 平和構築支援実施のために
著者等紹介
駒野欽一[コマノキンイチ]
1947年2月、東京生まれ。東京外国語大学アラビア語科中退。1970年、外務省入省。イラン・シラーズ市のパーラビ大学でペルシャ語研修。在外では、イラン(2回)・インドの日本大使館およびジュネーブの日本政府代表部に勤務。国内では、外務省経済協力局調査計画課長、大臣官房参事官(アフリカ担当)などを歴任。2002年4月より駐アフガン特命全権大使として、現地語(ダリー語・ペルシャ語)と経済協力の経験を生かして日本のアフガン復興支援を現場でリード。2005年9月より特命全権大使として東京で、NGO・アフガン支援調整・人間の安全保障を担当
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 集団語の研究 〈下巻〉