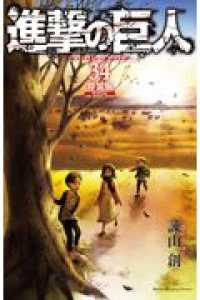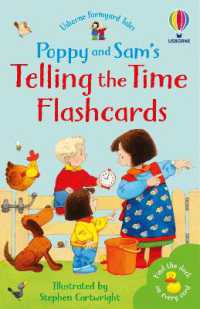出版社内容情報
歴史的都市の多くは、江戸時代の城下町を起源にしている。これらの街の生活記録にこそ、都市の原像、都市生活の本質が潜んでいる。日本人が自明のこととして了解していた事柄に改めて光を当てる資料集成。本巻では、外国人から見た都市生活の記録も収録。
序
凡例
第三巻 伝統のなかの都市/序(内田忠賢)
1 伝統的都市
2 伝統のなかの京都と諸城下町
3 近代の伝統的都市
4 新しいまなざし
1 京の生活誌
京都 町なかの暮らし(寿岳 章子)
京の室町(西村國三郎)
明治四十三年京都―ある商家の若妻の日記(中野 卓編)
解説(村上忠喜)
2 城下町の風俗・民俗
四谷旧事談(山中 笑)
松前年中行事(高倉新一郎)
秋田の昔有情(洞城庄太郎)
くらし
1 衣食住の特色(今村 充夫)
2 通過儀礼(今村 充夫)
3 年中行事と地域性(小林 忠雄)
4 信仰と宗教(小林 忠雄)
5 民俗芸能と伝承(小林 輝冶)
6 方言(砺波 和年)
洞津城下旧事談――明治末~大正初期――(堀田 吉雄)
長崎風物誌(本山 桂川)
解説(牛島史彦)
3 異国人から見た都市
徳島の盆踊(モラエス(花野富蔵訳))
釜ヶ崎はワタシの故郷(エリザベス・ストローム)
GEISHA[芸者]―ライザと先斗町の女たち(ライザ・ダルビー(入江恭子訳))
歌舞伎町ちんじゃら行進曲(
序
都市はいまや我々の生活の主要な場となった。生活のあらゆる場面にその影響を見いだすことができ、我々の生活それ自体が都市化された。都市は村落と対置される存在ではなくなった。かつて日本民俗学は、村落生活を主要な対象としつつ日本の民俗文化を究明しようとした。都市の生活は、その変化の著しさの故に相対的に軽視された。しかし、都市と村落とは本来相補的な存在であった。政治・経済・文化の中心としての都市は、村落からの人や物資の供給を得ながら地域の中心たりつづけた。したがって、日本の民俗文化を総合的に把握しようとするとき、いずれかを欠くことはできないはずであった。とりわけ都市的生活様式が普遍化してきた状況下において、村落に注いだのと同質の視点をもって都市をも把握する必要があったのである。
そこで、都市の民俗と生活文化とを把握するために、ここに「都市民俗生活誌」の幾つかを集めてみた。これは都市に暮らす人々の、伝統と文化が織り成す生活実態の記録である。しかも文字を用いることが容易にできた都市生活者が、自らその日常生活を記録したものである。
その多様な都市生活を把握するために、「都市民俗の生成」、「都市の活力」、「伝統なるはずである。
『都市民俗生活誌』編集委員
有末 賢
内田 忠賢
倉石 忠彦
小林 忠雄
目次
1 京の生活誌(京都 町なかの暮らし;京の室町;明治四十三年京都―ある商家の若妻の日記)
2 城下町の風俗・民俗(四谷旧事談;松前年中行事;秋田の昔有情;くらし;洞津城下旧事談―明治末~大正初期;長崎風物誌)
3 異国人から見た都市(徳島の盆踊;釜ケ崎はワタシの故郷;GEISHA(芸者)―ライザと先斗町の女たち
歌舞伎町ちんじゃら行進曲)
著者等紹介
有末賢[アリスエケン]
1953年、東京都生まれ。1982年、慶応義塾大学大学院社会学研究科社会学専攻博士課程修了。慶応義塾大学法学部教授。都市社会学、生活史研究専攻
内田忠賢[ウチダタダヨシ]
1959年、三重県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程中退。お茶の水女子大学大学院人間文化研究科助教授。人文地理学、日本民俗学専攻
倉石忠彦[クライシタダヒコ]
1939年、長野県生まれ。1963年、国学院大学文学部卒業。国学院大学文学部教授。日本民俗学専攻
小林忠雄[コバヤシタダオ]
1945年、石川県生まれ。1971年、早稲田大学大学院文学研究科芸術学専攻特殊学生修了。北陸大学教授。民俗学、考現学専攻
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 呪われ皇子と暮らすことになりまして! …
-
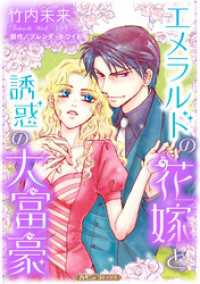
- 電子書籍
- エメラルドの花嫁と誘惑の大富豪【新装版…