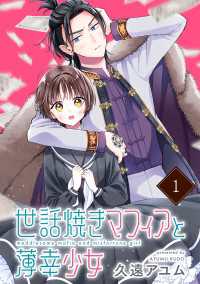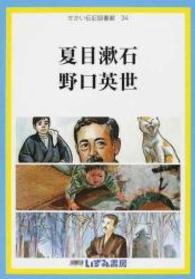出版社内容情報
日本では歴史の浅い非営利・助成財団の社会的な役割を、その中核的な担い手であるプログラム・オフィサーに焦点をあて体系的に位置づけた実践用の理論書。フィランソロピーの歴史や役割、運営上の倫理と経営方法など、米国での豊富な経験をもとに分析する。
プロローグ 財団、その歴史・構造・社会的役割
米国における財団の歴史/民間財団の原型、カーネギーとロックフェラー/相次ぐ財団の設立/1969年の税制改正法/米国の財団、その種別と構造/財団、その社会的役割/財団プログラム・オフィサーの役割
第1章 助成活動を意味あるものにする
助成スタイルの選択/事業形態の選択/社会的認知度の高さを選択する/優先助成分野を設定する/優先助成分野を設定するための五つのステップ/結論
第2章 助成活動における人的要素
フィランソロピーの誘惑/助成申請者の権利の章典/プログラム・オフィサーとしてどのような資質を身に付けるべきか/結論
第3章 申請者との関係構築
助成活動――関係性の上に成り立つ共同事業/確実なコミュニケーションに必要な項目/申請者との電話対応と面談/プロジェクト・ファイルの保存/同僚との関係/結論
第4章 申請書の審査
タイプ別に見る申請書/アイディアと申請書の関係性/申請書のゴーストライター/門番となるか執事となるか/優れた申請書に見られる12の特徴/活動の継続と評価/予算/事業実施能力の判断/結論
第5章 申請書を不採択とする
申請書が不採択となる四応答を終えて/プログラム・オフィサーと理事会との関係/結論
第10章 プロジェクトのマネジメント
プロジェクト・マネジメント、その可能性と現実/マネジメントの落とし穴/助成事業のマネジメント・テクニック/プログラム・オフィサーによる実務サポート/コンサルタントの利用/助成金の支払い停止と助成の取り消し/助成終了の戦略/結論
第11章 プロジェクトの終了
助成を継続すべきか否か/助成先からの報告を意義あるものにする/完了総括報告書/教訓を役立てる/結論
第12章 インパクトの強化
事前にインパクトを増やす/事業実施中にインパクトを増やす/事業終了後にインパクトを増やす/結論
第13章 いかに政策に影響を与えるか
財団の公共政策恐怖症/財団にできないこと/財団にできること/非営利団体にできないこと/非営利団体にできること/政策インパクトの類型/明白なイデオロギーを持つか、イデオロギーに中立か/政策枠組みを構築する/公共政策メッセージをつくる/政策活動における関係のあり方/影響力を持つために政策を使う/公共政策と民意/結論
第14章 財団主導型の助成
財団主導型の助成、その長所と短所/財団主導型の助成事業
はしがき
はじめに
助成財団の仕事には、人材養成コースも資格検定試験もなければ、正式な研修制度もほとんど存在しない。助成活動の実務について断片的に書かれた文献はあるが、そのほとんどは、定期刊行物や雑誌・モノグラフ、もしくは年次報告書などに短い記述として散見され、体系化されているものは極めて少ない。相当の決意を持って根気強く文献に当たらないかぎり、財団スタッフが助成という仕事の全体像を把握することは難しいが、仮にそうしたとしても、プログラム・オフィサーの役割と責任について書かれた箇所はほんの僅かで、そこにも綻びが目立つであろう。
内側の視点から書かれたプログラム・オフィサーの実務
本書は、プログラム・オフィサーのあらゆる職務に関し、経験に基づいて考察した初めての試みである。本書は、包括的なマニュアルでもチェックリストでもなく、能力と倫理観のあるプログラム・オフィサーになるために必要不可欠なスキルについて解説した入門書である。特に、新人プログラム・オフィサーが、その実務における基本原則について理解するのを助ける目的で書かれているが、ベテランのオフィサーにとっても、自分の仕事を見直すための材料として助成活動とは使命か専門職か」「どんな人物が助成活動に携わるべきか」「フィランソロピーの七つの誘惑にいかにして打ち勝つか」といった問いが投げかけられる。第3章から第14章までは、プログラム・オフィサーの基本的な業務、すなわち、申請者との関係構築、申請書の審査、申請書の不採択、現地訪問、申請事業案の推薦とプレゼンテーション、プロジェクトのマネジメントと評価、事業のインパクトの強化、財団主導型の助成など、順に取りあげる。最終章では、助成の倫理について触れ、エピローグでは、フィランソロピーの未来について展望する。
助成財団におけるプログラム・オフィサーは、いわば、貴重な資金を預かる執事のような存在であり、その資金は、しばしば、進歩と停滞、発展と衰退の違いを生み出すことを可能にする。公益のために、効果的かつ倫理的な投資を行う能力を高めることにより、その資金がもたらし得る可能性を最大限にすることは、助成財団とプログラム・オフィサーにかかっているのである。それがゆえに、私は本書を著し、読者であるあなたにお届けしている次第である。
2000年1月 ミシガン州カラマズーにて
ジョエル・J・オロズ
目次
財団、その歴史・構造・社会的役割
助成活動を意味あるものにする
助成活動における人的要素
申請者との関係構築
申請書の審査
申請書を不採択とする
申請書への対応
現地訪問
推薦理由書の作成
推薦理由書のプレゼンテーション
プロジェクトのマネジメント
プロジェクトの終了
インパクトの強化
いかに政策に影響を与えるか
財団手動型の助成
助成の倫理
フィランソロピーの未来
著者等紹介
オロズ,ジョエル・J[オロズ,ジョエルJ][Orosz,Joel J.]
ケロッグ財団において、フィランソロピー/ボランティア部門のプログラム・ディレクターを務め、現在は、グランバレー州立大学の教授として、フィランソロピー研究に関して教鞭をとっている。カラマズー大学歴史学学士、ケース・ウェスタン・リザーブ大学歴史学/博物館学修士、および歴史学博士を取得。ケロッグ財団に入るまで、カラマズー公立博物館において学芸員として勤務。1997年に出版した『万人のために―ミシガン州のフィランソロピー史』では編者を務め、同書は1999年にカウンシル・オン・ファウンデーションズの初の情報功労部門特別賞を獲得した。その他にも米国古銭学会と古銭文学会の賞を3回受賞している。カウンシル・オン・ファウンデーションズの法制委員会委員長をはじめポインツ・オブ・ライト財団のプログラム委員会、ミシガン財団協議会の政府関係委員会、アスペン・インスティテュート非営利セクター研究基金のミシガン非営利研究プログラム諮問機関など、数多くの組織や委員会のメンバーを務めている。また、ミシガン・コミュニティ・サービス委員会の理事も務める。ミシガン州カラマズーに住んでいる
牧田東一[マキタトウイチ]
桜美林大学国際学部助教授
長岡智子[ナガオカトモコ]
財団法人国際文化会館
小林香織[コバヤシカオリ]
財団法人笹川平和財団
鈴木智子[スズキトモコ]
財団法人日本国際流通センター
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。