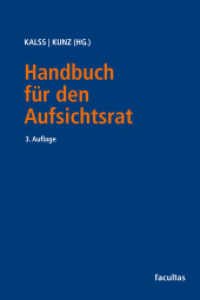出版社内容情報
大日本帝国時代、海外植民地ですすめられた言語政策はどのように機能し、どのような問題を残したのか。「多文化、多民族状況下での日本語」という今日的問題関心をも刺激する論考。
序
第一部 序論 国語と近代日本と
第二部 日本の言語政策と植民地
第一章 日本に植民地言語政策があったか
第二章 「外地」における日本語教育
第一節 台湾
1 発端
2 台湾における日本語教育の歴史的展開
3 伊沢修二の政策構想と理念
4 台湾人と日本語
第二節 満洲国
1 満洲国の「国語」
2 新学制とその背景
3 満洲国の統制方策
4 社会教育と語学検定
5 満洲カナと「協和語」
6 日本語普及の裏
7 関東州の日本語
第三節 大陸占領地
1 日中戦争以前の日本語
2 興亜院の日本語普及政策
3 興亜院の日本語教員派遣と日本語教育振興会
4 日本語普及の実態
第三章 淪陥下北京の言語的憂鬱
第一節 北京淪陥後
第二節 秦純乗と国府種武
第三節 教授法に纏わる葛藤
第四節 山口喜一郎の鬱憤
第五節 政治性・文化性と技術性
第三部 近代日本の言語思想 ――日本語論にみる言語イデオロギー
第一章 言霊と近代日本語
第ける日本語教育の意味
第四節 膨張の論理と「日本文化」
第五節 日本語の復権
終わりに 多文化、多言語社会に向けて――結論に代えて
跋
参考文献
付録 「言語の権利に関する世界宣言」
索引
事項索引
人名索引
文献索引
序
「日本の植民地言語政策研究」というテーマに取り掛かってから、光陰矢のごとしで、はやくも二〇年近く経とうとしている。その時と今と比べれば、世の中が大きく変動したことは言うまでもないことであろう。当時の日本についていえば、八〇年代後半の異常な「好景気」(いわゆるバブル)に伴う「日本の国際化」、次いで「日本語の国際化」などがさかんに議論されるようになり、さらに「国際文化」という奇妙な漢字語が流行り始め、このことばを冠した大学の学部と学科も雨後の筍のように現われ、現在では、優に百を超えているのである。一方、世界第二位の経済大国となった日本は、その経済力をバックに、東南アジアおよび中国などへ経済・技術・資本と人的移転と、言語・文化面での進出が一段と活発になってきた。国内労働力の不足に伴う外国人労働者と留学生など日本に入国した人数も鰻上りの一途であった。
しかし、国際化とは何か? グローバリゼーションとは何を意味するのか? という問題をめぐって、現在の世界におけるもろもろの状況も含めて、歴史を振り返り、虐げられた民族とその言語、文化、さらに周縁文化、少数文化の立場にたって考え直すことは、きわめて重要なことであえて公刊するものである。
本書は四部から構成している。
第一部「国語と近代日本と」では、近代日本における「国語」概念の成立という問題を提起し、植民地における日本語教育と「国語」概念との関連、さらに植民地が日本の言語学と言語観念に与えた影響を踏まえて「宗主語」と「隷属語」という、二つの新しい社会言語学的概念を提唱する。
第二部「日本の言語政策と植民地」では、実証的な研究を通して、日本はいわゆる「外地」における言語政策の復元を目指す。第一章では、まず「日本に植民地言語政策があったか」という疑念に対して、学校教育をはじめ、社会生活の各分野においてさまざまな言語面での統制が行なわれ、計画的に日本語の普及が図られた歴史的な事実を指摘した。第二章では、台湾、満洲国、大陸占領地など、各地における日本語普及政策の具体的な展開を追っている。「台湾」の部分では、近代日本の植民地言語政策の発端に位置するその施策の背景、日本語教育の展開、とくに日本の近代植民地教育の開拓者である伊沢修二をめぐり、その政策構想と理念に光を当て、また台湾における日本語普及の実態とその理念の後への影響について追跡した。「満洲国」の節では、満で、日本語論のさまざまな側面を取り上げ分析をした。そのうえで、日本の言語政策に顕著に現われたいくつかの特色を、宗主語イデオロギー、国家的・軍事的支配との癒着、言語政策の多元性、日本語学校、とまとめている。
第四部「日本語文法と帝国意識――多文化、多言語社会に向けて」第一章では、日本の植民地言語政策と言語認識が、近代日本の学問に、どのように影響を及ぼしてきたのかということを、主に時枝の文法理論に光を当てて分析を試みる。日本の文法理論の中でも異色な存在であった時枝の言語理論の成り立つゆえんは、植民地の現場において教育に携わっていたその「場面」が、大きく作用していたのではないかと指摘する。近代日本の植民地支配のもたらしたもの、日本の学問形態に対する内的影響という視点から問題提起であった。第二章「帝国意識と日本語」では、思想史と近代文化史の視点を踏まえながら、日本の植民地言語政策および近代言語理論、言語認識の性格を考察した。
戦前から戦中に、そして戦後にかけて「日本語」に関わる事態が大きく異なってきた。第二次大戦の終結からすでに半世紀以上経っており、今年はその六〇周年を迎える。今、再び世界へと進出しはじめ
目次
第1部 序論・国語と近代日本と
第2部 日本の言語政策と植民地(日本に植民地言語政策があったか;「外地」における日本語教育;淪陥下北京の言語的憂鬱)
第3部 近代日本の言語思想―日本語論にみる言語イデオロギー(言霊と近代日本語;宗主語と隷属語;日本語とはどういう言語なのか ほか)
第4部 日本語文法と帝国意識―多文化、多言語社会に向けて(植民地教育と日本語文法の成立;帝国意識と日本語;多文化、多言語社会に向けて―結論に代えて)
著者等紹介
石剛[セキゴウ]
1954年、中国に生まれる。博士(Ph.D)。河北大学卒業。一橋大学社会学研究科博士課程単位取得。現在成蹊大学文学部教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。