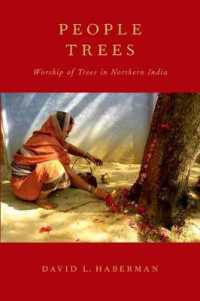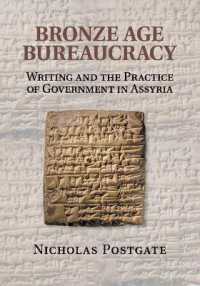出版社内容情報
衰退状況にあったアメリカの体育が、1980年代以降新たなパラダイムに立つフィットネス教育プログラムの開発へと収斂している状況を明らかにし、青少年の体力の持続的低下傾向や生活習慣病が増加するわが国に、適用する意義と可能性を提言する。
序章 体育の危機とアカウンタビリティー
第1節 体育の衰退と教育改革
体育衰退の危機/わが国の教育改革と体育
第2節 子どもの身体と教育
からだへの危機感/体育と身体の教育/スポーツ文化の隆盛
第3節 体育と健康・フィットネス問題
ライフスタイルの変化/高齢化社会の到来/子どもの健康と運動
第4節 アメリカの学校体育の概況
アメリカの教育改革と体育の危機/健康福祉省審議会報告書/健康関連フィットネスへの注目/フィットネスへの役割認識と新しいプログラム
第5節 研究動向と本書のねらい
研究動向/本書のねらい/本書の構成/用語定義
資料・注・文献
第1章 アメリカにおける教育改革の進行と体育の危機
第1節 教育改革の流れと特徴
アメリカの教育制度の概要/教育の平等を実現する流れ/20世紀半ばからの教育改革の流れ/1980年代以降の教育改革/「教育の優秀性」を目指す教育改革の特徴
第2節 体育の危機
強まる体育の危機感/教育改革が体育に及ぼす影響/体育衰退の傾向――体育の履修状況の変化/体育指導者の資格/NASPEの報告書に見る体育の衰退と問題点
注・文研究/身体活動に関する心理行動学的研究の動向/審議会報告書『身体活動と健康』に見る研究動向
第3節 学校体育への要請
研究者による要請/研究組織による要請/身体活動についてのガイドラインの作成
資料・文献
第4章 体育におけるフィットネス目標
第1節 体育におけるフィットネス目標重視の傾向
フィットネス重視に影響を及ぼした社会的要因/教育改革の進行とフィットネス目標/高まるフィットネスへの責任意識/体育に対する社会的要請としての健康・フィットネス
第2節 体育におけるフィットネス目標の位置づけ
体育のナショナル・スタンダードにおけるフィットネス目標の位置づけ/体育カリキュラム研究者によるフィットネス目標の記述/フィットネス研究者によるフィットネス目標の記述/体育論者によるフィットネス目標の記述と批判
文献
第5章 新しいフィットネス教育プログラムの開発
第1節 新しいフィットネス教育プログラムの概観
多様なフィットネスプログラム/中・高校生,大学生のためのプログラム/小学生のためのプログラム/フィットネステストを中心としたプログラム
第2節 AAHPERDによる Physi
2.本書のねらい
学校教育課程において体育が必修から外されたり、単位数や時間数が削減されるなどの衰退の状況は世界的な傾向である。ことにアメリカではこの傾向が顕著で、高等学校では1年間だけの必修が一般的になりつつあるという。
一方で、産業技術の発展などの社会変化は、人々の運動不足や栄養摂取の偏り、ストレス過多などを生み出し、生活習慣病の増大など健康不安や医療費の増加を招くことになった。このような健康問題は、学校体育に対しその存在意義の1つとして、健康・フィットネス問題に関する役割を期待していると認められる。
本書では、1980年代以降、アメリカの体育がフィットネス教育にそのプライオリティーを見出し、新たなパラダイムに立つフィットネス教育プログラムの開発へと収斂している状況を検討している。検討の焦点は次の3点に集約できる。
(1)近年の教育改革において危機に立つ体育とその対応の状況
(2)健康・フィットネス問題に対する体育の役割
(3)新しいフィットネス教育プログラムの開発とその特徴
3.本書の構成
本書は序章から終章まで、9つの章から構成されている。
序章においては、本研究の背景として教育改革、特に学校体育に関する施策に注目した。また、健康関連フィットネスへの注目や健康と運動との関連についての研究成果から、学校体育が求められている役割に言及した。
第4章では、教育改革の進行と健康・フィットネス問題の浮上によって、体育においてフィットネス目標を重視する傾向の表われていることに着目した。体育がその役割として子どものフィットネスへの責任意識を高めていく過程について言及し、ナショナル・スタンダードや研究者等の論述においてフィットネスがどのように位置づけられているかについて考察した。
第5章では、1章から4章までに述べた体育を取り巻く状況の変化に伴って、新しく開発されているフィットネス教育プログラムについて検討した。数多く開発されているフィットネス教育プログラムを概観し、そのうち、AAHPERDによるPhysical BestとCorbin and LindseyによるFitness for Lifeについて、その理念、内容などについて考察した。
第6章では、新しく開発されたフィットネス教育プログラムがその理念や内容において、これまでの体力づくりのプログラムとは異なる内容を持つものであることを明らかにした。これまでの体力づくりのプログラムが批判を受けて
目次
序章 体育の危機とアカウンタビリティー
第1章 アメリカにおける教育改革の進行と体育の危機
第2章 危機打開に向けての議論とストラテジー
第3章 健康・フィットネス問題の復活と体育への要請
第4章 体育におけるフィットネス目標
第5章 新しいフィットネス教育プログラムの開発
第6章 フィットネス教育プログラムの変容
第7章 わが国の保健体育への示唆
終章 まとめ
著者等紹介
井谷恵子[イタニケイコ]
京都教育大学教授、博士(学校教育学)。専門、体育科教育学、スポーツ・ジェンダー学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。