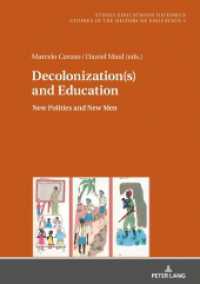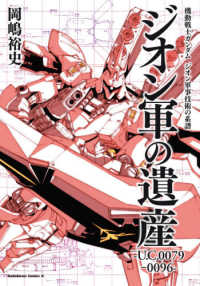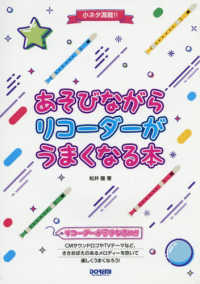出版社内容情報
NGO、NPOの活動は近年国際的に高く評価されるものもあるが、「公的領域で活動する、国民の自発自立的な組織や団体の領域」としての「市民社会」はまだ成長途上にある。本書はNGO、NPOが持つ制約や限界を提示し、それをどう克服するか論究する。
はじめに
第一章 「市民社会」とは
第1節 いくつかの定義
第2節 NGO・NPO
第3節 現代的な意味
第4節 クニとの関わり
第5節 市場との関わり
第6節 モノサシあるいは鏡
第7節 利益グループか否か
第8節 活動領域
第9節 公と私
一 官・民との関わり
二 その区分
三 日本の場合
第二章 「市民社会」論の背景
第1節 これまでに見えてきたこと
第2節 まだ見えていない背景
第3節 民主主義
一 いくつかの問題
二 正統性と答責性
三 任意の申し合わせ
第4節 市場経済
第5節 国際社会
一 クニとの関わり
二 クニにできないこと
第三章 「市民社会」論の吟味
第1節 その弱点
第2節 市民社会の効率性
第3節 コーポラティズム
第4節 市民社会の正統性・答責性
第5節 市民社会の正統性(近代国家の場合)
第6節 市民社会の答責性(近代国家の場合)
第7節 市民社会の正統性・答責性(国際社会の場合)
第四章 「市民社会」論の実効性
第1節 市民社会組織の資
はじめに
民間非営利組織(Non Governmental Organization、以下NGOと略す。あるいはNon Profit Organization、以下NPOと略す。語義については第一章第2節で詳説する)に対する期待が高い。阪神・淡路大震災以来、国内での認知度の飛躍的な向上が通称NPO法(平成一〇年法律第七号・特定非営利活動促進法)を生んだのはその一例だが、ことは日本の国内にとどまらず、国際問題も視野に入るようになってきている。
「二一世紀を、政策思考の対象にしようとする者にとって」、「行動している現代世界の行動主体は一体誰かを考えてみると、『シビリアン・パワーの先兵』と呼ばれるNGO以外にはなさそうに思われる」といった論調はその代表的なものだ。
さらに、「多元主義と自由に見出す価値観」を体現し、「市場の失敗」と「政府の失敗」を補う希望の星としてのNPO、という見方はきわめて魅力的で、「公的領域で活動する、国民の自発自立的な組織や団体の領域」としての「市民社会(Civil Society)」の議論が、ここにきてにわかにさかんになったのも、この傾向のいわば集大成であると言ってよい。
ちなみにこれは何も国内現象にとどまらないのは先に述べた通りで、例を問わず妥当するとは限らない。民主主義は貴い。民主主義の真髄は多数決だ、だから一足す一が二になるかどうかは多数決で決めよう、というのと似たような過ちをおかしかねないということだ。それにとどまらず、この種の過大評価は必ず逆方向へのバックラッシュを生む。現実に則したその能力の見きわめが必要な所以である。
ではいったいNGO・NPOのもつ制約や限界とはなんなのか。そのうちどれほどのものが原理的・本質的なもので、どれがなんらかのかたちで克服できるものなのか。それをNGO・NPO機能論の集大成としての「市民社会」論を中心に検討してみようというのが本論の目的である。
目次
第1章 「市民社会」とは(いくつかの定義;NGO・NPO ほか)
第2章 「市民社会」論の背景(これまでに見えてきたこと;まだ見えていない背景 ほか)
第3章 「市民社会」論の吟味(その弱点;市民社会の効率性 ほか)
第4章 「市民社会」論の実効性(市民社会組織の資源調達;資源の偏在 ほか)
第5章 結論に代えて―「市民社会」論の将来(文脈の整理;クニとの関係 ほか)
著者等紹介
入山映[イリヤマアキラ]
1939年生まれ。63年東京大学法学部卒業。日本国有鉄道(当時)、日本航空を経て、1982年U.S.‐Japan Foundation(米日財団)東京事務所代表。86年笹川平和財団設立と同時に常務理事(事業担当)。93年同理事長。立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。