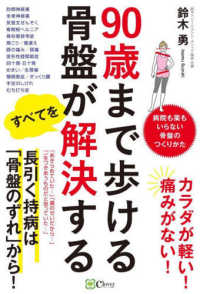出版社内容情報
社会問題として認識されはじめた高齢者虐待。アメリカ、オーストラリア、カナダ、ノルウェー、およびラテン・アメリカ諸国における高齢者虐待防止への取り組みの現状を、各国を代表する研究者が解説。日本の高齢者虐待防止策を講ずるうえで貴重な一冊。
はじめに
1 アメリカの高齢者虐待防止プログラムの現状
1. 高齢者虐待の広がり
2. 高齢者虐待の防止
3. 高齢者虐待の早期発見
4. 結 論
2 オーストラリアの高齢者虐待防止・発見システム
1. オーストラリアにおける高齢者虐待の背景
2. オーストラリアにおける高齢者虐待防止
3. 高齢者虐待発見・対応システム
4. 結 論
3 カナダの高齢者虐待早期発見・防止システム
1. はじめに
2. 高齢者虐待の実態
3. 歴史的背景――介入プロトコルの作成
4. 介入システム
5. 高齢者虐待およびネグレクト防止システム
6. 身体的虐待およびネグレクトの早期発見システム
7. カナダのプログラムとサービス(とくに虐待問題を対象とするもの)
8. カナダにおける高齢者虐待およびネグレクトに関する研究
9. 結 論
4 ノルウェーの高齢者虐待予防・早期発見システム
1. 家庭外で起こる高齢者の虐待(路上暴力)
2. ノルウェーにおける家庭内高齢者虐待の研究
3. 高齢者介護施設――その暗部――
4. ノルウェーの「高齢者保護サービス」機関の発展に向けて
本書『世界の高齢者虐待防止プログラム──アメリカ、オーストラリア、カナダ、ノルウェー、ラテン・アメリカ諸国における取り組みの現状』は、じつは、原文の英語版を2003年にアメリカで出版し、その後日本語版作成に向けての作業が始まる予定であった。しかし、諸々の事情で、英語版の刊行が中止になって、翻訳作業を急がせた結果、本書の出版がこのたび実現したのである。本書の執筆者らと共に、これまで、長年にわたって高齢者虐待の研究やアドボカシー活動に関わってきた私にとって、彼女たちの著作物を日本に紹介できることは、うれしいかぎりである。高齢者虐待に関する日本の文献は数多くあるが、本書のように、複数の国の問題に対する取り組み方がその国を代表する研究者によって書かれたものはない。そのような文献は、アメリカでも珍しいので、本書の英語版が企画されたのであった。
本書からもわかるように、高齢者虐待は、世界の多くの国で、深刻な社会問題として認識されているが、その問題への対応は多様である。対応が法制化されていて、高齢者虐待防止法かそれに似た法律が確立されている国もあれば、対応策が取られていない国もある。また、被虐待者やその家族に対すは今やグローバルな社会問題で、世界レベルの対応が必要である」という判断を国連が下したことを意味していた。
本書の執筆者は、全員INPEAと重要な関わりがあるということを付け加えたい。まず、老人専門研究医のリア・スザナ・ダイチマン(アルゼンチン)は、INPEAの現会長である。続いて、看護学教授のエリザベス・ポドニークス(カナダ)は、最近副会長に着任した。老年学研究者のパトリシア・ブラウネル(アメリカ)は、INPEAのアメリカ代表で、国連担当理事である。さらに、老人専門臨床医のスーザン・カール(オーストラリア)は、INPEAのオセアニア地域代表理事である。そして、上級ソーシャルワーカーのオーラグ・ユークレスタ(ノルウエー)は、INPEAノルウエー代表を同組織の開始当時から務めている。最後に、私は、1997年のINPEAの創立に参加した後、しばらく経理担当の理事を務めたが、現在は、アジア地域代表理事である。これらの執筆者の幾人かとこれまでにも共同で研究を行った経験があるが、執筆者全員で1つの目的の達成のために作業を遂行したのは、本書のプロジェクトが初めてであろう。執筆者たちの協力に対して厚い感謝の意を表したい。
本書のためのでない職員たちが一所懸命努力する毎日が続いているのである。(後略)
内容説明
本書では、わずか数ヵ国の例しか登場しないが、それらの国々の高齢者に対する考え方や高齢者虐待防止プログラムの仕組みを紹介している。
目次
1 アメリカの高齢者虐待防止プログラムの現状(高齢者虐待の広がり;高齢者虐待の防止 ほか)
2 オーストラリアの高齢者虐待防止・発見システム(オーストラリアにおける高齢者虐待の背景;オーストラリアにおける高齢者虐待防止 ほか)
3 カナダの高齢者虐待早期発見・防止システム(高齢者虐待の実態;歴史的背景―介入プロトコルの作成 ほか)
4 ノルウェーの高齢者虐待予防・早期発見システム(家庭外で起こる高齢者の虐待(路上暴力)
ノルウェーにおける家庭内高齢者虐待の研究 ほか)
5 ラテン・アメリカの高齢者虐待への取り組みの現状(高齢者虐待は新しい問題ではない;アルゼンチンの人口と諸々の問題 ほか)
著者等紹介
ブラウネル,パトリシア[ブラウネル,パトリシア][Brownell,Patricia]
フォーダム大学・大学院社会福祉担当(Fordham University)助教授。ハートフォード財団ソーシャルワーク特別研究員(Hartford Foundation)で、高齢者虐待防止国際ネットワーク(INPEA)のアメリカ合衆国代表。国連の高齢対策NGO委員会のINPEA代表者。研究専門分野は、老年学、高齢者虐待、家庭内暴力(ドメスティック・バイオレンス)で、この方面で多くの著作物を発表。30年以上にわたり、ドメスティック・バイオレンス、高齢化問題、公共福祉の分野で積極的に活動している
カール,スーザン[カール,スーザン][Kurrle,Susan]
シドニー北西部在住の老人病治療専門医。ホーンズビィ・クーリンガイ病院(Hornsby Ku‐ring-gai)リハビリ・高齢者看護部門の主事。1992年からニュー・サウス・ウェールズ州「後見審判所」メンバー。高齢者虐待防止国際ネットワーク(INPEA)オセアニア地域代表。高齢者虐待についての数多くの論文、書物を発表。その他の研究対象分野として、痴呆症への対処方法、股関節部骨折予防用保護器具の使用法などがある。また、シドニー大学医学部の臨床講師であり学生指導教官でもある
ポドニークス,エリザベス[ポドニークス,エリザベス][Podnieks,Elizabeth]
トロント・ライアソン・ポリテクニック大学(Ryerson Polytechnic University)看護学部教授。高齢者虐待防止国際ネットワーク(INPEA)副会長、「高齢者虐待防止委員会(USA)」役員。またケム・ジャクソン(Cam Jackson)市民権省大臣と共に「州高齢者虐待円卓委員会(Provincial Elder Abuse Round Table)」共同議長。高齢者虐待問題についてカナダ人社会が理解をもつ重要な一歩となった画期的な高齢者虐待調査を、1991年にカナダ全国を対象に実施。高齢者虐待の分野で著作研究を多数発表。1999年には、その業績により「カナダ賞(The Order of Canada)」を受賞している
ユークレスタ,オーラグ[ユークレスタ,オーラグ][Juklestad,Olaug]
オスロー大学「暴力に関する情報と研究のノルウェー資料センター」の上級顧問。ソーシャルワーカーとしての経歴、また主要病院や高齢者センターの運営に携わった経験をもつ。1991年から1994年にかけ、オスローで行われた研究プロジェクト「高齢者保護サービス(Verne for Eldre)」のマネージャー。同プロジェクトは現在のオスロー高齢者保護サービスの先駆けとなる。虐待への意識覚醒と理解の普及を目的とした資料、多数の論文、また書物1冊を発表。現在は、ノルウェー人高齢者について、ノルウェー高齢者が虐待をどのようにとらえているかについての調査研究のまとめに向けて研究作業中である
ダイチマン,リア・スザナ[ダイチマン,リアスザナ][Daichman,Lia Susana]
ベルグラノ大学(Belgrano University)心理学部准教授。ブエノス・アイレス大学老人医療特別大学院生コースのコーディネーター。過去15年間、老年学と老年病学に関する論文を多数発表。科学技術研究調査国際審議会(CONICET)、ベルグラノ大学、ブエノス・アイレス大学で老年学関連研究調査を実施。ジュネーブのWHOと共同で老年学関連研究調査を実施。アルゼンチン診療治療研究所の老年学・老年病学顧問。高齢者虐待防止国際ネットワーク(INPEA)世界会長。ラテン・アメリカ高齢者虐待防止委員会委員長でもある
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 財務報告基準設定論