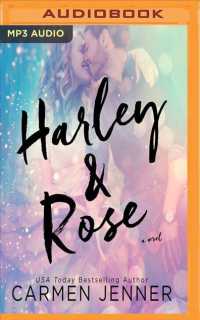出版社内容情報
里親養育の重要性は高まっているにも関わらず、制度そのもの、養育される子どもの現状については殆ど知られていない。専門里親制度など改革の要点から、諸外国の現状、養育で実際に出会う問題点、里親への研修と支援まで、制度の全体像と理念を知る最良の書。
第1章 はじまった里親制度改革
1 里親制度とは
2 わが国における里親制度の発展
3 危機にある里親制度
4 里親制度改革とその意義
第2章 わが国の里親制度の現状
1 里親制度の現状
2 里親委託のしくみ
3 養子縁組・特別養子縁組
4 里親制度が発展しない理由
5 里親制度に関わる民間団体
6 里親制度をめぐる資料・提言・図書・報告書・研究論文
第3章 創設された専門里親制度
1 専門里親制度創設の背景
2 専門里親モデル実施調査研究委員会による検討
3 専門里親制度の概要
4 専門里親制度の課題
第4章 里親と委託された子どもの状況と意識
1 「里親の意識および養育の現状について」調査結果(庄司ほか、一九九九)
2 「養護施設入所児童等調査結果の概要」(厚生労働省雇用均等・児童家庭局、二〇〇一)
3 「成人里子の生活と意識」調査(家庭養護促進協会神戸事務所、一九八四)
4 「養育家庭での生活体験に関するアンケート調査」(東京都養育家庭センター協議会、一九九八)
第5章 諸外国における里親制度
1 社会的待)の防止
7 子どもの自立
8 実親との関わり
9 実親への支援
10 里親家庭の人間関係
第9章 里親への研修と支援
1 里親研修
2 専門里親研修
3 支援のあり方
第10章 施設養護の現状と課題
1 社会的養護における施設養護の位置
2 乳児院
3 児童養護施設
4 施設に入所している子どもの発達と行動
5 虐待をする保護者への援助
6 施設での養育と里親養育
7 里親養育に施設ができること
第11章 里親制度・里親養育推進のための提言
1 国および地方自治体に対して
2 児童相談所に対して
3 児童福祉施設に対して
4 里親および里親会に対して
5 研究者に対して
6 地域の人々に対して
フォスターケアとは里親養育を意味することばである。「里親」ということばはよく知られている。しかし、その制度、あるいは里親としての養育に関しては、限られた一部の関係者を除いて、ほとんど知られていないのが現状であろう。
里親養育については本文中で詳しく論じることになるが、要するに、家庭での養育を必要とする子どもをわが家へ引き取り、親子として、家族として、あるいは生活共同者として、いっしょに暮らし、互いを理解しながら、子どもの成長を目指す営みといえよう。法制度にもとづくものではあるが、暮らしの中で緊密な感情の交流が生じる。ここにこそ里親養育の意義があるのだが、他方、このことが里親養育のむずかしさをももたらすのである。
本書は、フォスターケア、すなわち里親養育の現状と課題について論じたものである。本書のタイトルを「フォスターケア」としたのは、筆者が「里親」ということばに若干の抵抗を感じているためである。しかし、ことばの問題は第1章で検討することにしよう。
本書では「里親養育」を主に取り上げるつもりではあったが、里親養育は、里親制度と密接な関連があり、また、最近、里親制度が大きく変わったので、はじめに予定かに養育するために――里親として子どもと生活をするあなたへ』がQアンドAによってわかりやすく整理しているので、本書では里親制度、里親養育の基礎にある考え方を主に論じるようにした。
本書では、主な読者として、里親、里親になることを希望する人、児童相談所や児童福祉所管課の関係者、児童福祉領域の研究者と学生を想定しているが、施設関係者、保健師、小児科医、小児精神科医、心理士などの方々にも読んでいただけることを望んでいる。というのは、里親養育の実践にはこれらの専門領域の方々の理解と支援が不可欠だからである。
はじめに 著者
内容説明
本書は、フォスターケア、すなわち里親養育の現状と課題について論じたものである。「里親養育」を主に取り上げるつもりではあったが、里親養育は、里親制度と密接な関連があり、また、最近、里親制度が大きく変わったので、はじめに予定したよりも里親制度について触れるところが多くなった。本書では、主な読者として、里親、里親になることを希望する人、児童相談所や児童福祉所管課の関係者、児童福祉領域の研究者と学生を想定しているが、施設関係者、保健師、小児科医、小児精神科医、心理士などの方々にも読んでもらいたい。
目次
第1章 はじまった里親制度改革
第2章 わが国の里親制度の現状
第3章 創設された専門里親制度
第4章 里親と委託された子どもの状況と意識
第5章 諸外国における里親制度
第6章 里親養育の基本となる考え
第7章 里親養育の実際
第8章 里親養育において出会う諸問題
第9章 里親への研修と支援
第10章 施設養護の現状と課題
第11章 里親制度・里親養育推進のための提言
著者等紹介
庄司順一[ショウジジュンイチ]
1949年東京都に生まれる。1975年早稲田大学大学院文学研究科心理学専攻修士課程を修了。同年東京都職員(心理技術職)となり、1979年より都立母子保健院心理指導員。1992年恩賜財団母子愛育会日本総合愛育研究所(現日本子ども家庭総合研究所)主任研究員。94年企画室長、97年研究企画・情報部長。1999年青山学院大学文学部教育学科教授、現在にいたる。日本子ども家庭総合研究所福祉臨床担当部長(非常勤)。1983年川崎市にて里親登録。専門は臨床保育学、子ども虐待、里親養育、乳児院での養育
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
-

- 和書
- 時間と存在 (新装版)
-

- 電子書籍
- ハネムーンは授業のあとで【マイクロ】(…