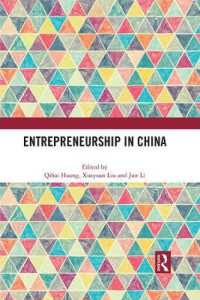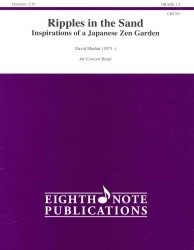出版社内容情報
偏見や差別を認識し、立ち向かうことを可能にする多文化主義を学校文化に根付かせるための教員・管理職ガイド。
第一章 文化的多様性を理解する
アメリカの教育における文化的多様性の現状
文化とは何か?
競合するモデルとアプローチ
統一と多様性―本質的な緊張関係
歴史的視座から見るアメリカの経験
競合する視座
多文化主義擁護の主張
多文化主義とTQE
第二章 偏見と差別を認識し正面から立ち向かう
偏見と差別を理解する
偏見の本質
差別の本質
偏見と差別の相互関係
人種主義、性別主義、年齢主義、その他
差別と権力を検証する
差別をなくす―いくつかの活動とアプローチ
第三章 生徒の教育機会を制限する構造的な障壁を取り除く
間接的差別
教育機会に対する基本的な障壁を取り除く
学力別グループ分け
生徒指導
学校施設―魅力的なものか、それとも刑務所のようなものか
試験に関する諸問題
カリキュラム
教えるという実践
教師、生徒、家族の限定された役割
第四章 教職員の力量向上とカリキュラム開発の促進
学校における多様性
学校管理職―プラクシス(実践)の役割モデル
文化に適切に対応した教授方法
多様性を高める―ートを提供すること
知的な刺激を与えること
高い達成期待をもつこと
文化的多様性―キャンディ瓶の中のハラペーニョ
多文化教育や人権教育のあり方について、とくに近年さまざまなふりかえりや議論が行われてきました。これは、多文化共生、反差別、人権といったテーマが、日本社会においてますます重要性を高める一方で、それに対応する教育論が十分に確立されていなかったために、教育実践の現場において、さまざまなとまどいが生じてきたからです。とくに、当為の学とされる教育学に、多文化共生、反差別、人権といった「正義の理念」が結びつくと、場合によってはとても「反民主的」で特定の価値観やものの見方を押しつけるようなやり方に流れる可能性があることを、心に刻んでおく必要があるでしょう。
「教え込みではなく、これからは参加・体験型が有効だ」と、ゲーム的な手法を含むさまざまな「参加・体験学習」のやり方が、一九九〇年代の半ばごろから注目され、学校教育や社会教育の現場に広がりました。それらは効果的な学びを活性化させる着想や方法論を備えていたものの、他方では表層的な実践にとどまってしまうことも多かったように思われます。従来の多文化教育や人権教育におけるある種の行き詰まり状況に対して、「ほんものの学びはどのようにして起こるのか」「真正な学びの論理にもとづいたきや経験を個人レベルのストーリーにとどめるのではなく、どのように組織的に蓄積し、まとまりをもった教育環境づくりに反映していくのかという視点や戦略が、これまでどうも弱かったように思うのです。(後略)
訳者序文
内容説明
著者たちは学校における文化的多様性に関するさまざまな研究や著作を概観できるような本を出版したいとの思いで、本書を執筆しました。アメリカのほとんどの学校に、それが地方であれ、郊外であれ、都市部であれ、どこに立地しているかにかかわらず、英語が第一言語ではない生徒、教師、地域住民が存在しています。著者たちは学校の校長や他の管理職が多様性を肯定的にとらえ、教師がその専門的な力量向上を通じて、社会の主流ではない人種・エスニック・文化集団の家庭を含むすべての子どもたちにより良いかたちで学習を保障できるようにすることが、とても重要だと考えています。著者たちは学校における社会正義の実現を強く支持しており、この問題に関する著者たちの信念や考え方を学校管理職の皆様と分かち合うための試みとして、本書を書きました。
目次
第1章 文化的多様性を理解する
第2章 偏見と差別を認識し正面から立ち向かう
第3章 生徒の教育機会を制限する構造的な障壁を取り除く
第4章 教職員の力量向上とカリキュラム開発の促進
第5章 学校と地域と家族の連携の強化
第6章 多文化的なエートスを支えること
第7章 TQEリーダーシップ―変化するパラダイムに対応するための新しいスキル
著者等紹介
コルデイロ,ポーラ・A.[コルデイロ,ポーラA.][Cordeiro,Paula A.]
サンディエゴ大学教育学部長。前の勤務先コネチカット大学では教育リーダーシップ(Educational Leadership)の分野の修士および博士プログラムのコーディネーターを、ベネズエラやスペインのインターナショナル・スクールでは教員や校長をつとめた。各種編集委員会の委員、インターナショナル・スクール校長協会(AISH)理事。学校リーダーシップ分野で博士号を出している研究機関の国際組織である教育経営大学協議会(UCEA)前総裁。サンディエゴ大学教育学部では彼女のリーダーシップのもと、サンディエゴ市立学校のすべての学校管理職に対して研修を行っている
レーガン,ティモシー・G.[レーガン,ティモシーG.][Reagan,Timothy G.]
コネチカット大学教育リーダーシップ学科で教育政策研究と教育言語学を担当。これまで公立学校と大学の多文化教育プログラムに深く関わり、アメリカや海外のさまざまな文化的・言語的マイノリティ集団の教育に関連した各種著作を出してきた
マルチネス,リンダ・P.[マルチネス,リンダP.][Martinez,Linda Pitt]
テネシー州にあるヴァンダービルト大学から教育学修士(M.Ed.)および教育学博士(Ed.D)を取得している。現在、ビジネスおよび教育組織のためのリーダーシップにおける差異と創造性に関する国際コンサルタントである。アメリカ合衆国内務省インディアン局の学校で校長をつとめたり、ワシントンDCにあるインディアン教育プログラム局で仕事をしたりしたことがある。以前、コネチカット大学で助教授をつとめ、現在、ニューメキシコ州のサンタフェ大学とアリゾナ大学で特任教授の立場にある。アリゾナ州ツーソン在住
平沢安政[ヒラサワヤスマサ]
大阪大学大学院人間科学研究科教授(人権教育学)。1954年大阪府生まれ。78年大阪大学人間科学部卒業。89年ハーバード大学教育大学院博士号取得(Ed.D)。中学校教員、国際会議通訳者を経て現職。社会的活動としては大阪府人権協会理事、大阪府人権施策推進審議会委員など
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
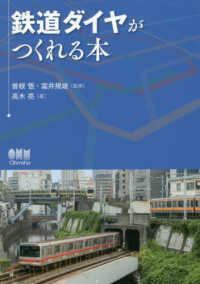
- 和書
- 鉄道ダイヤがつくれる本
-

- 和書
- インドー傷ついた文明