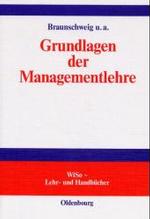出版社内容情報
近代郵便はイギリスの制度をそのまま導入したという従来の説を覆し,近世の宿駅,飛脚制度との関連・連続性の中で発達してきたことを史料を活用し論証する。歴史学界において空白の分野に一石を投じる。
一 近世交通・通信の特質について―東海道宿駅における書状逓送を中心に
二 京都・高岡間の書状逓送日数―『幕末維新風雲通信』より
三 東海道守口駅での御用状継立の変遷過程―継飛脚より郵便へ
四 東海道草津駅の郵便創業
五 東海道守口駅の郵便創業―近世宿駅制度崩壊過程と関連して
六 明治四年三月の郵便物数と郵便利用者―石部駅の郵便創業史料より
七 日米郵便交換条約の意義について―在日外国郵便局の設置と撤退
八 大阪における創業当時の郵便機関の変遷
九 軍事的警察的通信制度―飛信 滋賀県下の実態
十 明治前期郵便線路の拡張と地方開発―滋賀県下,石部・信楽間の場合
十一 朝鮮植民地支配と日本郵便機関の役割について
付論一 立ち消えた書信館―幕末における郵便局設置案
付論二 「郵便」という名称―前島密の新造語ではない
付論三 前島密のアピール
目次
1 近世交通・通信の特質について―東海道宿駅における書状逓送を中心に
2 京都・高岡間の書状逓送日数―『幕末維新風雲通信』より
3 東海道守口駅での御用状継立の変遷過程―継飛脚より郵便へ
4 東海道草津駅の郵便創業
5 東海道守口駅の郵便創業―近世宿駅制度崩壊過程と関連して
6 明治四年三月の郵便物数と郵便利用者―石部駅の郵便創業史料より
7 日米郵便交換条約の意義について―在日外国郵便局の設置と撤退
8 大阪における創業当時の郵便機関の変遷
9 軍事的警察的通信制度 飛信―滋賀県下の実態
10 明治前期郵便線路の拡張と地方開発―滋賀県下、石部・信楽間の場合
11 朝鮮植民地支配と日本郵便機関の役割について
付論1 立ち消えた書信館―幕末における郵便局設置案
付論2 「郵便」という名称―前島密の新造語ではない
付論3 前島密のアピール
著者等紹介
薮内吉彦[ヤブウチヨシヒコ]
1926年大阪市に生まれる。1944年大阪府立豊中中学校卒(旧制)。1947年大阪高麗橋三郵便局長拝命。1987年同定年退職。郵便史研究会会長、交通史研究会会員、大阪歴史学会近代史部会会員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
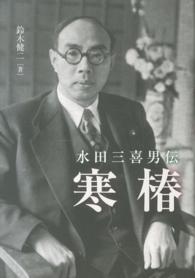
- 和書
- 寒椿 - 水田三喜男伝