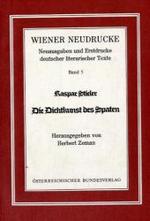内容説明
「景観」で何がわかるのか?現在の学術的な潮流のなかで、なぜ「景観」という概念が注目されているのか。人工と自然、人間と環境、物質と精神、可視性と不可視性といった二分法的な視点をこえて、人類学・考古学の分野で新たな知見を生みつづけている「景観」論の思考方法とその研究成果を横断的に紹介する
目次
人類学と考古学の景観論―その研究動向と課題
第1部 景観という視座(「景観を」ではなく「景観で」考える―交差点としての景観研究の布置;現代人類学で景観を問う意義を考える)
第2部 環境・記憶・モニュメント:景観で考える考古学(景観で考えるモニュメンタリティ―ペルー北海岸のマウンド・ビルディングを事例に;自然地形から神殿へ―アンデスの神殿を景観から考える;景観をめぐる時間の多様性―繰りかえし築かれ、利用される神殿;火山灰が創る景観;絡み合いの景観論―祭祀景観をめぐる民族考古学的試み;考占学における景観概念を捉えなおす―「景観」概念の整理と方法論的課題)
第3部 認知・言説・マテリアリティ:景観で考える人類学(霊性との呼応から創出される景観―ラオス南部の水辺集落における浄化儀礼から考える;景観の物語を語る―住まうことの重層性;景観とイマジネーション―ペルー北部山村の暗闇における不可思議な体験談から;視覚イメージと言説実践―神戸南京町の景観形成をめぐって)
著者等紹介
河合洋尚[カワイヒロナオ]
東京都立大学人文社会学部・准教授。1977年、神奈川県生まれ。2009年、東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程修了。博士(社会人類学)。専門・研究テーマ:社会人類学、景観人類学、フードスケープ(食の景観)論。中国南部と環太平洋地域を結ぶヒト(特に客家)、モノ、景観のマルチサイト民族誌
松本雄一[マツモトユウイチ]
国立民族学博物館人類文明史研究部/総合研究大学院大学先端学術院・准教授。1976年、茨城県生まれ。2010年、イェール大学大学院博士課程修了。PhD.(Anthropology)。専門・研究テーマ:南米考古学、文明形成論。中央アンデスにおける神殿を中心とした社会の成立と崩壊をめぐる考古学的研究
山本睦[ヤマモトアツシ]
山形大学学術研究院(人文社会科学部担当)准教授。1978年、大分県生まれ。2009年、総合研究大学院大学文化科学研究科博士課程単位取得退学。博士(文学)。専門研究テーマ:アンデス考古学。文明の形成過程、モニュメント、地域間交流、文化遺産(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。